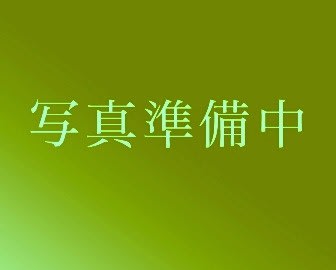
***** 丑年の展望 No.6 *****
昨日ご紹介した「グレートコンジャンクション」しかり、
来年の干支である「辛丑(かのとうし)」しかり、
それらの暗示の中には、迷信のひと言では
片づけられない、「今後の示唆」が
隠されていると個人的には考えております。
恐らく古代の人々も、遺跡や磐座を通して
下ろされる「天の言葉」に耳を傾けながら、
日々の生活を送っていたのでしょう。
しかしながら、いつの頃からか私たちは
「目に見えるもの」だけを崇拝し、
自然や天地とのつながりを断ってしまったのでした。
さらには、本来「公」のものだった占術の類を、
「お金儲けの道具」「個人の利益を得るためのツール」
として活用し始めたことから、世の中は
混乱の方向へと進んでしまったのかもしれません。
だとすれば、これから人類はいかにして
「見えるもの」と「見えざるもの」
とのバランスを取っていけば良いのか……。
それらのヒントが集約されているのが、
まさに「神道(古神道)」の世界観だと思うのです。
2021年という年は、多くの日本人が
日本の価値に気づく年になるのでしょう。















