
村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』
1982年秋、『羊をめぐる冒険』を書き上げ、小説家として手ごたえを感じた時、彼は走り始めた。以来、走ることと書くこと、それらは、村上春樹にあって分かつことのできない事項となっている。アテネでの初めてのフルマラソン、年中行事となったボストン・マラソン、サロマ湖100キロ・マラソン、トライアスロン……。走ることについて語りつつ、小説家としてのありよう、創作の秘密、そして「僕という人間について正直に」、初めて正面から綴った画期的書下ろし作品です。
仕事の合間にさらっと読めるかな、と思って選んだんですが、
案外しっかりした骨太な本でした、for me。
この人のこの手の、ベタに自分の日常や感情を語ったエッセイは、ちょっと珍しいかも。
や、小説そのものがすごく「僕」化してる作家だと思うのですが
ついつい1人称の小説のように読めてしまった。
あまりにもフィジカルだから、かえってフィクションっぽく感じたりする部分もあって、
なんだかそゆ自分と春樹氏との距離感みたいな・認識の形みたいなもの自体、興味深かったり。
で、なんというか、ちょっと読んでて、身につまされたり
ためいきついたり、自分の行く末と今を考えたりしちゃいました。
それぞれに持つ感想や、注目点は違うと思いますが、私的には
『年をとることについて語るときに僕の語ること』という感じの印象が色濃く残りました。
あと『人間関係について語るときに僕の語ること』かなー。
当たり前の話だが、誤解されたり非難されたりするのは、決して愉快な出来事ではない。そのせいで心が深く傷つくこともある。これはつらい経験だ。
しかし年齢をかさねるにつれて、そのようなつらさや傷は人生にとってある程度必要なことなのだと、少しづつ認識できるようになった。考えてみれば、他人といくらかなりとも異なっているからこそ、人は自分というものを立ち上げ、自立したものとして保っていくことができるのだ。(中略)心の受ける生傷は、そのような人間の自立性が世界に向かって支払わなくてはならない当然の代価である。(p36)
誰かに故のない(と少なくとも僕には思える)非難を受けたとき、あるいは当然受け入れてもらえると期待していた誰かに受け入れてもらえなかったようなとき、僕はいつもより少しだけ長い距離を走ることにしている。(中略)腹がたったらその分自分にあたればいい。悔しい思いをしたらそのぶん自分を磨けばいい。そう考えて生きてきた。~(p37~38)
うーん、なんかね、クールでドライで動じない人ではなく、その揺れを自分が吸収できるように自分を鍛える、それもフィジカルに、ってやっぱちょっと特別な感性のように思います。自制心がすごく効いてる感じ。(私の対極かも;
それにしても書くことと走ることの結びつきと自覚的な調整がすごい。
どういう脳の自己管理プロセスが企まれてるんでしょう!
ブチ当たるんじゃなく、受け流す(あ、先週の『働きマン』みたいw)、そのための受け皿を意識的に作っていく・・・うーん・・・。
こうして考えると、この作家は内容と方法論がすごく一致してるんだな。
自分の腑に落とすために腑のほうも変えていく作家なのだと再認識。
小説の書き方含め、「これが僕だ」をきちんと記録する方法で記録された村上本だと思います。
あ、加齢してく身体とうまくやってく具体的な指導本としてもいいと思います。
おまけ:なる@的ドッグイヤーポイント(全体で読まないと意味は変わると思いますが、あえて)
人生は基本的に不公平なものである。それは間違いないところだ。しかしたとえ不公平な場所にあっても、そこにある種の公平さを希求することは可能であると思う。(中略)そのような「公正さ」に、あえて希求するだけの価値があるかどうかを決めるのは、もちろん個人の裁量である。(p63)
そう、ある種のプロセスは何をもってしても変更を受け付けない。僕はそう思う。そしてそのプロセスとどうしても共存しなくてはならないとしたら、僕らにできるのは、執拗な反復によって自分を変更させ(あるいは歪ませ)、そのプロセスを自らの人格の一部として取り込んでいくことだけだ。
やれやれ。(p95〜96)
彼女たちに背後から抜かれていっても、べつに悔しいという気持ちはわいてこない。彼女たちには彼女たちに相応しいペースがあり、時間性がある。僕には僕に相応しいペースがあり、時間性がある。それらはまったく異なった成り立ちのものだし、異なっていて当たり前である。(p130)
真に不健康なものを扱うためには、人はできるだけ健康でなくてはならない。それが僕のテーゼである。つまり不健全な魂もまた、健全な肉体を必要としているわけだ。(p134)
意識なんてそんなにたいしたものではないのだ。(p136)
若死を免れた人間には、その特典として確実に老いていくというありがたい権利が与えられる。肉体の盛衰という栄誉が待っている。その事実を受容し、それに慣れなくてはならない。(中略)数字に表れないものを僕は愉しみ、評価していくことになるだろう。そしてこれまでとは少し違った成り立ちの誇りを模索していくことになるだろう。(p164~165)
40代以上で、もう若いとはいえないな、という自覚のある人が読むと、
道の先から聞える声に、すこしだけ戸惑い、
そのあと、少しだけ肩の力を抜けるかもしれません。











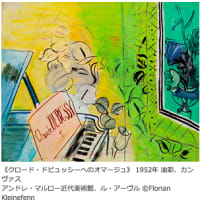
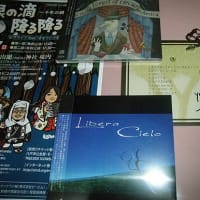












褒めているのでも、貶しているのでもなく。
本質的にドライな人は、ドライな言動なんかする必要はないし。
そのせいか、村上春樹にはなんとなく、共感してしまう。
もちろん、勝手な思い込みですけどね。
同時にやはり繊細なんでしょうね。
でも、こうして自分の弱みを吐露できるのは、強さでもあるなぁ、
と思ったり。
私は「彼はタフだな」と思うことが多いです。
そこがアスリートだからかも。
書くことでしか表現できない、それが自分だ、と言いきれる
そんな自分を育て・切磋琢磨し続ける姿勢は学ぶべきだと感じます。
彼の場合、こういうグダグダした感じが、また
文体の「魅力}(というか記号)となってるのが興味深いです。
ともあれ、今回の「老い」を語る内容は、小説以上にずしんと来ました。(;
まぁ、先輩がいるというのはいい意味でも悪い意味でも
影響があるということなのでしょう・・・。やれやれ。w