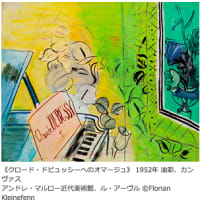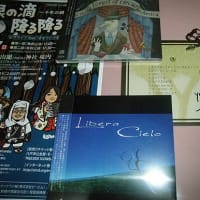フューチャリスト宣言 (ちくま新書) (新書)
梅田 望夫 (著), 茂木 健一郎 (著)
2007年5月初版ですが、今読んでもかなり面白いです。
『ウェブ進化論』の梅田さんと、茂木さんの対談集。
この2人、どこまでも突き抜けるようにポジティブで最強です!
情報のあり方、ネットビジネスのあり方、大学のあり方、個人のあり方、ネットが壊して(変えて)いく知的インフラについて、大胆に切り込んでいます。
身近な話題として「そういう見方・考え方もあるなー」と思ったブログ論を抜粋してみました。ブログとSNSの差違を見極めながら、ネットの中の社会と個人のありようを分析している部分です。
※ざくざく編集してますので、興味をもたれた方はぜひご一読を。グーグル論だけでも面白くって読む価値あると思います(内容的に古くはありますが、企業ポリシーとかは変ってないので)。
※ネットの使い方や目的は個人によって異なるのが当然ですし、人によってはブログをSNS代わりに使っている方や両者を使い分けてる方(私含む)もおられるでしょうから、あくまで主機能面でのブログとSNSとの差違ということで解釈しました。
==================================
第2章クオリアとグーグル
※●はNAL
●ネットで消費される個人
茂木/(略)自分にとって本当に大切なことを書く時には、おそらく僕も梅田さんも匿名の巨大掲示板に書くことってないと思うんですよ。どうして我々がそういう感覚を持っているかというと、どんなに力を混めて書いたとしても、それは確率論、ポートフォリオの一要素として消費されてしまうという感覚がある。たとえば北朝鮮問題や中国の問題について、どんな極端な議論をしても、それはネットの上の後半な言語分布のなかの一部分に位置づけられる。単なる1つのスレッド、エントリーにすぎない。
(中略)
茂木/書く側はいろいろな想いを託して書くわけでしょう。それこそ自分の全存在のウエイトをかけて。ところが読む側、コミュニティ側は単なる1つのエントリーとして消費してしまう。なのにそれが自己実現だと思ってしまう人がいると思うんですよ。
梅田/僕の感じは少し違って、仮に消費されるにしても誰かの心に残る。結果として何が起きるかというと、ある種の社会貢献。社会への関与ですよね。
(中略)
梅田/映画「マトリックス」の電池みたいになっていくということでしょう。システムがみんなとつながっていて、みんな違う夢を見ている。だけど生体はシステムの維持のためにある。
茂木/SNSなんてまさにそうで(中略)そして友達ができればいいなぁ、出会いがあればいいなぁと思ってやっているのだけれど、運営側からすると「シメシメ」と思っているわけでしょう。そうやってデジタルの1ビットに回収されていく。(084-086)
●ブログの意味とポテンシャル
茂木/インターネットをグーテンベルクの活版印刷技術の延長だととらえる人が多いようですが、むしろ、個人のキャラクターを際立たせる場というか、自分とは何であるかということを説明するインフラが社会的にできたということの意味が大きい気がする(088)
茂木/「偶有性」という話を先にしましたが、インターネットのポテンシャルの最高の部分はオープンなところ。そういう意味でSNSにはやはりあまり共感できないなぁ。
梅田/SNSはウェブ1.0だということは、僕も言っているんですよ。ウェブ1.0と2.0の違いに関する僕の感性っていくつかあるんだけど、コンテンツが検索エンジンに引っかかるかどうかが大きいと思うんですよね。それが未知との遭遇になるので。匿名であれペンネームでもいい、ブログであれば匿名といってもアイデンティティがあるから。検索エンジンを通して未知との出会いがあるのか、それともないのかというところに、SNSとブログの決定的な違いがあると思う。(090)
●感情の技術
茂木/ブログには、厄介なコメントやメールもたくさん来ます。それを良しとして引き受けるべきという考えが、僕の中では倫理観としてある。少なくとも、文化活動をしようという人には、不特定多数の「声」にさらされるという荒々しい体験が、ネット時代の通過儀礼だと思うんですよ。
(中略)
梅田/ネット時代のリテラシーというのは感情の技術ですよね。
茂木/オープンになるということはいいものと同時にイヤなものも運んでくる。ときどき無菌状態にしたい衝動に駆られるんです。たとえば、ブログのコメント欄やトラックバックは最初から受け付けないようにしようとか、掲示板は閉じちゃおうとか。でもね、そのたびに「待てよ。ネットというのはオープンだからこそ価値がある。踏みとどまらないとしようがない」と踏みとどまる。一方でときにはすごくいい出会いもあるので救われる。
梅田/いい出会いのほうが圧倒的に多いんだけど、一個のイヤなことが吹き飛ばすようなときがあるんですよね。
(中略)
茂木/自分の感性をどうコントロールするかということ。先ほど述べたように、ネット上では、自分に向けられたプラスとマイナスの声のパターンが自分のキャラクターを織り成すという認識は、僕にとって1つの大きな発見であり、救いだったんですよ。そう思うと気が楽だなぁと。僕をサポートしてくれる人もいるし酷評する人もいるけれども、そのパターンによって、ある像が結び始める。あっ、こういうグループの人たちは僕の言ったことに反発することが多いなぁ、とか。
梅田/村上春樹が同じようなことを言っていて「一つひとつの意見がもし見当違いなもので、僕が反論したくなるようなものだったとしても、それはしょうがないんですよね。僕は正しい理解というのは誤解の総体だと思っています。誤解がたくさん集まれば、本当に正しい理解がそこに立ち上がるんですよ」(柴田元幸著「翻訳教室」新書館)つまり読者の感想の、誤解も含めた総体が、評価であり理解なんだということを言っています。
●ブログという倫理観
茂木/結局、ネット上のやり取りって、どんなコメントでも、返事をしてもそこでリアルなコミュニケーションはまず生まれないんですよ。(中略)みんな経験を積むといいと思うんだけどなぁ。ブログってそれぞれの人の倫理観が試されるような気がしますよね。(略)僕の倫理観としては、基本的にポジティブな気持ちを広げるような感じにしたい。イヤなことは書かない
(中略)
梅田/結局教育って、ポジティブなものを与えるということ以外に何の意味もない(中略)
茂木/(夏目漱石が)東京帝国大学の教授職を断って朝日新聞に入った理由は、そのほうが多くの人に読んでもらえるから。いまだったら絶対ブログで連載してると思うんですよ。(092-094)
=============================
今、mixi以外のSNSに参加しはじめて2週間目なのですが、日記のコメント欄、伝言板、メールというコミュニケーション手段があり、人によっては日記のコメントへのレスとかも含めて、メールだけでコンタクトしてくる方がいます。
私のように、ブログでのオープンコミュニケーションが当然だと思っていると、かなり面食らうんですが、確かに自己防衛的にはそれも「あり」なのかもしれない。
・・・と思いつつ、閉鎖的なのはやはり苦手(メールで、内容も個人的というのが特に)なので、レスしないでいたら、やはりちょっとクレームじみたものが来ちゃっいまして・・・。「うーん、多分経験や価値観が違うんだろうな、どう説明したらわかってもらえるかな?」とか考えてたんですが、この文章を読んでもらうのがもしかしたら早道かも?
私もネット&ブログの素晴らしさは、自分の知らないモノ・コト・人との出会いだと思っているので、茂木さんや梅田さんほど確固たる自信や気概はないけど、同じベクトルの端っこを歩いていたいなぁ、と思います。
ここで出会い、コメントをくださる方々は、リアルではまったく面識なくスタートして(もろもろのしがらみや利害関係から開放されて)、ある趣味や話題が偶然に紡いで・つないでくれたご縁なわけですが、だからこそ、あらかじめ決められた枠内での交流(それにも別のメリットもありますが)以上に、素晴らしい方々に出会えている、と今更に実感しています。私にはもったいないご縁でもあります。そういう意味で「111」は私のホームベースであり、ネットライフで一番やりたいことは全てここに詰まっていると思っています。
ご参加に感謝いたします。
※大学に代表される、限られた情報(リソース)の囲い込み型(特権)ビジネスの限界(と終焉)についてはまた別途まとめたいと思っています。いまやネットのほうがリソース的には大学より上という発想は頭では理解できますが、そこには物理的関わりという形での「場」「人」「教え方」の重要性もあると思う。いずれにしてもこのお2人がネット大学をやるなら参加したいなぁ、とは思いますが・・・。(・・・まずは英語で辞書なしレベルで論文読めるようにならないと;;;<遠いなぁ;;
梅田 望夫 (著), 茂木 健一郎 (著)
2007年5月初版ですが、今読んでもかなり面白いです。
『ウェブ進化論』の梅田さんと、茂木さんの対談集。
この2人、どこまでも突き抜けるようにポジティブで最強です!
情報のあり方、ネットビジネスのあり方、大学のあり方、個人のあり方、ネットが壊して(変えて)いく知的インフラについて、大胆に切り込んでいます。
身近な話題として「そういう見方・考え方もあるなー」と思ったブログ論を抜粋してみました。ブログとSNSの差違を見極めながら、ネットの中の社会と個人のありようを分析している部分です。
※ざくざく編集してますので、興味をもたれた方はぜひご一読を。グーグル論だけでも面白くって読む価値あると思います(内容的に古くはありますが、企業ポリシーとかは変ってないので)。
※ネットの使い方や目的は個人によって異なるのが当然ですし、人によってはブログをSNS代わりに使っている方や両者を使い分けてる方(私含む)もおられるでしょうから、あくまで主機能面でのブログとSNSとの差違ということで解釈しました。
==================================
第2章クオリアとグーグル
※●はNAL
●ネットで消費される個人
茂木/(略)自分にとって本当に大切なことを書く時には、おそらく僕も梅田さんも匿名の巨大掲示板に書くことってないと思うんですよ。どうして我々がそういう感覚を持っているかというと、どんなに力を混めて書いたとしても、それは確率論、ポートフォリオの一要素として消費されてしまうという感覚がある。たとえば北朝鮮問題や中国の問題について、どんな極端な議論をしても、それはネットの上の後半な言語分布のなかの一部分に位置づけられる。単なる1つのスレッド、エントリーにすぎない。
(中略)
茂木/書く側はいろいろな想いを託して書くわけでしょう。それこそ自分の全存在のウエイトをかけて。ところが読む側、コミュニティ側は単なる1つのエントリーとして消費してしまう。なのにそれが自己実現だと思ってしまう人がいると思うんですよ。
梅田/僕の感じは少し違って、仮に消費されるにしても誰かの心に残る。結果として何が起きるかというと、ある種の社会貢献。社会への関与ですよね。
(中略)
梅田/映画「マトリックス」の電池みたいになっていくということでしょう。システムがみんなとつながっていて、みんな違う夢を見ている。だけど生体はシステムの維持のためにある。
茂木/SNSなんてまさにそうで(中略)そして友達ができればいいなぁ、出会いがあればいいなぁと思ってやっているのだけれど、運営側からすると「シメシメ」と思っているわけでしょう。そうやってデジタルの1ビットに回収されていく。(084-086)
●ブログの意味とポテンシャル
茂木/インターネットをグーテンベルクの活版印刷技術の延長だととらえる人が多いようですが、むしろ、個人のキャラクターを際立たせる場というか、自分とは何であるかということを説明するインフラが社会的にできたということの意味が大きい気がする(088)
茂木/「偶有性」という話を先にしましたが、インターネットのポテンシャルの最高の部分はオープンなところ。そういう意味でSNSにはやはりあまり共感できないなぁ。
梅田/SNSはウェブ1.0だということは、僕も言っているんですよ。ウェブ1.0と2.0の違いに関する僕の感性っていくつかあるんだけど、コンテンツが検索エンジンに引っかかるかどうかが大きいと思うんですよね。それが未知との遭遇になるので。匿名であれペンネームでもいい、ブログであれば匿名といってもアイデンティティがあるから。検索エンジンを通して未知との出会いがあるのか、それともないのかというところに、SNSとブログの決定的な違いがあると思う。(090)
●感情の技術
茂木/ブログには、厄介なコメントやメールもたくさん来ます。それを良しとして引き受けるべきという考えが、僕の中では倫理観としてある。少なくとも、文化活動をしようという人には、不特定多数の「声」にさらされるという荒々しい体験が、ネット時代の通過儀礼だと思うんですよ。
(中略)
梅田/ネット時代のリテラシーというのは感情の技術ですよね。
茂木/オープンになるということはいいものと同時にイヤなものも運んでくる。ときどき無菌状態にしたい衝動に駆られるんです。たとえば、ブログのコメント欄やトラックバックは最初から受け付けないようにしようとか、掲示板は閉じちゃおうとか。でもね、そのたびに「待てよ。ネットというのはオープンだからこそ価値がある。踏みとどまらないとしようがない」と踏みとどまる。一方でときにはすごくいい出会いもあるので救われる。
梅田/いい出会いのほうが圧倒的に多いんだけど、一個のイヤなことが吹き飛ばすようなときがあるんですよね。
(中略)
茂木/自分の感性をどうコントロールするかということ。先ほど述べたように、ネット上では、自分に向けられたプラスとマイナスの声のパターンが自分のキャラクターを織り成すという認識は、僕にとって1つの大きな発見であり、救いだったんですよ。そう思うと気が楽だなぁと。僕をサポートしてくれる人もいるし酷評する人もいるけれども、そのパターンによって、ある像が結び始める。あっ、こういうグループの人たちは僕の言ったことに反発することが多いなぁ、とか。
梅田/村上春樹が同じようなことを言っていて「一つひとつの意見がもし見当違いなもので、僕が反論したくなるようなものだったとしても、それはしょうがないんですよね。僕は正しい理解というのは誤解の総体だと思っています。誤解がたくさん集まれば、本当に正しい理解がそこに立ち上がるんですよ」(柴田元幸著「翻訳教室」新書館)つまり読者の感想の、誤解も含めた総体が、評価であり理解なんだということを言っています。
●ブログという倫理観
茂木/結局、ネット上のやり取りって、どんなコメントでも、返事をしてもそこでリアルなコミュニケーションはまず生まれないんですよ。(中略)みんな経験を積むといいと思うんだけどなぁ。ブログってそれぞれの人の倫理観が試されるような気がしますよね。(略)僕の倫理観としては、基本的にポジティブな気持ちを広げるような感じにしたい。イヤなことは書かない
(中略)
梅田/結局教育って、ポジティブなものを与えるということ以外に何の意味もない(中略)
茂木/(夏目漱石が)東京帝国大学の教授職を断って朝日新聞に入った理由は、そのほうが多くの人に読んでもらえるから。いまだったら絶対ブログで連載してると思うんですよ。(092-094)
=============================
今、mixi以外のSNSに参加しはじめて2週間目なのですが、日記のコメント欄、伝言板、メールというコミュニケーション手段があり、人によっては日記のコメントへのレスとかも含めて、メールだけでコンタクトしてくる方がいます。
私のように、ブログでのオープンコミュニケーションが当然だと思っていると、かなり面食らうんですが、確かに自己防衛的にはそれも「あり」なのかもしれない。
・・・と思いつつ、閉鎖的なのはやはり苦手(メールで、内容も個人的というのが特に)なので、レスしないでいたら、やはりちょっとクレームじみたものが来ちゃっいまして・・・。「うーん、多分経験や価値観が違うんだろうな、どう説明したらわかってもらえるかな?」とか考えてたんですが、この文章を読んでもらうのがもしかしたら早道かも?
私もネット&ブログの素晴らしさは、自分の知らないモノ・コト・人との出会いだと思っているので、茂木さんや梅田さんほど確固たる自信や気概はないけど、同じベクトルの端っこを歩いていたいなぁ、と思います。
ここで出会い、コメントをくださる方々は、リアルではまったく面識なくスタートして(もろもろのしがらみや利害関係から開放されて)、ある趣味や話題が偶然に紡いで・つないでくれたご縁なわけですが、だからこそ、あらかじめ決められた枠内での交流(それにも別のメリットもありますが)以上に、素晴らしい方々に出会えている、と今更に実感しています。私にはもったいないご縁でもあります。そういう意味で「111」は私のホームベースであり、ネットライフで一番やりたいことは全てここに詰まっていると思っています。
ご参加に感謝いたします。
※大学に代表される、限られた情報(リソース)の囲い込み型(特権)ビジネスの限界(と終焉)についてはまた別途まとめたいと思っています。いまやネットのほうがリソース的には大学より上という発想は頭では理解できますが、そこには物理的関わりという形での「場」「人」「教え方」の重要性もあると思う。いずれにしてもこのお2人がネット大学をやるなら参加したいなぁ、とは思いますが・・・。(・・・まずは英語で辞書なしレベルで論文読めるようにならないと;;;<遠いなぁ;;