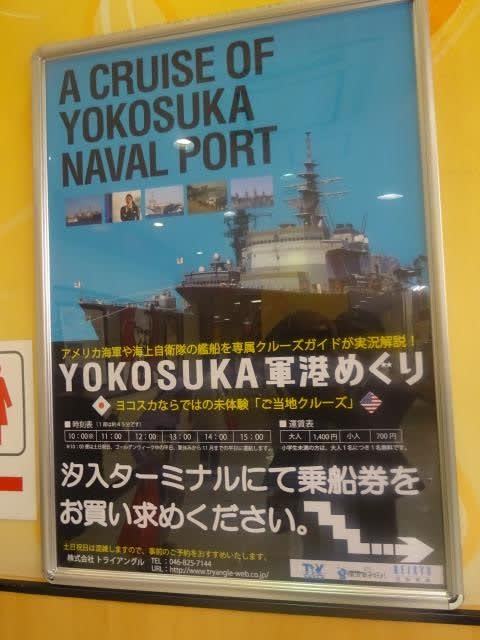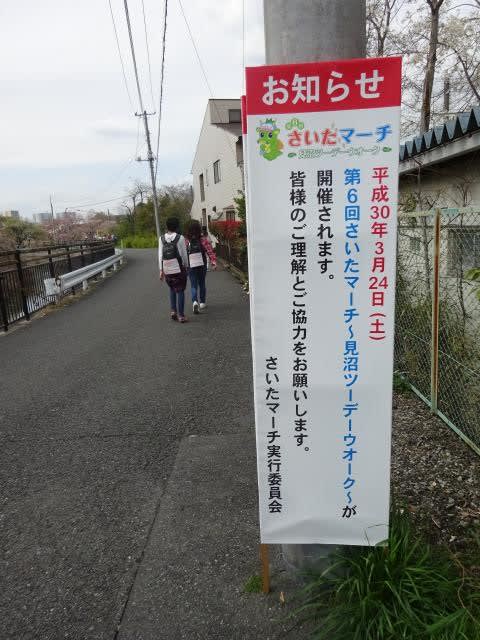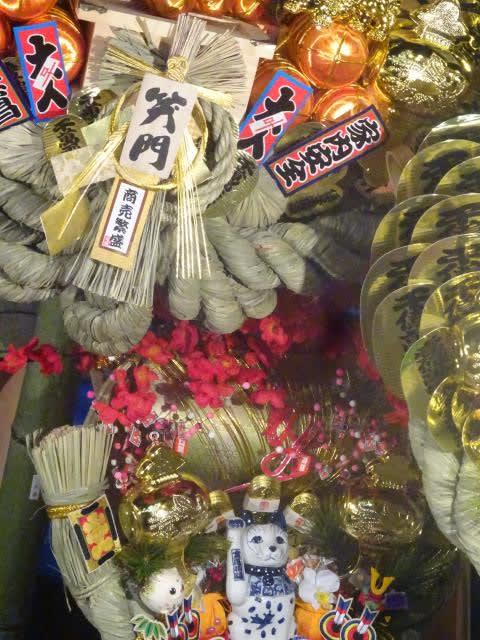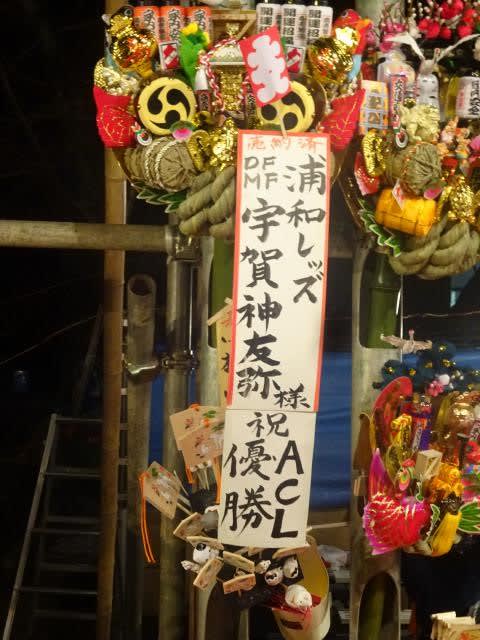7月6日(金)から9月24日(月)までコレド室町1の日本橋三井ホールで
開かれたアートアクアリウムのチケットを頂いたので行って来た。
このイベントは江戸・金魚の涼~&ナイトアクアリウム
「史上最大の作品が織り成す史上最高のアートアトリウム
その衝撃を目撃せよ・・・」というタイトルで実施。
ナイトアトリウムということで夜の部はTOP DJや
伝統芸能で真の日本を体感できる企画が盛り沢山あった。

ここは会場の入口、このイベントは今夏、日本橋以外にも
名古屋そして中国上海でも初披露されている。
今回の展覧会は大変な評判になり、累計有料入場者数は
925万人(9月25日現在)を動員したという。ここ日本橋会場でも
地下の地下鉄改札付近では長蛇のウェイティング列を
帰りに目撃し、あまりの多さにビックリした。

入口を入るといきなり、ご覧の様な衝撃的な光景に遭遇。
これは江戸時代の豪商が、ガラスの水槽を天井に造り、
金魚を見上げて鑑賞していたという伝説を現代に蘇らせた
2018年の新作「天井金魚」だ。構想期間は5年にもおよび
鏡面効果により、さまざまな角度から金魚の美しさを
見ることができる新感覚の作品だ。



新潟県長岡市山古志から取り寄せた最高級品種の錦鯉が
円筒形の水盤の中を優雅に静かに泳ぐ。全体が水で覆われた
直径1.5Mの円筒形の作品は、錦鯉と周りの水をまるごと切り出し、
まるで錦鯉が宙を浮いているかのような不思議な見え方が
楽しめる。新作「フローティングリウム」。



地球をイメージした直径1.5Mの球体の水槽の中を錦鯉が
乱舞いする作品「アートアクアリウム・ジャポニズム」
水が溢れ流れる巨大な球体水槽はアートアクアリウム史上最大の
質量と作品自体が回転するという想定外の仕掛けを施し、
観る者を圧倒する。そしてどこの作品もそうであったが、
ライティングで作品の色がどんどん変化していく。



2016年アートアクアリウム誕生10年の集大成として誕生した
新たなる超大作「超・花魁」。アートアクアリウムの処女作でありながら
10年にわたり主役の座に存在し続け、600万人に感動を
与えたあの名作「花魁」が想像を超えた規模になり
逆に生まれ変わった。その姿は生まれる前から伝説になることを
約束された神の領域の美しさと、驚愕の大きさを兼ね備えた
まさしく世界最大の金魚鉢であり、作品名の前に超を与えられた特別な作品だ。
この新超大作は3000匹の金魚が舞泳ぎ
今迄の1000匹を大きく凌駕した七色に光輝くライティングと
神々しさを際立たせる映像効果により、まさに最高峰の
花魁となり、見るものを圧倒する作品だ。



会場全体の光景。各作品はライティングで色が変わり、
会場壁にもクラブ的な照明をしていた。今回のイベントコンセプトは
「夏の日本」だそうだ。そしてテーマは「江戸・金魚の涼」
江戸時代に日本橋で金魚が庶民文化として根付き、
金魚を鑑賞して夏の涼をとっていた文化を現代に蘇らせている。
そして日本の美のひとつともいえる金魚や錦鯉を中心とした
合計約8000匹の鑑賞金が日本的な作品の中を優雅に舞い泳いでいる。


鏡面効果を持つ三角柱のアクアリウムを積み上げた
見る角度によってい金魚の数が変化する不思議な作品
「アクアゲート」。1対の作品で会場の両側に展示することで
ゲートとしての役割を果たしている。




江戸時代から伝わる伝統工芸である江戸切子を用いた作品
「キリコリウム」。江戸切子の特徴であるカットガラス工法の良さを生かし、
上から見ても横から見ても、金魚たちが不思議で美しく見える。
作品下部は現代の工芸でもあるアクリルで江戸切子を模して
製作しており、日本が誇る新旧の工芸技術の共演による
品のある美しさを感じる作品だ。それにしても江戸切子の
器の中を泳ぐ奇妙奇天烈な金魚。多分出目金の仲間だろうが、
今にも目の玉が落ちそうだ。こんな金魚は初めて拝見した。


透明な多面体でプリズム効果をもたらすアクアリウム
「プリズリウムF12、F18」は18面体と12面体の2種類が展示
されている。光のマジックにより、中に泳ぐ魚の群れが
大きく見えたり、小さく見えたり、時には歪んで見える等、
ユニークな見方が楽しめる。

日本に古くからある道具の1つである「手毬」をモチーフとした
球体の作品、毛毬の特徴である色とりどりの可愛らしい
模様を伝統工芸である伊賀組紐と中を泳ぐ生きた金魚で表現している。
伝統工芸とアクアリウムが完全に融合した名作だ。





新作の「大政奉還金魚大屏風」
大政奉還は日本の歴史においてさまざまな影響を与え、
芸術の世界も大きな転換期を迎えた。この作品では
日本美術史の移り変わりを表現したプロジェクトマッピングによる
動く屏風絵を屏風型のアクアリウムを投射し、
その中を金魚が優雅に泳ぐ。映像は、大政奉還の時期とその
前後の時代というように、3つの時代のテーマで創り、
大政奉還がもたらした日本の芸術への影響へが
理解できる幅約5.4Mにもおよぶ18連(ビョウプリウム)の大型作品だ。



生きた金魚の動きと映像の融合による、掛軸のアートアクアリウム
「床掛け金魚飾り」手前に展示された月山作の日本刀(翔英美天命)に合せた
映像を新たに制作。飾り立てられたシルバーアートはイタリア最古の
宝飾ブランド「Cuusi」とのコラボレーション。

よく見ると壁には江戸切子のグラスを利用した照明器具が。
遠くから見るとこの照明器具は変わっていて何だろうと思ったが
そういうことであった。これはグッドアイディアだと思う。

金魚は人の手で生み出されたアート。その生きるアートをコレクションとして
沢山の作品の品種を1作品づつ鑑賞してもらう金魚コレクションの1つ。
普段中々目にすることの無い珍しい品種を展示。
金魚を妖艶に映し出す演出が楽しめる。

今回金魚鯉を中心に約100枚の写真を撮った中で
一番良く撮れたと思う金魚写真でこのブログをクローズします。
このイベントで江戸時代の花街に彷徨いこんだような非日常的な
涼しい世界を充分楽しむことができました。