ハミッド・ダバシ『ポスト・オリエンタリズム テロの時代における知と権力』(作品社、原著2009年)を読む。
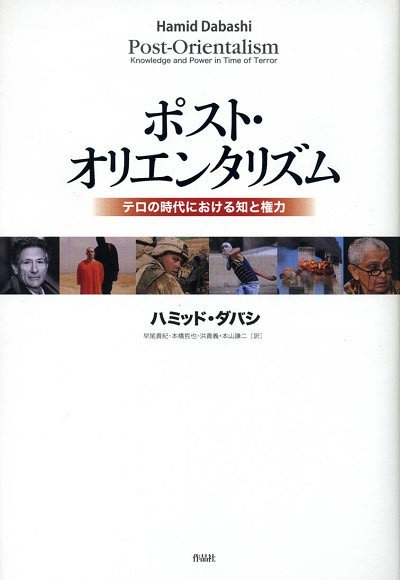
著者のハミッド・ダバシはイラン出身の中東研究者であり、しばしば故エドワード・サイードにも比される。本書もサイードの『オリエンタリズム』(1978年)を意識し、また直接引用・批評するものである。従って、ポストコロニアル批評の発展形でもあると言うことができる。
サイード『オリエンタリズム』は、アジアや中東(もともとはギリシャ・ローマから視た「東」)について、ヨーロッパが、自分の視点でのみ一方的でコミュニケーションになど基づかない言説をいかに作り上げていったかを実証的にまとめ上げたものだった。本書の前半では、ゴルトツィーエル・イグナーツという19-20世紀のイスラーム・東洋学者の活動について、その観点から検証している(馴染みのない議論でありここで挫折する人も少なくないだろう)。それによれば、サイードが想定した東方への視線を、必ずしもゴルトツィーエルが持っていたわけではなかった。『オリエンタリズム』の描く大きなストーリーからはみ出してしまうものはあるということだ。
しかし、そのことは同書が画期的な成果だったことに傷をつけるものではない。ダバシは、同書はミシェル・フーコーが発展させた理論に影響された面が大きいと説く(たとえば非合理なものを線の向こう側に追いやる歴史的な経緯を説いた、1961年の『狂気の歴史』)。まさにフーコーの理論をリアルの社会と歴史に適用したことがサイードの功績であったというわけである。その分、サイードは抽象的な思想を開拓したわけではなかったとする。本人は同書を理論ではなく遊撃(パルチザン)だと表明している。
一方で、ガヤトリ・C・スピヴァクが引き合いに出される。サイードとは対照的に、ジェンダーの違い、サバルタン性、非ヨーロッパ(インド)という立ち位置からの批評は明瞭ではなく、わかりにくく、大きな批判の対象にもなった(実際に彼女のポストコロニアル批評のテキストはわかりにくいと思う)。だが、そのことを踏まえた上で、ダバシはスピヴァクの言説もサイードと同様に高く評価する。おそらくそれは、異なる立ち位置からの言説の模索ゆえのことである。私たちは何もサイードとスピヴァクのどちらかを選ばなければならないわけではない。
というのも、本書後半になって、越境を伴う者たち(モフセン・マフマルバフ、マルコムX、チェ・ゲバラ、フランツ・ファノンら)の視線こそを非常に称揚するからだ。
「理論家でかつ実践家でもあるこれらの革命家は巡礼者のようだ。つねに移動することを定めとし、さらにまた次の現場を訪れる。こうしてまさに訪れたどこか他の場所の遠いこだまを聞き取って語り、また見覚えあるあらゆる場所に堆積している知恵を読み取って語るのである。彼らはつねに自らの声の中にある異郷の波紋とともに語った。そして来るべき場所についての確信の輝きとともに行動した。たいへんな説得力でものを見て触発することができたのだが、それは自分たちがいたのとは別の異なる場所がどこかにあるという、響き渡る確信の声で語ったからである。昨日の世界からやってきたが、明日の言語で語った。(略)神の介入によってではなく、駆け抜ける馬の蹄、旅するブーツのかかとが巻き上げるつむじ風によって幻視したのである。」
それと対照的なものは、サイードが可視化したようなヨーロッパ内で相手(東方)を内部化する言説、あるいは、アメリカのエスタブリッシュメント・ネオコンと深く関係したイデオローグ的な言説(ノーム・チョムスキーが何度も指摘しているように)。ダバシの表現によれば、この「内方浸透」による知のあり方は「ヘゲモニーなき帝国に奉仕して何も意味しない知」と手厳しい。一見相手を公平・客観的に位置づけ扱うようであっても、それは固定化され歪んだ構造に基づくものに過ぎないということである。なぜ誰もがヨーロッパ的な思想空間・言説空間を介して表象せねばならないのか、ヨーロッパ的な者を対話者として選ばねばならぬのか、語る主体は誰なのかというわけだ。
「彼らの恐れと震えに向き合うこと。彼らが「自分たちの古典」と呼ぶものの死せる読解における、生命のない確実性に頼ろうとする「西洋文明」の守護者としての「西洋」を、脱物語化する潮流に身を投じること。ポスト土着主義(ポストコロニアル)の知識人の基本的な仕事は、こうしたテクストが実際に自分たちに属しているという満足を、ありもしない「西洋」の文化的戦士たちに与えないことだ。これらのテクストは、彼らのものではない。これらのテクストが亡命(エグザイル)しているとき、私たちは故郷(ホーム)に居るのである。」
●ミシェル・フーコー
ミシェル・フーコー『性の歴史Ⅰ 知への意志』(1979年)
ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(1975年)
ミシェル・フーコー『ピエール・リヴィエール』(1973年)
ミシェル・フーコー『言説の領界』(1971年)
ミシェル・フーコー『わたしは花火師です』(1970年代)
ミシェル・フーコー『知の考古学』(1969年)
ミシェル・フーコー『狂気の歴史』(1961年)
ミシェル・フーコー『コレクション4 権力・監禁』
重田園江『ミシェル・フーコー』
桜井哲夫『フーコー 知と権力』
ジル・ドゥルーズ『フーコー』
ルネ・アリオ『私、ピエール・リヴィエールは母と妹と弟を殺害した』
二コラ・フィリベール『かつて、ノルマンディーで』
●ガヤトリ・C・スピヴァク
ガヤトリ・C・スピヴァク『ナショナリズムと想像力』(2010年)
ガヤトリ・C・スピヴァク『デリダ論』(1974年)




















