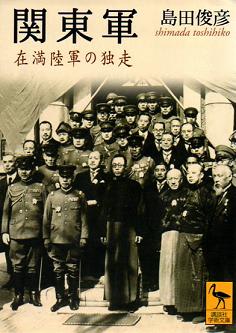NHK『プロジェクトX』で放送された、黒部ダムの特集を2巻借りてきた。「厳冬 黒四ダムに挑む ~断崖絶壁の輸送作戦~」(2000年)と、2週連続での「シリーズ黒四ダム 第1部・秘境へのトンネル 地底の戦士たち」「同 第2部・絶壁に立つ巨大ダム 1千万人の激闘」(2005年)であり、続けて見ると、関電本社の移転を挟んでいる(笑)。「黒四ダム」とも称するのは、ここからの水による地下の発電所が「黒部川第四発電所」だからである。大きな弧を描く「アーチ式コンクリートダム」であり、水圧を両岸の岩盤で支える。そのため峡谷に限られる。

人がほとんど立ち入ることができない秘境・黒部に資材を運ぶため、1年以上かけてトンネルを掘り、また山の上からブルドーザーをソリで降ろす。トンネル掘りは地盤が危ないが、通常を遥かに上回るペースで進める。これが、石原裕次郎主演の『黒部の太陽』の舞台であるらしいが、大スクリーンでしか見せないという方針であったため、観る機会はない。佐久間ダム建設において川の迂回路となるトンネルを掘った者がここでも携わったようで、番組では、記録映画『佐久間ダム』の一部分が使われていた。
また、地下の発電所を掘削するとき、高熱の岩盤であったため、掘削現場は100℃前後となった。そのため、後ろから裸の掘削者に放水するという方法がとられた。なお、この前に建設された「黒部川第三発電所」でも高熱岩盤に苦しめられたようであり、吉村昭『高熱隧道』でその建設の様子が小説化されている(私は読んでいない)。
コンクリートを流しいれる方法にも驚かされる。崖の上のクレーンで、コンクリートを入れた籠を操作し、崖下に落とす。このときにあまりにも揺れて場所が定まらなかったが、ひとりの名人の手によって解決している。それをブルドーザーで均し、クレーンとの時間の競争となった。
どの工程もいちいち信じ難く、驚嘆する。もはやこのような土木工事は不可能に違いない。7年間の工事で、雪崩や落石などによって171人が亡くなっている。越冬の厳しさや恐怖で精神が参ってしまった者もいる。当時を回顧する方々は皆、勇気がなければだめだった、おそれたら終わりだった、と口をそろえる。そして、亡くなった方々を弔う記念碑に手を合わせる。
観ながら痛感した。これは戦争に出征した兵士たちなのだ、と。番組のつくりは戦争ドラマと変わるところはない。必要な電気のためだったが、多数の死者を生むことが最初からわかっていた戦争だった。そして他の選択肢があったかもしれないことについては、当時も今も触れられない。もちろん侵略戦争とは根本的に異なる。途轍もない事業である。だが、このような形で美談にすることには大きな違和感がある。
『黒部の太陽』は、巨大ダム造りを進めるプロパガンダとして、各河川の漁協説得に使用された歴史を持つ。そして、不思議なことに毎年建設省(当時)が資金を提供する各地のダム自治体の「湖水(ダム)祭」などは、石原プロの企画が多かったという(天野礼子『ダムと日本』)。『プロジェクトX』にも同じプロパガンダに利用されるにおいが漂っているような気がするのだ。