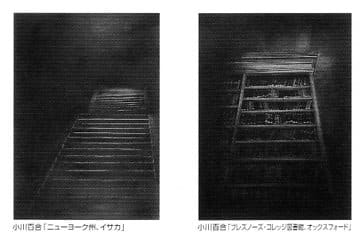井上光晴『明日 ― 一九四五年八月八日・長崎 ―』(集英社文庫、1982年)は、長崎における原爆投下の前日を描いた作品である。「あとがき」によると、ここに登場する人物にはそれなりのモデルがいるということだが、「嘘つきみっちゃん」の言であるから実際にそうなのかはわからない。
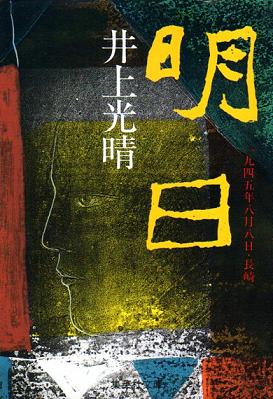
その日。あるふたりは結婚式を挙げ、同じ日、新婦の姉は赤ん坊を産む。そして、結婚式に集まった親戚や友人たちそれぞれの日常が、入れ替わり立ち代り浮上する。語り手は唐突に交代し、視線も感情も交錯する。最初はよくつかめないながら、次第に複層的な世界に引き込まれていく、井上光晴の語り・騙りである。
じっとりと暑い日、戦争の窮乏期にあって、いくつもの卑屈さや差別がある。これを目に見えるパフォーマンスで表現することは難しいだろうと感じる。
井上光晴の想像力は、出産時の苦しみの独白で極みに達する。こればかりは、体験できない自分には共感しようにもできないのだが。
「こんなことはもうたくさんだ。私にはできない。どうにかなってしまったのだ。何かよくないことが起こりかけている。私は多分このまま死ぬ。ねじれた川。私の前で黄金色の水がうねり忽ち渦となる。あれは何。粒状のものをいっぱいつけた透明な紐は。暗緑色に輝く無数の粒はぷちぷち音を立ててつぶれ、そこからまた新しい粒が生まれる。蛇よ、蛇の卵よ、と誰かがいっている。燃やすとよ、早う。火で焼いてしまわんと大ごとになるけんね。」
翌朝までかけて無事赤ん坊を出産し、新しい一日がはじまる。この日のカタストロフを待たずに作品は終わる。
おそらく誰もが想像してしまう「その日」は、ヒロシマナガサキの後でも、私たちにとって永遠に「明日」なのだ。明日になればまたその明日。いつ訪れるかわからない、その「明日」。
仙台行きの新幹線で読み、日帰りしてから、黒木和雄『TOMORROW 明日』(1988年)を観た。原作のエッセンスはうまく活かされてはいる。ただ、決定的な欠陥がある。
狭い袋小路にあって、人びとの差別的な感情、鬱屈した感情が描かれていない。示されているのは、朝鮮人や捕虜となった米国人への差別的な行為であり、あくまで目に見えるパフォーマンスである。それだけでなく、明瞭に発声する劇では駄目だろうと思う。
それに輪をかけて、桃井かおり、佐野史郎という、顔に「演劇」と書いてある役者のパフォーマンスであっては、日常からかけ離れた世界にしかなっていない。井上光晴による、出産時の想像力の飛翔に比べ、大汗をかいて苦しむ桃井かおりの姿はどうしようもなく格落ちだ。
●参照
○井上光晴『他国の死』
○原爆と戦争展
○原爆詩集 八月
○青木亮『二重被爆』、東松照明『長崎曼荼羅』
○『はだしのゲン』を見比べる
○『ヒロシマナガサキ』 タカを括らないために