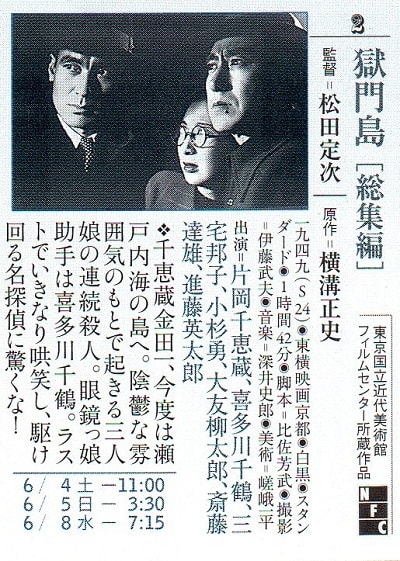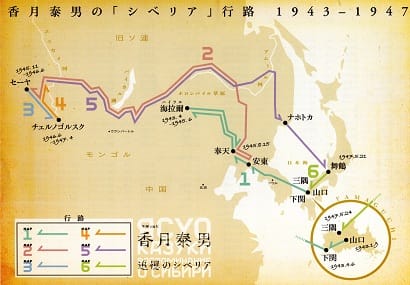(つづき)
■ 笹口孝明さん(新潟県旧巻町・元町長)
新潟県巻町(現・新潟市)には、かつて巻町原発の建設が計画されていた。1995年の住民自主管理による住民投票、推進派町長のリコール・辞任と住民投票を実施した会からの新市長(笹口市長)の誕生、1996年の町による住民投票、町有地の反対派への売却と最高裁での勝利、東北電力による原発断念と、まさに住民主導の合意形成プロセスを実現させた例である。
共通の記憶とされるべき歴史であり、私も『これでいいのか福島原発事故報道 マスコミ報道で欠落している重大問題を明示する』(丸山重威 編・著、あけび書房、2011)(>> リンク)において大事な事例として取りあげた。(なお詳細には、伊藤守・渡辺登・松井克浩・杉原名穂子著『デモクラシー・リフレクション:巻町住民投票の社会学』(リベルタ出版、2005)にまとめられている。)
その笹口町長である。いまは元の「造り酒屋のオヤジ」に戻っているのだという。直接話を聴けることは嬉しい限りだ。笹口氏はこのプロセスを振り返り次のように述べた。
1965年頃には、東北電力が土地ブローカーを使い、観光名目で角海浜(かくみはま)の土地買収を始めていた。それをスクープしたのは1969年の「新潟日報」であった。その後、概して町長は2期目になると原発推進に転じ、そのたびに原発に慎重な新町長が選ばれることが続いていた。しかし1994年、笹口町長前任の佐藤町長が「世界一の原発をつくる義務がある」との公約を掲げて三選を果たし、急に話が現実味を帯びてきた。このとき出てきた問題点は、「本当に町民は原発建設に同意しているのか?」ということだった。当選したとはいえ、原発に反対する候補の票のほうが佐藤町長の票を上回っていたのだ。
笹口氏を含め、地元の商工業社長と弁護士の計7人は「住民投票を実行する会」を結成、本気であることを示すために、プレハブの事務所をつくり、常駐職員を置き、マスコミへの発表と住民説明を行った。佐藤町長に原発の是非に関する住民投票への立会人派遣を要請するも拒否され、住民自主管理での投票となった。推進派は投票実施すると負けるために投票自体のボイコットを呼び掛けた。すなわち、「住民投票に行くこと」が「反原発」と見なされる雰囲気となり、住民は相互監視の目にさらされることとなった。カメラに写されるのを嫌がり帰る人、マスクとマフラーで顔を隠してくる人、家族を投票所に連れてくるも自分だけ自動車から出ない人などがいた。「会」はマスコミへの撮影自粛を要請した。そして住民投票は投票率45.3%、反対95%という結果になった。
佐藤町長は、「ルールにないため町政とは関係ない」と「会」との面談を拒否し、町有地を東北電力に売却しようとする。押しかけた住民により町議会は流会、そして町長リコール、辞任。次の選挙で「会」の笹口町長が誕生する。
あらためての住民投票は集票合戦となった。結果、投票率88.3%、反対60.9%という結果が出た。民意は明らかであった。しかし、町議会は推進多数であり県知事も推進派、放っておいたら危ないため、笹口町長は町有地の反対派への売却を行う。推進派の町議が裁判を起こしたものの、一審・二審ともに売却を是とし、2003年12月、最高裁は上告を受理しなかった。ほどなくして東北電力は建設を断念した。
この過程のなかで、住民投票という方法への批判が一部メディアからなされた。曰く、混乱させる。議会の存在意義を無にするものだ。国策に口を出してはならない。
しかし、そうではない。この過程は、民主主義とは何か、を問うものだ。

■ 音楽演奏(ウリ・ゲッテさん、ディエゴ・ヤスカレーヴィッチさん)
ドイツから来日中のウリ・ゲッテさんによるコンセプチュアルな感覚のピアノ演奏、ディエゴ・ヤスカレーヴィッチさんによるチャランゴ演奏があった。チャランゴは弦の本数が多い難しそうな弦楽器で、ずいぶん小さい。これをヤスカレーヴィッチさんは抱えるようにして弾いた。見事だった。


■ 藤本安馬さん(元毒ガス工場工員)
戦時中、広島の大野久島は毒ガス工場を抱えていた。機密のため地図から消されたりもした島である。藤本さんは、この島の工場で工員として働いていた。
藤本さんは、「ど田舎」の島での毒ガス製造と、「ど田舎」の地域での原発建設に共通点を見出している。そして、「あなたの問題はあなたの問題、私には関係ありません」という現代社会の共通意識が如実に顕れたのが原発であるとし、「あなたの問題は私の問題」とする団結の論理こそが求められるものだと訴えた。

■ 簡全碧さん(重慶大爆撃被害者)
簡全碧さんは旧日本軍による重慶大爆撃の被害者である。これにより家族の運命が一変し、精神的な傷が癒えないのだと語った。簡さんたちは、現在、日本政府に対して謝罪と賠償を求め、東京地裁での訴訟を起こしている。
簡さんは、真の中日友好は、この問題を解決してからだと訴えた。


重慶大爆撃の絵
■ 安次富浩さん(沖縄・ヘリ基地反対協議会)
広島から祝島行きにも同行する予定だった安次富さんは、結局、台風のために飛行機が飛ばず、電話でのアピールとなった。基地と原発は根っこは一緒であり、「僻地」や沖縄は虐げられる一方でアメによってがんじがらめになり、都市が受益者になっているのだと語った。
■ けしば誠一さん(杉並区議)
今回同行の新城せつこさん(杉並区議)と戸田ひさよしさん(門真市議)を紹介するとともに、中央からでは難しい反原発を進めるため、「反原発地方議員の会」を発足させたとアピールした。