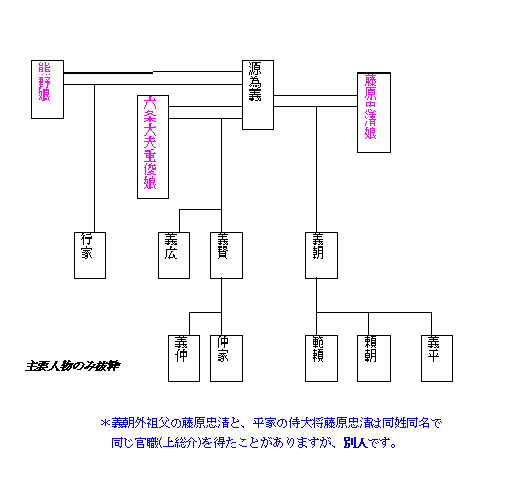その夜源頼朝の元に梶原景時は伺候していた。
「そうか、婚儀はつつがなく行なわれたか。」
「御意。昨晩つつがなく。」
「藤九郎の娘もけなげに内室の勤めを果たしておるとも聞いている。」
「殿の眼力には恐れ入ります。」
そこへ雑色が頼朝の元へ酒をもって現れた。
「どうじゃ、久しぶりにやらぬか。」
「恐れ入ります。」
頼朝に渡された酒器には折りたたまれた書状が目立たぬように添えられていた。
頼朝はそれをこっそりと読んだ。
「平三、どうやら北東の方が騒がしくなってきたようじゃ。」
「北東、だけでございますか?」
「北も、というべきであろうが、北には手が打ってある。」
「さようですか」
「手を打ったというよりも、なるべくしてなったというべきであるがな。」
「東国に対立の火種は事欠かぬ。
血筋を同じくするものの中の争い、領地を隣り合わせに持つものの争い、
などなどな。」
主従は静かに杯を酌み交わす。
「ところで平三、六郎と内室に明後日わしのもとへ来るようにと申伝えてくれぬか。」
「明後日、でございまするか?」
「そうじゃ、今宵は夫婦になってまだ二日目じゃ。
婚儀三か日は邪魔をしては悪いからの。」
「は!」
「六郎には、此度働いてもらわねばならぬ。」
頼朝は東北の方角をキッと見据えた。
前回へ 次回へ

「そうか、婚儀はつつがなく行なわれたか。」
「御意。昨晩つつがなく。」
「藤九郎の娘もけなげに内室の勤めを果たしておるとも聞いている。」
「殿の眼力には恐れ入ります。」
そこへ雑色が頼朝の元へ酒をもって現れた。
「どうじゃ、久しぶりにやらぬか。」
「恐れ入ります。」
頼朝に渡された酒器には折りたたまれた書状が目立たぬように添えられていた。
頼朝はそれをこっそりと読んだ。
「平三、どうやら北東の方が騒がしくなってきたようじゃ。」
「北東、だけでございますか?」
「北も、というべきであろうが、北には手が打ってある。」
「さようですか」
「手を打ったというよりも、なるべくしてなったというべきであるがな。」
「東国に対立の火種は事欠かぬ。
血筋を同じくするものの中の争い、領地を隣り合わせに持つものの争い、
などなどな。」
主従は静かに杯を酌み交わす。
「ところで平三、六郎と内室に明後日わしのもとへ来るようにと申伝えてくれぬか。」
「明後日、でございまするか?」
「そうじゃ、今宵は夫婦になってまだ二日目じゃ。
婚儀三か日は邪魔をしては悪いからの。」
「は!」
「六郎には、此度働いてもらわねばならぬ。」
頼朝は東北の方角をキッと見据えた。
前回へ 次回へ