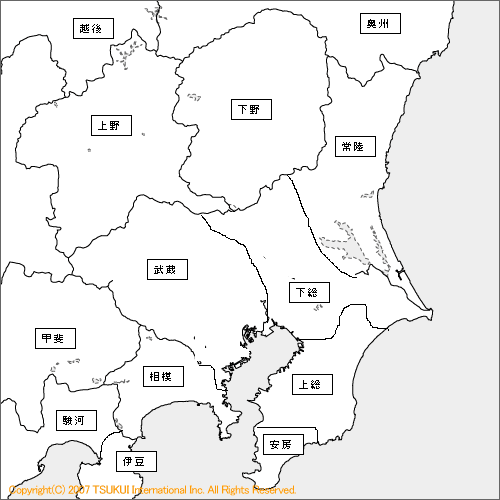義仲が鎌倉勢に攻められて都を落ちる前に、ある女性と名残を惜しんでいたという逸話が「平家物語」等の軍記物に記されています。
その名残を惜しんだ女性は「平家物語」諸本によって違います。
1.前摂政松殿基房の娘
2.都に入ってからのなじみの女房
という異なる相手が夫々記されています。
現在、小説などで描かれる場合は松殿の娘を取り上げているケースが多いように見受けられます。
ちなみに、義仲が松殿の娘を妻にしたという話は「平家物語」等の軍記物が主なソースで当時の「玉葉」などの日記等にはかかれていないようです。
木曽殿が本当に、最後に名残を惜しんだ女性がいたのか、いたとしたら相手はだれだったのか、非常に気になるところです。
ところで、義仲に関しては巴にしてもそうですが「軍記物」の記述があたかも史実であったかのように鵜呑みにされているような気がしてなりません。
もっとも「軍記物」鵜呑みは義仲に限ったことではないのですが、
学術的研究の世界においては、少なくとも清盛、重盛、頼朝、義経などに関しては
「脱軍記物」という試みがなされているようですが、義仲に関してはどうなのでしょうか?
「軍記物」は確かに面白いのですが、面白いが故にそれを史実だと思い込まされてしまう危険性を多分に含んでいるような気がします。

その名残を惜しんだ女性は「平家物語」諸本によって違います。
1.前摂政松殿基房の娘
2.都に入ってからのなじみの女房
という異なる相手が夫々記されています。
現在、小説などで描かれる場合は松殿の娘を取り上げているケースが多いように見受けられます。
ちなみに、義仲が松殿の娘を妻にしたという話は「平家物語」等の軍記物が主なソースで当時の「玉葉」などの日記等にはかかれていないようです。
木曽殿が本当に、最後に名残を惜しんだ女性がいたのか、いたとしたら相手はだれだったのか、非常に気になるところです。
ところで、義仲に関しては巴にしてもそうですが「軍記物」の記述があたかも史実であったかのように鵜呑みにされているような気がしてなりません。
もっとも「軍記物」鵜呑みは義仲に限ったことではないのですが、
学術的研究の世界においては、少なくとも清盛、重盛、頼朝、義経などに関しては
「脱軍記物」という試みがなされているようですが、義仲に関してはどうなのでしょうか?
「軍記物」は確かに面白いのですが、面白いが故にそれを史実だと思い込まされてしまう危険性を多分に含んでいるような気がします。