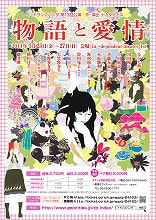
今までずっとナカタアカネさんの芝居を見てきたが、ここまでストレートに自分の心情を描いたものは初めてではないか、と思う。いつも主人公は自分をモデルにして、自分自身で演じてきたのだが、今回はちょっとタッチが違う。いつも、彼女の芝居を見るたびに「これ中田さんそのままじゃん」と思うけど、今までの「そのまま」は表層的なストーリーがナカタさん自身をなぞっているからであって、作品自身は決してそうではないのではないか、と思っていた。ある種のオブラードでくるんで見せている。それがありのままのナカタアカネというオブラードだった。
しかし、今回はそうじゃない。今までなら言わなかったような、自分のナマの心情を物語に乗せてきちんと言ってしまう。寅さんなら「それを言っちゃぁ、おしまいよぉ」と言うようなことまで、言ってしまう。そうすることで、作家としての自分にひとつの決着をつけようとしているように見える。文豪の名前を冠した登場人物の男たちに託したのは、「物語」という構造を信じるという覚悟ではないか。(遊びかもしれないが、ヒロインのリカの相手役となる男性には「ナツメ」、ゲストでその対極にある男性には「モリ」としたのもおもしろい。僕の見た回のモリを演じたのは、ごまのはえさんで、彼の気持ち悪さは絶品だった。)
たくさんの男の子たちに囲まれていても、本当の自分を見せることは出来ない。だが、引っ込み思案というのとは違う。とてもアクティブな女の子だけれど、自分の世界に閉じこもっている。なんだか相反するいろんなものが彼女にはある。そんな女性が、主人公のリカ(なかた茜)だ。彼女は劇作家だ。父(大竹野正典が遺影で登場する)も劇作家で、母(川田陽子)はTVの脚本家。リカのひとり暮らしの部屋が、この芝居の舞台となる。そこに様々な人々が出入りして、話が展開していく。
彼女の内面のドラマを、サイドストーリーとして見せながら、さらにはそこに隣の部屋に住む男の子(これがナツメだ)が登場し、彼とリカをセットにして、一人となるようにして描いてある。家族の問題を核にしっかり据えて、ラストでは母親や妹ときちんと向き合うことになる。ここまできっちりと正面からそういう問題を描くなんて、初めてのことだろう。自分の本音をぶつける妹がしゃべっていることを、ただ聞いているリカの姿を見ながら、この子が何も言えない心情がしっかり伝わってくる。しゃべらないことが、こんなにも饒舌な瞬間を見たことがない。それは彼女が言いたい気持ちを抑えている、のでもない。彼女は今、何も言わないことでこんなにもたくさんのことを言っている。その過剰さにうろたえるのだ。
ナカタアカネさんは、こんなにも小心で、寂しがりやで、だから、そばに誰かがいなくては、立っていられないような女の子を正直に認めてしまう。痛々しさではなく、そこに強さを感じる。
しかし、今回はそうじゃない。今までなら言わなかったような、自分のナマの心情を物語に乗せてきちんと言ってしまう。寅さんなら「それを言っちゃぁ、おしまいよぉ」と言うようなことまで、言ってしまう。そうすることで、作家としての自分にひとつの決着をつけようとしているように見える。文豪の名前を冠した登場人物の男たちに託したのは、「物語」という構造を信じるという覚悟ではないか。(遊びかもしれないが、ヒロインのリカの相手役となる男性には「ナツメ」、ゲストでその対極にある男性には「モリ」としたのもおもしろい。僕の見た回のモリを演じたのは、ごまのはえさんで、彼の気持ち悪さは絶品だった。)
たくさんの男の子たちに囲まれていても、本当の自分を見せることは出来ない。だが、引っ込み思案というのとは違う。とてもアクティブな女の子だけれど、自分の世界に閉じこもっている。なんだか相反するいろんなものが彼女にはある。そんな女性が、主人公のリカ(なかた茜)だ。彼女は劇作家だ。父(大竹野正典が遺影で登場する)も劇作家で、母(川田陽子)はTVの脚本家。リカのひとり暮らしの部屋が、この芝居の舞台となる。そこに様々な人々が出入りして、話が展開していく。
彼女の内面のドラマを、サイドストーリーとして見せながら、さらにはそこに隣の部屋に住む男の子(これがナツメだ)が登場し、彼とリカをセットにして、一人となるようにして描いてある。家族の問題を核にしっかり据えて、ラストでは母親や妹ときちんと向き合うことになる。ここまできっちりと正面からそういう問題を描くなんて、初めてのことだろう。自分の本音をぶつける妹がしゃべっていることを、ただ聞いているリカの姿を見ながら、この子が何も言えない心情がしっかり伝わってくる。しゃべらないことが、こんなにも饒舌な瞬間を見たことがない。それは彼女が言いたい気持ちを抑えている、のでもない。彼女は今、何も言わないことでこんなにもたくさんのことを言っている。その過剰さにうろたえるのだ。
ナカタアカネさんは、こんなにも小心で、寂しがりやで、だから、そばに誰かがいなくては、立っていられないような女の子を正直に認めてしまう。痛々しさではなく、そこに強さを感じる。
























