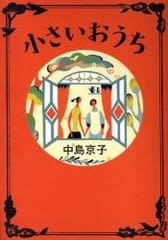
『女中譚』に続いて再び【女中】を主人公にして描く中島京子の新作。前作をウォーミングアップにして、今回は長編として昭和初期を舞台にしたひとりの女中の姿を追った野心作。老嬢が60年以上も前の日々を振り返って行く。彼女の10代後半から20代半ばまでの一番幸せだった日々のいくつもの思い出が順を追って語られていく。昭和5年春から19年の春まで。尋常小学校を出たばかりのタキが山形から東京に出てきて、女中として生活するスケッチは僕等が想像する[昭和の初め、女中奉公]というものの持つイメージとは微妙に違う。そこがこの小説の魅力だ。
全体の構成は、現在のタキが、回想録を書く、というスタイルになっている。それを近所に住む甥っ子の健史が覗き読みしていろいろ突っ込みを入れる。彼(現代を生きる普通の青年)の視点から見た昭和初期と、タキの目に映った現実との落差がおもしろいのは先に書いた通りだ。学校で教わったこと、頭で考えたことと、事実の間には微妙な齟齬が生じる。戦争に突入していく時期、その当時の上流階級の意識、さらには庶民レベルでの理解と、今を生きる僕等の意識の間にもかなりの違いがある。タキは必ずしも思い出を美化しているわけではない。
彼女は赤い三角屋根の洋館で過ごした15年間の日々を、とても愛おしいものとして受け止めている。そのささやかな日々のひとつひとつの出来事は彼女にとってはかけがえのない歴史として心のかたすみに色鮮やかに今も残る。
この小説を読みながら、昭和10年前後という時代のささやかだけど幸福な時代を、彼女の視点で見つめていくことを通して、知っている気になっていただけで何にも知らなかった「昭和」を追体験する。だが、この小説はそれだけでは終わらない。大仕掛けが最後に用意されてある。
故郷の村に帰ってからの描写を挟んで、注目は最後の章である。そこでは、タキの死後、健史が彼女の手記に書かれなかった記憶をたどる旅が描かれる。ここでこの小説はがらりとタッチを変えていく。ノーテンキに見えた回想録が、改めて一つの時代の真実を提示することになる。さらには、時子奥さまとタキ、ぼっちゃんの3人を見つめていた板倉さんの視線が大きくクローズアップされ、彼がこの赤い小さな家の中で見たものが浮かび上がってくる。あやういバランスのうえで奇跡的に成り立っていた幸福というものを、板倉さんを通して描くこととなるのだ。
時子奥さまが秘かに心を交わしていた板倉という男性が脇役から重要なポジションを獲得することで、この小説はようやくドラマの確信に迫ることとなる。発見された『小さなおうち』と題された板倉の幻の紙芝居。その紙芝居の持つスタイル(中心に丸で囲まれた世界がありそこでは2人の女と子どもがいて、その周囲に外の世界がある)と、その内容(幸福な時間と悲惨な戦争体験を象徴的に描く)は衝撃的である。板倉がそこに託した想いは、時子への憧れだけではなく、あの時代の幸福を見事に指し示す。それはもちろん単純に甘いだけのものではない。痛ましいものも含めて、あの家の幸福を描くこととなる。それは、そこまでタキのことが理解できなかった健史にも通じる。最後に提示されるこの距離感があるから、この小説は傑作になり得たのだ。
全体の構成は、現在のタキが、回想録を書く、というスタイルになっている。それを近所に住む甥っ子の健史が覗き読みしていろいろ突っ込みを入れる。彼(現代を生きる普通の青年)の視点から見た昭和初期と、タキの目に映った現実との落差がおもしろいのは先に書いた通りだ。学校で教わったこと、頭で考えたことと、事実の間には微妙な齟齬が生じる。戦争に突入していく時期、その当時の上流階級の意識、さらには庶民レベルでの理解と、今を生きる僕等の意識の間にもかなりの違いがある。タキは必ずしも思い出を美化しているわけではない。
彼女は赤い三角屋根の洋館で過ごした15年間の日々を、とても愛おしいものとして受け止めている。そのささやかな日々のひとつひとつの出来事は彼女にとってはかけがえのない歴史として心のかたすみに色鮮やかに今も残る。
この小説を読みながら、昭和10年前後という時代のささやかだけど幸福な時代を、彼女の視点で見つめていくことを通して、知っている気になっていただけで何にも知らなかった「昭和」を追体験する。だが、この小説はそれだけでは終わらない。大仕掛けが最後に用意されてある。
故郷の村に帰ってからの描写を挟んで、注目は最後の章である。そこでは、タキの死後、健史が彼女の手記に書かれなかった記憶をたどる旅が描かれる。ここでこの小説はがらりとタッチを変えていく。ノーテンキに見えた回想録が、改めて一つの時代の真実を提示することになる。さらには、時子奥さまとタキ、ぼっちゃんの3人を見つめていた板倉さんの視線が大きくクローズアップされ、彼がこの赤い小さな家の中で見たものが浮かび上がってくる。あやういバランスのうえで奇跡的に成り立っていた幸福というものを、板倉さんを通して描くこととなるのだ。
時子奥さまが秘かに心を交わしていた板倉という男性が脇役から重要なポジションを獲得することで、この小説はようやくドラマの確信に迫ることとなる。発見された『小さなおうち』と題された板倉の幻の紙芝居。その紙芝居の持つスタイル(中心に丸で囲まれた世界がありそこでは2人の女と子どもがいて、その周囲に外の世界がある)と、その内容(幸福な時間と悲惨な戦争体験を象徴的に描く)は衝撃的である。板倉がそこに託した想いは、時子への憧れだけではなく、あの時代の幸福を見事に指し示す。それはもちろん単純に甘いだけのものではない。痛ましいものも含めて、あの家の幸福を描くこととなる。それは、そこまでタキのことが理解できなかった健史にも通じる。最後に提示されるこの距離感があるから、この小説は傑作になり得たのだ。

























