街の駅の展示替えをしました。毎年11月23日に行っている「草刈りボランティア」についての展示です。
なぜ、乙女高原には草刈りが必要なのか、乙女高原で草刈りしないとどうなるのか等を説明しています。
草刈りのちらしも置いてあります。ぜひお持ちください。
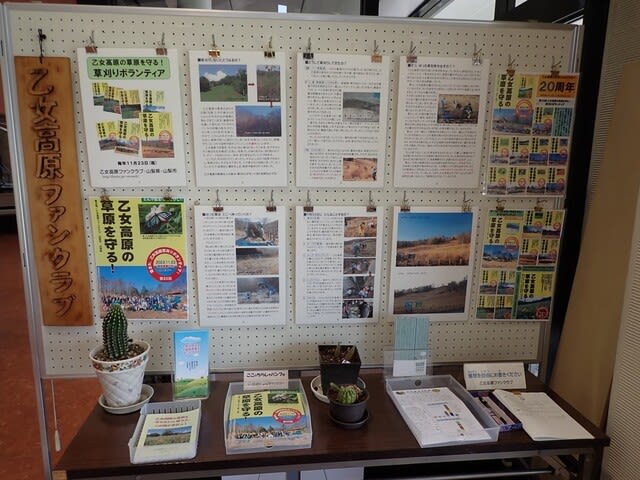
街の駅の展示替えをしました。毎年11月23日に行っている「草刈りボランティア」についての展示です。
なぜ、乙女高原には草刈りが必要なのか、乙女高原で草刈りしないとどうなるのか等を説明しています。
草刈りのちらしも置いてあります。ぜひお持ちください。
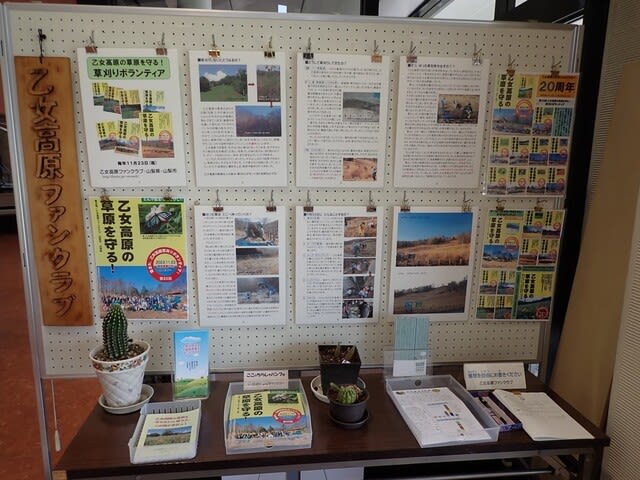
※井上さんがレポートを書いてくださいました。
シカ柵設置直前から年に一度行っている、高槻先生指導の植生調査を実施しました。調査地点は草原内に10か所。ポールが立っているのですが、毎年、そこの植生を調査します。今年の調査に集まったのは8名。

いつもは入れない遊歩道のロープの中に入っていきます。ポールが立っている所で、折り尺2本を使って、1m四方の方形を作って、その中にどんな植物があるかを調べます。まず10cm×10cmの中の植物、次に10×25、25×25、25×50、50×50、50×100、100×100というふうに範囲を広げていって、あった植物を記録していきます。もう花の咲き終わったものが多く、葉で植物名を同定しなくてはなりません。特に根生葉のものや小さな葉のものは何の植物なのか、判断の難しいものもありますが、高槻先生や植原さんが植物名を同定していきます。他の人たちは周りでその様子を見ていますが、植物の同定では、葉の形や葉柄など、植物をよく観察しなくてはならないことがわかり、皆、興味深げでした。私は記録を担当しました。

1m四方の中の植物の同定が終わると、高槻先生がその植物の「被度」(調査区内で出現した各植物種が、どの程度の面積を占めているのかを示す尺度)と「高さ」も見ていき、それを記録します。その後、1m方形の外側1m×2mと2m×2mに新たに見られた植物も記録して、1区画の調査が終わります。
午前中5か所、午後5か所の調査をしました。記録していくと1か所で30種類くらいの植物があり、植物が増えてきているのがわかります。また、同じ草原内でも地点によって、見られる植物が少しずつ違うことも興味深いです。

参加した何人かは始めは調査の様子を見ていましたが、特定外来植物のヒメジョオンをあちこちに見つけて、この駆除作業をおこなってくれました。
1週間前に比べると、夏の花はほとんど終わっていますが、ヤマラッキョウが花盛り。やはり増えているようで、たくさん咲いていました。ノハラアザミは次々に咲くようで、咲き終わりもあるけれど、まだきれいに咲いているものも多かったです。これらの花にはウラナミシジミやセセリチョウ、アブやハムシがきていました。ノダケの上には、キアゲハの幼虫がいっぱい。2,3歳のものから終齢のものまでさまざまな時期の幼虫がいました。1つのノダケには8匹もいました。花や葉を食べつくしていて、これから寒くなるのに大丈夫かと気になりました。




まだまだ残暑厳しい中、6/21、7/11、7/29、8/19に引き続き、今年5回目となる「花と昆虫のリンク」調査を行いました。今回は事前申し込み者がなんとゼロで(9月上旬に乙女での催しが目白押しだったのが理由だと思います)心配しましたが、ロッジに着くと、井上さんの姿が見えたので、ちょっと安心しました。

高槻先生、井上さん、植原と3人で調査を開始しました。できるだけ同じ時間帯に調査したいので、今回は3人がそれぞれ別のルートを歩いて、別々に記録を取ることにしました。

もう調査は慣れたものです。メジャーをめいっぱい伸ばして、帰りながら花に来ている昆虫を時刻と距離とともに記録していき(往路)、メジャーの「0・伸ばし始め」に到着したら、今度は遊歩道の反対側を記録しなから、メジャーのところまで行ったら(復路)、1ステージ終了です。これを繰り返して、乙女高原の全遊歩道をクリアします。

8月の調査では往路だけで調査用紙が3枚必要になるところが続出し「勘弁してよ」と思いましたが、今回はどのコースも往路1枚・復路1枚ずつで済んだので助かりました。

それでも、お昼を食べた後も調査を続け、結局、終わったのは3時ごろになってしまいました。

2013年(乙女高原を囲うシカ柵設置前)に、当時、麻布大学の卒研生であった加古さんが行った調査結果と比較しようと、高槻先生のご指導で2020年から再出発(?)したこの調査です。自然を観る目を鍛えられた気がします。ひとことで言うと「目の前で起きていることをしっかり観ろ」ということでしょうか。

たとえば、一般的にはカメムシは「植物の茎などに注射針のような口を刺して汁を吸う」と言われて(思われて)います。昨年まではカメムシが花にいたとしても、花にたかって、外から口を刺して汁を吸っているとしか思いませんでした。ところが、今年、オミナエシの花の中に口を突っ込んで、蜜を吸っているように見えるカメムシがいました。それまでカメムシを「訪花昆虫」「送粉者」として認識していませんでしたが、カメムシも送粉に一役買っていると思うようになりました。また、ハサミムシは「地面にいる虫」というイメージがあると思いますが、ツリガネニンジンなどの花の中に頭を突っ込んでいるものがいます。これも送粉に一役買っているのだと思います。もしかしたら、私たちはハサミムシの飛翔能力を十分に理解していないのかもしれません。

今日、とったデータは、高槻先生がエクセルに打ち込んで、その結果から考察されていきます。高槻先生、いつもいつも、大変な仕事をありがとうございます。

日 時:2023年9月14日(木) 午後7:00~8:30
乙女高原連絡会議
■第22回草刈りボランティア (検討・連絡会議)
・送迎車両は10人乗りと7人乗りのワゴン車を予定(林道通行許可申請は不要か)(市)。
・刈った草は(株)田丸のパッカー車を頼んで運んでもらう(依頼済)(FC)。
・11/11(土)に予定していた準備作業は、11/10(金)の「観光地美化清掃」終了後に続けて行う(FC)。
・「悪天候の場合の実施決定マニュアル」は来年改訂する。悪天候が予測される場合、前日に中止決定するように変える。
・次回連絡会議から、「準備品」や「準備項目」の進捗状況を確認する。
・例年の「昼食➝終わりの会」を入れ替えて「(記念写真➝)終わりの会➝昼食」とする。
・市長は参加する予定(市)。
■第21回乙女高原フォーラム (検討・連絡会議)
・開催日とした1/28(日)に「なんでも鑑定団」の収録が行われることが判明➝前後一週間のどちらかに移動
・9/22(金)にズームで講師と打ち合わせを予定
■第5期乙女高原案内人養成講座2024 (検討・連絡会議)
・今回、提案されたことを、次回以降に検討。講師(10人)、開催期間3日間(5、6、7月に1日ずつ)等
・TOYO TIRE環境保護基金の2024年度助成に申請済
・養成講座テキストの全面改訂 A4判180ページ(2006年初版)から270ページへ。編集中。
・市・県への後援依頼事務を進める。
・会場は乙女高原
乙女高原ファンクラブ世話人会
■『乙女高原ガイドブック』発刊 (検討・世話人会)
・頒価300円に決定。謹呈先については、学校、図書館等。必要なところには事務局判断で謹呈。
■花と昆虫のリンク(訪花昆虫)調査 (振返り・世話人会)
・2023年は6/21、7/11、7/29、8/19・21、9/16に実施。高槻先生がデータ入力と考察
■21期マルハナバチ調べ隊 (振返り・世話人会)
・2023年は6/25(ラインセンサス7)、8/5(同119)、9/2(同100)に実施。
■第8回谷地坊主の観察会 (振返り・世話人会)
・7/1に実施
■夏の案内活動 (振返り・世話人会)
・7/22、7/23、7/29、8/5、8/6と6日間開設。約100人を案内。
■遊歩道の草刈り (振返り・世話人会)
・7/22 遊歩道が歩きやすくなった。
■笛川小・日下部小の乙女高原自然観察学習 (振返り・世話人会)
・笛川小5年生20名9/5 (1)ブナ爺班 (2)谷地坊主 (3)草原満喫
・日下部小4年生56名9/12(1)ブナ爺班 (2)谷地坊主班 (3)草原満喫班 (4)草原の謎班
■新規案内人の認定
・世話人会の総意で新乙女高原案内人を承認。ワッペンと名札を贈与した。
■そのた
・林道の至る所で伐採が行われているが、シカの個体数増加を招かないか?
・駐車場で夜間ライトトラップを行った痕跡が複数回見つかっている。規制はできないか。
➝行政として無理なら、ファンクラブでお願いしたり、しないようキャンペーンを行うことは可能か。
【次回連絡会議/世話人会】10月19日(木)19:00~ 牧丘総合会館 (山梨市役所牧丘支所)
山梨市内の学校が乙女高原を訪れて自然観察学習するのを「乙女高原案内人」がサポートする・・・というのをもう21年続けています。旧牧丘町内の全3小学校を案内する年も7年間続きました。旧牧丘町内の小学校は「笛川小学校」に統合されました。雨で中止になった年はありますが、統合後もずっと5年生を案内しています。

今年はさらに「日下部小学校」からも案内のリクエストがありました。喜んでお引き受けしました。とはいえ、案内人の減少と高齢化は止められません。これを読んでいる方で「子どもたちと一緒に自然観察を楽しみたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡をいただきたいと思います。『教えてうえちゃん・乙女高原スペシャル』動画や『乙女高原の自然観察』ガイドブックで事前に「研修」しておくことができますし、なにより、「子どもたちと一緒にお散歩しながら自然を楽しむ」という気持ちが大切だと思います。「何かを教えよう」という態度だと、かえって子どもたちも楽しめません。

さて、笛川小学校の5年生20人が引率の先生と一緒にスクールバスでいらっしゃったのは9月5日(火)でした。ですが、8月31 日に植原が笛川小学校を訪れて、子どもたちにスライドの写真などを見せながら、乙女高原の今の様子や、草原保全の要となる草刈りの意義や歴史、乙女高原のキーストーン種であるマルハナバチの説明などをしました。こういうのを事前学習といいます。また、このときに担任の先生と打ち合わせをしたので、その結果をもとに、参画する乙女高原案内人の打ち合わせをマルハナバチ調べ隊の終了後に行いました。このような準備をして、当日を迎えたわけです。

トイレを済ませ、一休み後「はじめの会」が始まりました。司会は子どもがしていました。案内人から一人一言、自己紹介をしました。事前に子どもたちは一人一人の希望をもとにを3つの班に分かれていました。その班ごとに自然観察ハイキンに出発しました。途中で水分補給することを徹底しました。
ブナ爺班は、案内人の角田さん・松林さんと一緒にブナ爺さんのもとに向かいました。ブナ爺さんのウエストを巻き尺で測って、同じ大きさのわっかがどれくらい広いか確かめていたようです。谷地坊主班は植原がお相手をしました。途中、「なぜ、ここの遊歩道を使わなくなったのか」や「この小さな四角い柵は何なのか」などの説明をしながら、谷地坊主を見に行きました。草原満喫班は芳賀さんや駒田さんと一緒に、草原でじっくりお花たちやマルハナバチを見て来たようです。
どの班もペットボトルで作った昆虫観察グッズが大活躍。普通、昆虫観察器というとカップ状になっていて、上からしか覗けないのですが、これは全方位から見ることができます。虫を入れる時も口が広いので入れやすいし、このような容器の中に入っていると、虫嫌いな子も顔を近づけることができます。なんといっても、虫を子どもたちの魔の手から(!?)守ることができます。これは滋賀県在住の自然観察指導員が考案したものです。自然観察会でとっても重宝しますよ。

自然観察ハイキングから帰ってきたら、一休みして、あとは各自で自由に自然観察する時間にしました。各班で帰ってくる時間はまちまちですし、学校でこのような「校外学習」を企画すると、たいがい次から次へとスケジュールをこなすようになっていて、子どもたちの自由時間などないからと考え、設定しました。
ところが、初めて乙女高原を訪れる子が多かったし、高原とはいえ暑かったので、ほとんどの子は木陰で休んでいました。こういうときは、先生方が「ガキ大将」の役割をして子どもたちを積極的に「追い出す」「誘って連れ出す」のがいいかなと思いました。
「おわりの会」も子どもたちが司会進行し、私たち案内人も一言ずつ感想を述べさせてもらい、子どもたちとさよならをしました。子どもたちを見送って後、みんなでお昼を食べながら歓談しました。「なかなか孫に会えないからねー。孫と一緒に歩けたようで楽しかったよ」という話が印象的でした。

日下部小学校の4年生56名が引率の先生方と乙女高原に来られたのは9月12日(火)でした。流れは笛川小とほとんど同じでしたが、もちろん学校によって、例えば児童数や学年、学習のめあてなどが違うので、学校に応じてカスタマイズしています。

たとえば、日下部小は56名と子どもの数が多いので3班ではなく、4班にしました。ブナ爺班:角田・松林、谷地坊主班:植原、草原満喫班:駒田のほかに、案内人の鈴木さんにお願いし、草原が森に変わらないヒミツを探っていく草原の謎班を新たに作りました。
また、日下部小の方が笛川小より遠いので、後半の自由時間が少なくなりました。しかも、結局、大人数でトイレの時間がかかり、自由時間はほとんどとれませんでした。でも、臨機応変でいいのです。スケジュールは絶対的なものではなく、あくまで目安です。とはいえ、「終わる時刻」は厳守です。
 子どもたちを見送った後、案内人のみんなでお昼を食べました。来年、もっと多くの学校から案内リクエストがあるといいですね。
子どもたちを見送った後、案内人のみんなでお昼を食べました。来年、もっと多くの学校から案内リクエストがあるといいですね。
