
今回、一番子どもたちを夢中にさせていたのは、慶應義塾湘南藤沢中等部の上の問題です。
(慶應義塾湘南藤沢中等部の受験問題は、算数にしても国語にしても、
子どもたちから、考えることへの愛情を引き出してくれるような問題が多いので大好きです。
思考力は必要でも、公式などは知らなくても解けるものがたくさんあるので、小3や小4の子たち
も解くことができます。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
右の図のように、1辺の長さが3㎝の立方体を積み上げて、
立体を作っていく。このとき、次の問いに答えなさい。
①5番目にできる立体の体積を求めなさい。
②29番目にできる立体の面の数を求めなさい。たとえば、2番目にできる
立体の面の数は10枚である。
③面の数が602枚になるのは何番目のときですか。
(慶應義塾湘南藤沢中等部 平成21年度)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①はどの子にも易しかったようで、すぐに解いてしまったのですが、
②には頭をひねっていました。
それぞれ必死に考えていて、正解にたどりつけた子は小躍りして喜んでいました。
③は算数難問研究部の後、午後からある科学クラブで(そちらにも参加していた一部の子たちに)
解いてもらいました。
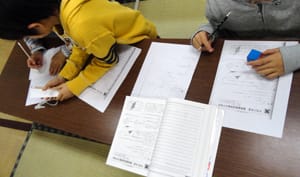

②を解く前に、
<たとえば、2番目にできる
立体の面の数は10枚である。>
ということを、立方体の積み木で、数え方を確認しておきました。
そんな風に「小さい数を扱っている段階で、自分の理解をしっかりさせておいて、
大きい数を扱う推理に役立てる」ということを
学習中です。
子どもたちが夢中になって算数の問題に取り組むようになるのに、
最初はチームで協力しあって解いて、途中からこれは自力で最後まで解けそうという子が
チームから抜けて個人で答えを出す、
という方法がうまく機能することが多いです。

かなり難しくて、それでいて、知識はなくても思考力があれば解いていけるような問題を、
みんなで解いていくのです。
難解な図形の角度を求める問題だと、
どこにも角度が書いてないので、自分で補助線を引いて、
角度を作りだして解いていくことがあります。
そんな時には、「正三角形を見つけ出せ(60度が生まれるから)」
「2等辺三角形を見つけ出せ(底辺の両端の角が同じなので、そこから答えが見つかるから)
「直角をさがせ」「対角線を引いて45度を作りだせ」といった
探しっこゲームのような形で楽しんでいるうちに、
しまいに最後まで自分で答えを突き止めたいという気持ちになっていきます。
それと同じ要領で、文章題の線分図に隠れた秘密を見つけ出すような
調子で楽しむうちに、自力でしっかり解くようになっていました。
文章題にしても、図形問題にしても、子どもたちは
自分なりの考えで正解にたどりついていたため、答えはあっているものの、
解答欄にあった解き方とは異なる子たちもいました。
より効率的な解き方を学ぶために、
答え合わせをして正しい解き方を確認するのも大事でしょうが、
それぞれが自分の思考力で答えを導きだす力を持っていることも
大切にしていってあげたいと感じています。




算数の学習の前に子どもたちが協力して電子工作の
「申し訳ない」とえらい人が頭をさげる人形を作っていました。
設計図を隅々まで読んで、自分たちだけで
こうしたものを仕上げることができるのは、
頼もしいです。






















