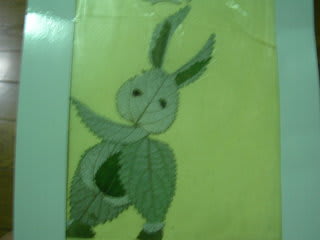三時過ぎになると咲くというサンジソウ
「何処からか飛んできて、いつのまにやらウチの庭で咲いてるの、二時やったら咲いてなくて三時過ぎになると咲くんよ、そやから三時草」と教えてくれた友人。
そよかぜさんあのね、フシギね・・・
オオマツヨイグサ、ツキミソウ、オシロイバナいろいろありますよね、時間を待って咲く花たち。
これらの花たちは体内時計みたいなものがあるのかしら?
Re:そよかぜ
写真はスベリヒユ科のハゼランですね。
多くの花で、一日のうちで花の咲く時間がほぼ決まっているようです。
虫との“待ち合わせ時間”なんでしょうね。
これを「内生(ないせい)リズム」と呼んでいます。
内生リズムは植物体内で働いている酵素のリズムで、最近ではこれらの酵素を支配している遺伝子の研究から、内生リズムを支配しているしくみを知ろうとする研究も始まっているようです。
もうひとつのサンジソウ
タンポポのような、夏に咲く黄色い花

Re:そよかぜ
夏に咲く黄色い花というのは、ツルナ科のベルゲランサスだと思います。
オシロイバナ~白粉花~(オシロイバナ科)



こちらは4時過ぎに咲くといわれてます。
熟した黒く固い種をつぶすと白粉(おしろい)のような”白い粉”が出てくる。
名前の由来はそこから。
名づけ親は江戸時代の博物学者、貝原益軒。
夕方頃に活動する昆虫には、花の多彩な色で引きつけ,夜に活動する昆虫には、その香りで引きつける。→花の本より
遠い昔、私が子供だったころ、オシロイバナの細いところをくわえて笛みたいに鳴らしてよく遊んだこと・・・
ふと思い出し、やってみた。

向こう側の短いほうが「ぷぅ~~」とよく鳴った・・・・
くちびるにビビビビビと細かく×2響くのも思い出しました。