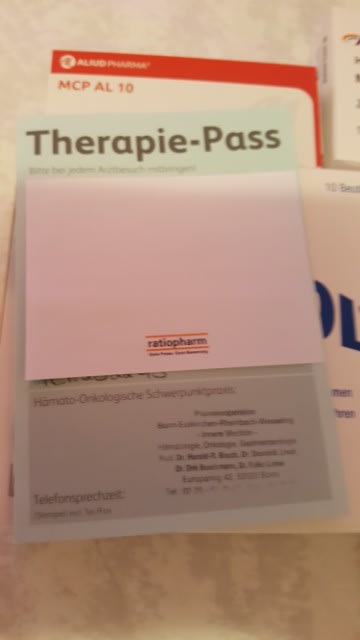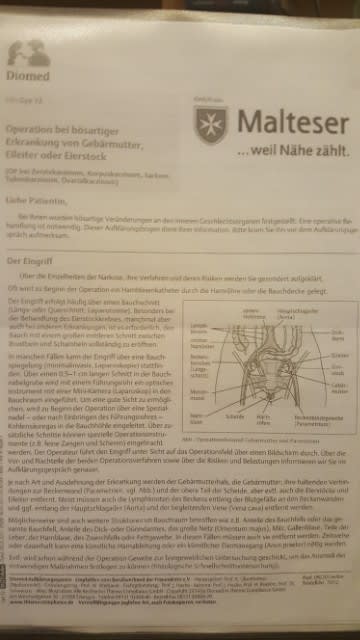唐突ですが、10日ほど入院していて、今日(7月26日)退院しました。最終的な診断書と治療方針などを含む紙の束を抱えて。
(がん患者のための社会保障は記事末尾にまとめてあります。)
診断から手術まで
事の起こりは6月12日にかかりつけの婦人科にがん予防定期検診に行ったことでした。そこで例年のごとく超音波検査を受けたのですが、ドクターが画像を見ながら「うーん、これは全く気に入らない」とかなり長いこと唸っていたので、何かと思ったら、前回(15か月前)には影も形もなかったのに、いきなり3cmの子宮筋腫(Myom)ができていると言うのです。通常子宮筋腫というのは良性で成長も遅いものです。何年もかけて数ミリ成長するのが相場なので、15か月以内に3cmは確かに異常な成長率です。私は2年前に既に子宮筋腫で子宮掻爬術(Abrasio des Corpus uteri)を受けており、今回は再発なので、子宮切除を勧められました。
「子宮の切除」などいきなり受け入れられるわけもなく、セカンドオピニオンを聞きたいと思いまして、とある超音波診断専門医を紹介していただき、早速予約を入れて、6月19日に診察を受けました。その女医さんも「子宮切除」に関しては同意見で、「子宮筋腫ばかりでなく、子宮内膜の様子も変」という所見を出し、3週間以内に何らかの処置をとるように強く勧められました。
その診察の帰りにまたかかりつけの婦人科に戻り、診断書を渡すと、「既にファックスが届いてる」と言われて、驚きました。とにかく緊急性が高いので、翌朝に診察に来るように言われました。
翌朝にその婦人科へ行くと、子宮切除に関する意向を聞かれたので、切除に同意しました。希望する病院があるかどうか聞かれたので、それはないと答えると、その婦人科医は「マルテーザー病院がいい」と言って、彼の助手に病院の予約を電話で入れるように指示しました。電話でその助手が病院に断られそうになっているのを見て取るや、自分で受話器を取り、私の診断と緊急性を説明して、なんと翌日に予約を「ねじ込み」ました。やはり緊急性があると扱いが違うのだな、と驚きました。ドイツでは病院などの予約を患者自身が入れようとすると場合によっては数か月先になってしまうこともざらにあるからです。
さて、翌6月21日に、そろそろ病院へ行く支度をしようかと思った頃にかかりつけの婦人科医から電話があり、子宮頚の組織検査の結果が「悪性腫瘍」だったことを知らされました。その最新の診断結果もマルテーザー病院の方へファックスしてくれました。それで実際に病院へ行ってみると、確かに書類は全部届いてましたが、それでも私が一から説明することからは逃れられませんでした。要するに書類整理がまだできてなかったみたいですね。
とにかくそこでも超音波検査を受けました。その際マルテーザー病院婦人科の医局長が自ら立ち会っていたのですが、画像を見ながら「子宮内膜がん(子宮体がんともいう)みたいだね」と軽くのたまりました。その診断そのものにもびっくりでしたが、なぜそんなすぐに予想が立てられたのかそのことにも驚きました。同じ超音波検査なのに、機械の精度の違いなのでしょうか。経験の違いもあるかもしれません。
というわけで診断は「子宮筋腫」⇒「子宮筋腫+子宮内膜病変?」⇒「子宮筋腫+子宮内膜がん?」と発展しました。
まずは本当にがんであるかを確認するために、子宮掻爬術(Gebärmutterausschabung, Abrasio des Corpus uteri)で子宮内膜を採取することが決定し、その手術を6月26日に受けました。この時は入院ではなく日帰りでした。24時間は車の運転をしてはいけないことになっていたので、ダンナに迎えに来てもらいました。
この手術で掻き出した子宮内膜の組織検査の最終結果を聞いたのは7月6日のことです。「子宮筋腫+子宮内膜がん?」の「?」が取れて診断が確定しました。ステージはまだ不明でしたが、悪性度はG2(通常の速さで増殖)とのことでした。
他器官への転移がないかを調べるためにその翌日にCT検査を受け、「転移なし」の結果が出たので、7月16日入院で、17日に卵巣・卵管を含む子宮全摘手術が決まりました。術式は基本的に腹腔鏡手術(Laparoskopische Chirurgie)で、場合によっては開腹手術に変更になることもある、とのことでした。また切除部位も術中に変更することもあるとか、あれやこれやのリスクがあることを詳細にわたって知らされ、「そのリスクを全て了解した上で手術に同意しますか」と聞かれて逃げ出したくなりました。「インフォームド・コンセント」のドイツ版です。
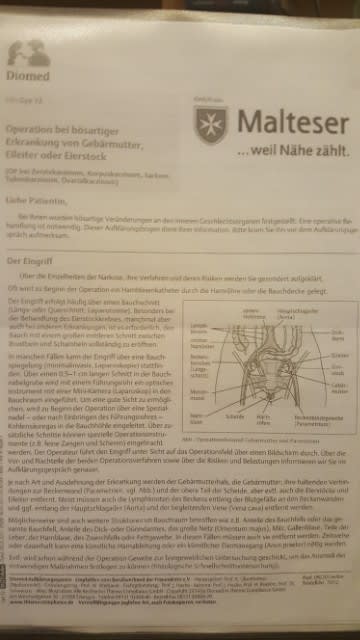
どんなに確率の低いリスクでも、症例があれば全て言及するのがドイツ式です。こうなると患者の意思の尊重ではなく、病院や医師を訴訟などから守るためのものと言えます。患者には余計な心配が増えるばかりです。心配や不安が強まると免疫力が低下するので、治療的観点から見るとこのドイツ式インフォームドコンセントは全くマイナスにしかなりません。「知らぬが仏」って言葉あるよなあ、と考えながら、同意書に署名しました。
フランスでは、患者が質問すれば医師も詳細に答え、質問が無ければ特に言及しないそうです。お国違えば… ですね。
そんなこんなでビビりながらも16日の夕方に入院しました。

病室は2人部屋で、取りあえず私一人でした。
病棟にはテーブルと椅子が置かれた広いベランダがあり、病室よりはちょっと開放感があります。


このマルテーザー病院は「森の病院」という別名があり、本当に森に囲まれているので、環境はいいと言えますが、入院してしまえば、周りが森でもあまり関係なくなりますよね。
お昼以降は食べてはいけないと指示されていたので、お腹ぺこぺこなのを水を飲んで誤魔化してました。手術前の処置として血栓症(Thrombose)防止用注射(Clexane)を受け、浣腸もされました。
そして翌朝9時少し過ぎに手術室に搬入され、病室に戻されたのは夜の8時過ぎでした。手術時間は正味9時間ちょっとだったようです。腹腔鏡による卵巣・卵管を含む子宮全摘(Totale laparoskopische Hysterektomie mit Adnexektomie beiderseits)だけで約1時間半、リンパ節郭清(Pelvine und paraaortale Lymphonodektomie)も含めておよそ4時間の手術と予想されていましたが、術中に卵巣への転移および子宮の外側の腹膜にもがんが見つかったため、急遽大網膜も切除する(Omentektomie)ことになったのでした。大網膜は血管や神経が集中する繊細な組織なので、慎重に扱う必要があり、そこに最も時間がかかったようです。
手術後に患者は「覚醒室(Aufwachraum)」とでもいうのでしょうか、そういう特別な部屋に運ばれて、麻酔から覚めるまで厳しい観察下に置かれます。麻酔から目覚める時、多くの人が吐き気を催したりしますが、私は過去2回とも何事もなく目覚めたので、事前問診でそのように回答してあったにもかかわらず、今回はものすごい吐き気に襲われ、担当の看護師さんが驚いていました。ともかく吐き気に効く薬を注射され、酸素チューブを装着されました。私はその時眠りたくて仕方なかったのですが、「病棟からの迎えが来るまで起きてて」と体をゆすられて何とか覚醒状態を保ってました。ここからは起きた患者さんしか病棟に引き渡せないことになっているんですね。
病室に戻ったとき、のどがカラカラで辛かったです。
ダンナが手術にかかった時間やおおよそ何が行われたのかを説明してくれましたが、うつろな意識でそれを聞きながらあっという間に眠りに落ちてしまいました。看護婦さんたちにもいろいろ質問されたような気がしますが、何をどう答えたのか覚えていません。
手術後の経過
翌日は看護婦さんたちに支えられながらベッドから起き、1回立ち上がっただけで、後はずっと寝てました。食べていいとは言われましたが、殆ど食べられない状態でした。冷や汗をかいて眩暈がするなど循環器系の問題がありました。
二日目も似たようなものでしたが、立ち上がるだけではなく、病室の中を少し歩かされました。
三日目に尿カテーテルが取れて、一人でトイレに行けるようになり、大分不快感がなくなりました。食事も少しできるようになりました。鎮痛剤も点滴から錠剤(イブプロフェン400)に切り替わりました。この日、従手リンパドレナージの施術も受けました。

四日目にはドレーンも取れてすっきりし、トイレばかりか病棟の中を歩き回れるようになれました。でも非常に疲れやすく、食欲も余り回復してませんでした。
五日目から出されたものが完食できるようになり、このあたりから自分でも分かるほど回復してきました。因みに病院食は下の写真のような感じです。


パン食は朝晩出され、昼食だけが温かい食事になります。私のはベジタリアンメニューでした。朝晩同じようにラクトーゼフリーのチーズが続き、見るのも嫌になりましたよ。この日は車イスを借りて森に散歩に行きました。まだ一度にたくさん歩けなかったため、車いすに座って押してもらう時間の方が長かったのですが、新鮮な空気が吸えてよかったです。
六日目はもう車イスなしでも散歩に行けました。我ながら凄い回復ぶりですね。
病院サービスと社会保障
手術後三日目の7月20日、尿カテーテルが取れて大分気分が良くなった時、執刀医の一人が挨拶に来て、がん患者は50%の身体障碍者認定が申請すれば受けられるとか、今後の可能性についてざっと説明し、臨床心理士とソーシャルワーカーそれからアロマサービスを要請したことを伝えてくれました。
その女医さんが去った後、間もなくして臨床心理士が来て、50%の身体障害者認定のことやメンタルケアについて説明してくれました。
続いてアロマサービスの人が来て、ルームアロマを提供してくれました。
その後に病院付属図書館の人が来て、「何か読むものを持って来ましょうか?」と御用聞きに来てくれました。私は何冊も本を持ち込んでいたので、丁重にお断りしましたが、この「姫扱い」にかなり感動してました。
翌日ドレーンが取れて人並みに感じられるようになった時、ソーシャルワーカーが来て、50%の身体障碍者認定の申請用紙やその他のがん患者のための公的支援についてのパンフレットの山を持ってきてくれました。もちろん私にとって重要なことは丁寧に説明してくれました。

がん患者は法律によって申請すれば、自動的に50%の身体障碍者認定を受けられます。その認定があると、様々な保護や特典(交通費・博物館や美術館の入場料割引など)を受けられるのですが、中でも重要なのは、定職に就いている場合の解雇保護(解雇には管轄の統合局の許可が必要になる)や追加有給休暇1週間および税制上では障碍者特別控除があり、税負担が軽減されることです。
因みにがんに限らず病気になった場合は、6週間までは雇用主が給料を100%払うことになっています(Fortzahlung bei Krankheitsfall)。その後は健康保険が傷病手当(Krankengeld)として税込月収の70%(上限は手取り月収の90%)を支給します。支給期間は病欠初日から数えて78週間です。つまり約1年半は働かなくても収入が確保できるわけです。健康保険はどんな雇用形態でも強制保険なので、派遣などでも傷病手当が得られます。
治療費はもちろん健康保険が負担してくれます。自己負担額は公的健康保険の場合は薬1種類あるいはマッサージなどの施術1件につき最高10ユーロまで、年間自己負担総額の上限が年収の2%未満となっています。
ドイツは社会保障が手厚くて助かりますね!
何よりも素晴らしいと思ったのは、自分で調べなくても、病院がこうした情報を提供してくれるということです。
私はそこまではマルテーザー病院に(食事を除いて)大変満足していたのですが、手術後五日目(7月22日)の夜11時過ぎに出産したばかりの女性と新生児が私の病室に運び込まれ、彼女のダンナさんが夜中の1時過ぎまで病室に居たこと、そしてその後に赤ちゃんがぐずりっぱなしだったことで、途中耳栓をもらったにもかかわらず大した助けにはならずに殆ど寝れなかったことで、一挙に気分がダウンしました。
普通は手術患者と新生児を抱えた母親を同室にすることはないとのことですが、その晩はたまたまベッドの空きが他になくてやむを得ずそういうことになったっそうで、病院側の都合で私には大変迷惑なことでした。手術後で休養が必要なのに眠れなかったというばかりでなく、片や出産したばかりの幸せなお母さん、片やがんのために子宮を始めとする女性的な器官をごっそり失った女(妊娠・出産経験なし)の対比があまりにも激しく、普段は考えもしないようなネガティブな方向へ思考が行ってしまい、かなりの情緒不安定に陥りました。
翌日の午後に部屋割りが変更され、母子は別室に移され、代わりに若い手術を控えた患者が同室となりました。二晩はさすがに身体的にも精神的にも耐えられなかったと思いますが、一晩で済んだのでなんとか。。。
それにしてもその母子を運び入れた夜勤看護婦が私に事情説明するなり、断わりを入れるなりしてくれても良かったのではなかろうかと思います。しかしその看護婦さんは私に考慮する様子は全くなく、さも当たり前のように母子を運び込んだのです。耳栓を要求した時も、「こんなことになってごめんなさいね」くらい言っても良さそうなのに、無言で耳栓を持ってきただけでした。後から考えるとかなりひどい対応じゃないかと思いますね。
朝の巡回に来た看護婦さんに苦情を言った時はきちんと説明もしてくれたし、私に対して理解も示してくれ、その日中に何とかすると約束し、その通りに実行してくれたので、模範的な対応だったのですが…
最後の二日間は元気になり過ぎて病院に居ることが苦痛でした。ネットの接続速度が遅く、その上不安定だったのでそのせいでイラつくこともありました。
退院前日にはまた臨床心理士が、私がハーブなどに興味を持っていることを覚えていてくれて、放射線・化学療法以外の補完的ながん治療法に関するパンフレットをわざわざ持ってきてくれました。

まだパラパラっと見ただけですが、有名な砂糖絶ちやゲルソン療法等は「お薦めできない」というスタンス。詳しく論証されてる訳ではないですが、結局のところ臨床検査で効果が確認されてない、つまりエビデンスグレードが低いというのが論拠になっています。
とにかく、がん治療は放射線や化学療法が優先されるけど、それを補うエビデンスグレードの高い療法もあるので、その辺はがん担当医と患者で話し合いすべき、とのことです。私も末期がんで絶望的と言う状況ではないので、ひとまずそういうスタンダードな路線で行くつもりです。
最終診断と治療方針
さて、最終的な診断ですが、「悪性度グレード2の子宮内膜腺がん(Endomeriodes Adenokarzinom)、卵巣転移(metastasierte Ovarien)、プラス原発性腹膜がん(Peritoneales Karzinom)」のステージ3b期(FIGO-Stadium IIIb)と出ました。ただし腹膜がんが原発性か卵巣からの転移かについては病院の腫瘍カンファでもかなり議論があり、100%確実ではない所見だそうです。それにしても最初の「子宮筋腫」から随分遠い所に辿り着いてしまった感じですね。時間の経過とともにどんどん診断が深刻になっていって、本当に心臓に悪いです。腹膜がんは予後不良とも言われているので。。。
手術前に行ったCT検査で、卵巣がんや腹膜がんが見つからなかった(卵巣には嚢胞があることしか分からなかったのです)という事実にも驚きを禁じ得ません。この二つは子宮内膜がんという診断があって手術したからこそ発見されたわけで、それが無かったらいつ見つかったのだろうかと想像するだけでも恐ろしい気がします。
CT検査では他に小さい胆石および軽い肝臓肥大が見つかりました。これも本当に「いつの間に?!」と驚くばかりです。ずっと健康なつもりでいたので、自覚症状が無いのは結構怖いことなのだなと思った次第です。
治療方針は、腹膜がんの診断が出る前までは放射線と化学療法の組み合わせという話だったのですが、腹膜がんのせいで下腹部全体にまだそれとは分からないがん細胞が散らばっている可能性が出てきたので、まずは化学療法のみで様子を見るということになりました。がん治療は手術したマルテーザー病院ではなく、別のがん専門クリニック(Onkologische Praxis)で受けることになります。この分業にはちょっと辟易しますが、少なくとも最初の予約はマルテーザー病院が入れてくれました。
入院中に毎朝血栓症予防のための注射(Clexane)を打たれてましたが、退院後6週間はこの注射が必要とのことで、しかも自分でそれを打つとなるとかなり気が引けます。とりあえず病院で6日分もらいましたけど、ちょっと不安ですね。

こんな状況になっても、ブログ記事を書けるほどには元気なので、未だに自分が「重病患者」であるというのが信じられないくらいです。化学治療が始まったらもしかして実感が湧いてくるのかも知れませんが、そうならないことを祈ります。
余談ですが、私はハウスダストアレルギーで、普段は抗アレルギー剤を飲まないとくしゃみが止まらないのですが、手術後は体がハウスダストなどに構ってられなくなったせいか、抗アレルギー剤なしで全く平気でした。今現在でも平気です。
ドイツにおけるがん患者のための社会保障まとめ
- がん患者は法律によって申請すれば、自動的に50%の身体障碍者認定。
- その認定があると、様々な保護や特典(交通費・博物館や美術館の入場料割引など)を受けられる。中でも重要なのは:
- 定職に就いている場合の解雇保護(解雇には管轄の統合局の許可が必要になる)
- 追加有給休暇1週間
- 税制上では障碍者特別控除があり、税負担が軽減。
- がん治療後のリハビリ
- 必要に応じて家事ヘルパー、在宅介護ヘルパーの派遣
- ソーシャルワーカーによる全般的支援
- 臨床心理士による心のケア
病気になった場合の経済保障:
- 6週間までは雇用主が給料を100%払う(Fortzahlung bei Krankheitsfall)。
- その後は健康保険が傷病手当(Krankengeld)として税込月収の70%(上限は手取り月収の90%)を支給。支給期間は病欠初日から数えて78週間。
- 治療費は健康保険が負担。
- 自己負担額は公的健康保険の場合は薬1種類あるいはマッサージなどの施術1件につき最高10ユーロまで。年間自己負担総額の上限が年収の2%未満。
- 民間健康保険の場合は保険プランによって自己負担額も変動。