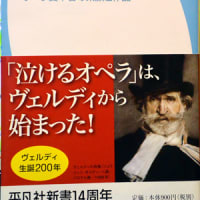北沢方邦『音楽入門』には、「世界の音」が鳴り響いている。
北沢方邦『音楽入門』(2005年11月平凡社刊)は、著者長年の哲学的思考に裏打ちされた、誠にユニークな音楽入門書である。普通の入門書と明確に異なる第1の点は、「音の持つ意味」という主題が全編を貫いていることである。熱帯雨林の笛と太鼓の響きから始まり、日本雅楽、ガムラン音楽、中近東の音楽、そして西洋音楽に至るまで、極めて広い領域をカバーしているにもかかわらず、全体が1つの交響曲のような緊密なまとまりを持っている。
■「出版ニュース」1月上・中旬合併号では、ここに焦点を当てた書評が載せられている。
本書は音楽の意味を再発見するための音楽入門書で、全編を通して音楽を「記号」として扱う点が特徴である。
これは音を単なる音記号の連鎖と考え、その表層的な連なりを美しく流麗に演奏することを推奨しているわけではなく、このようなことは「記号のニヒリズム」として逆に否定し、大切なのは音楽という記号にはその種族の伝統や文化、宇宙観が込められていることを自覚することだと書いている。
『音楽入門』の記述のうちほぼ半分は、非西洋音楽に当てられている。
■「読売新聞」12月11日の吉田直哉氏の書評は、主にこの部分に触れている。これは短文でもあるので全文を紹介したい。
「北沢さんが『野生の思考』の音楽版を書いてくれるといいんだがなあ」と亡き武満徹が言ったのは、彼がチェロとオーケストラのための『オリオンとプレアデス』を作曲した年だから、1984年である。
この一対の星座が展開する「追いかけ、追いつき」は、オーストラリアのアボリジニ、アメリカ先住民ホピなどの重要な天文学的コードであった。日本の神話でもスバルとカラスキはスサノオの「天つ罪」をあらわす、という北沢説に刺激されてこの曲を構想した、と彼は打ち明けてくれた。
それから20年。武満は残念ながら読めないが、彼の待ち望んでいたものがついに世に出た。本書である。熱帯雨林の奥の笛と太鼓から、中国古代の編磬と編鐘による天と地の音の交響。インドのラーガが描く宇宙そのものの情感。誤って未開と呼ばれてきた社会の、宇宙的ひろがりをもった音楽に力点をおいて、小型本ながら内容はずっしりと重い。
この書評の影響力は大きく、『音楽入門』は今でも、書店の民族音楽の棚に置かれていたりする。本書は当然のことながら西洋音楽にも十分な目配りをしていて、私なども日頃聴いている音楽がまったく新しい相貌を持って立ち現れてくるのを実感したものだ。民族(俗)音楽と西洋音楽との関わりについては、
■「音楽現代」2月号の倉林靖氏がいい書評を書いている。
今日のグローバル化社会のなかにあって、あるいは文化と社会の制度を全般的に見直さなければならないという風潮のなかにあって、西洋のいわゆる「クラシック音楽」のありようを相対化するとか、世界のなかの西洋音楽ということで改めて位置付けするということが随所で行われつつあるが、北沢方邦のこの『音楽入門』はそうした方向での格好の入門書であり概説書であり、かつ刺激的な問題提起の書となっている。単に内容が概説的であるというだけではなく、どの部分をとっても深い思索と知識に裏打ちされており、鋭く啓発的な問いかけを行っているのだ。こうした内容は、北沢氏が世界の民族(俗)音楽や邦楽にも、クラシック音楽にも、どちらにも等しく幅広い知識を持っており、かつ構造主義哲学や文化社会学などの面においても旺盛な著作活動を行ってきたひとだからこそ提出しうるものなのである。
……
民族(俗)音楽のなかにある天・地の宇宙論などの解説も新たに知ることが多く大変興味深いし、また西洋クラシック音楽の歴史を「人間の音楽」として思想的に、あるいは社会的に論評していくくだりは非常に啓発的で、新たな発見を促してくれる。
……
こうした体裁の本にもかかわらずどこでも極めて真摯に考察を進めていることは尊敬に値する。これから「音楽」を考える人には誰でも読んでほしい、優れた「思索」の書である。
『音楽入門』には「世界の音」が鳴り響いている。帯の文句ではないけれど、本書を読んで、音楽発見の旅に出かけよう!
2006年6月15日 j-mosa