先週末は奈良、今日は常磐線のいずれも日帰り旅。今は特急ひたちの車内からです(しかし、車中で最後まで書き終わらなかったので後でアップしています)。新幹線やこういう特急の車内は、ブログ記事を作成するのにほどよい時間・空間ですね。モバイルPCを購入しまして、週末だけですが連れ出して活用しています。軽くて電池持ちもいいし、なかなかよいですね。
さて、そういうわけで特急乗車中に何が書けるか。そうですね、3月21日、お彼岸の日に奈良・三輪で見た夕日の話でも。
現在私の興味が向かっている所は、大きく分けると二つかな?一つは、神社や古墳の立地している方角などについて。もう一つは、詳しくは書けませんが、大学通信教育の卒論のための題材についてです。
日本の神様は嫌い、神社に参拝などしたくない、初詣もできればしたくない、というのが従来の私でしたが、ここ数年、がらっと変わってきました。皇国史観とか天皇陛下万歳につながるような思想は取り除いた部分で、日本の神社の起源や神話について、もっと知りたいと考えるようになりました。神話は全くでたらめと頭から決めてかかるのではなく、その中に本当のことも含まれていると感じられるようになってきました。その本当のことをできるだけ抽出したい、と思うようになりました。
出雲が大好きな私は、三輪山についても特に興味があります。その周辺(桜井市周辺)に、卑弥呼の邪馬台国ではないかとされる纏向遺跡や、箸墓古墳、その他たくさんの古墳・遺跡があります。
その中で、私がいろいろな本を読んでいたところ、崇神天皇の宮・磯城瑞籬宮(しきのみずがきのみや)があったと推定されている場所が、桜井市金屋のあたりで、そこからは、春分・秋分の日には、ちょうど二上山の二つの山の谷間に太陽が沈む、という情報を知りました。
磯城瑞籬宮のあったとされる場所は、桜井市金屋の、現在は天理教会のある所らしいのですが、また、一方で、その近くの現在の志貴御懸坐(しきのみあがたにます)神社の付近であるといわれており、実際に行ってみると、そのような石碑が建っていました。
詳しくは、後日整理してお届けします。今日は、あと30分でできること、ということで・・・
そういえば、さっきちらっと窓の外を見たら、右手に筑波山がきれいに見えました。どのへんかなと思ってGPSで見ていたら、高浜という駅を通過したあたりかな?そして、地図では近くに二子塚古墳とか舟塚山古墳があるらしい・・・?
なんかですね、この方向から見ると、筑波山が二上山に似てるな??と思えたんですよね。
奈良から来た人だと、そう思うんじゃないかなと、先日奈良に行ってきた私は思いました。
今日の筑波山↓

話が脱線しましたが、戻って、私がお彼岸の日に奈良へ日帰りで行ったのは、その、崇神天皇の宮跡から、二上山の谷間に沈む夕日を見たかったからなのです。二上山は、雄岳と雌岳という二つのピークがあるのです。その間に沈むということです。
一応、天文のシミュレーションソフト・ステラナビゲータで調べてみても、やはり、その付近から見ると、二上山の谷間に太陽が沈むらしいので、これは行きたい!と、お彼岸の日を狙い、お天気はどうだろうかと気にしながら計画を立てていました。
21日なら、晴れそうだ、と予想できたので、決行しました。
ただし、一度レンタサイクルで下見をして、自転車を返した後に夕方またその場所に徒歩で行って見ようと考えていたのですが、その計画は疲労などから頓挫しました。
それに、意外とその金屋の場所は見晴らしがいいとはいえなかったのです。
それで、金屋ではないし、たぶん二上山の谷間からずれるけど、三輪山・大神神社近くの展望台、「大美和の杜」からでもいいか、と妥協し、そこにも行ったのですが、結果として、さらに妥協して、やはりもうちょっと早く帰途に就きたい、と考え、三輪の駅に戻り、電車が来る寸前に、駅から撮ることができた、その写真がこれです!

三輪駅発18時05分、日没もステラナビゲータの計算でだいたいそのくらいになるということで、もしや三輪の駅から日没が見えるんではないかと頭をよぎり、電車が来る前にホームの連絡橋の上に上ってみたら、ちょうど二上山に沈むところだったのです。
ただし、三輪駅からでは二上山の谷間には沈みませんでした。雄岳の頂上近くに沈みましたね。 お天気は絶好でした。ちょっとカメラの選択を誤りました。これはスマホカメラによるものです。
山影に大きな太陽が次第に吸い込まれていく様子は、ただならぬ光景でした。やはり、何か感じるものがあります。古代の人もそうだったのでしょう。
大神神社の巨大な鳥居(道路をまたぐ鳥居では日本最大とか)をかすめて沈もうとする夕日。三輪駅に向かう途中、大神神社二の鳥居を出てJR桜井線の線路横から撮ったもの。

お天気に恵まれて、疲れはしましたが、心は満たされて東京に戻って来ました。←これは21日の話です。今日も、疲れましたが、収穫を得て、心豊かに東京に戻ってきました。
詳しくは後日。
さて、お花見しないと、満開になってしまった東京は、散ってしまいますね。ではまた。
☆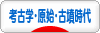 にほんブログ村
にほんブログ村
さて、そういうわけで特急乗車中に何が書けるか。そうですね、3月21日、お彼岸の日に奈良・三輪で見た夕日の話でも。
現在私の興味が向かっている所は、大きく分けると二つかな?一つは、神社や古墳の立地している方角などについて。もう一つは、詳しくは書けませんが、大学通信教育の卒論のための題材についてです。
日本の神様は嫌い、神社に参拝などしたくない、初詣もできればしたくない、というのが従来の私でしたが、ここ数年、がらっと変わってきました。皇国史観とか天皇陛下万歳につながるような思想は取り除いた部分で、日本の神社の起源や神話について、もっと知りたいと考えるようになりました。神話は全くでたらめと頭から決めてかかるのではなく、その中に本当のことも含まれていると感じられるようになってきました。その本当のことをできるだけ抽出したい、と思うようになりました。
出雲が大好きな私は、三輪山についても特に興味があります。その周辺(桜井市周辺)に、卑弥呼の邪馬台国ではないかとされる纏向遺跡や、箸墓古墳、その他たくさんの古墳・遺跡があります。
その中で、私がいろいろな本を読んでいたところ、崇神天皇の宮・磯城瑞籬宮(しきのみずがきのみや)があったと推定されている場所が、桜井市金屋のあたりで、そこからは、春分・秋分の日には、ちょうど二上山の二つの山の谷間に太陽が沈む、という情報を知りました。
磯城瑞籬宮のあったとされる場所は、桜井市金屋の、現在は天理教会のある所らしいのですが、また、一方で、その近くの現在の志貴御懸坐(しきのみあがたにます)神社の付近であるといわれており、実際に行ってみると、そのような石碑が建っていました。
詳しくは、後日整理してお届けします。今日は、あと30分でできること、ということで・・・
そういえば、さっきちらっと窓の外を見たら、右手に筑波山がきれいに見えました。どのへんかなと思ってGPSで見ていたら、高浜という駅を通過したあたりかな?そして、地図では近くに二子塚古墳とか舟塚山古墳があるらしい・・・?
なんかですね、この方向から見ると、筑波山が二上山に似てるな??と思えたんですよね。
奈良から来た人だと、そう思うんじゃないかなと、先日奈良に行ってきた私は思いました。
今日の筑波山↓

話が脱線しましたが、戻って、私がお彼岸の日に奈良へ日帰りで行ったのは、その、崇神天皇の宮跡から、二上山の谷間に沈む夕日を見たかったからなのです。二上山は、雄岳と雌岳という二つのピークがあるのです。その間に沈むということです。
一応、天文のシミュレーションソフト・ステラナビゲータで調べてみても、やはり、その付近から見ると、二上山の谷間に太陽が沈むらしいので、これは行きたい!と、お彼岸の日を狙い、お天気はどうだろうかと気にしながら計画を立てていました。
21日なら、晴れそうだ、と予想できたので、決行しました。
ただし、一度レンタサイクルで下見をして、自転車を返した後に夕方またその場所に徒歩で行って見ようと考えていたのですが、その計画は疲労などから頓挫しました。
それに、意外とその金屋の場所は見晴らしがいいとはいえなかったのです。
それで、金屋ではないし、たぶん二上山の谷間からずれるけど、三輪山・大神神社近くの展望台、「大美和の杜」からでもいいか、と妥協し、そこにも行ったのですが、結果として、さらに妥協して、やはりもうちょっと早く帰途に就きたい、と考え、三輪の駅に戻り、電車が来る寸前に、駅から撮ることができた、その写真がこれです!

三輪駅発18時05分、日没もステラナビゲータの計算でだいたいそのくらいになるということで、もしや三輪の駅から日没が見えるんではないかと頭をよぎり、電車が来る前にホームの連絡橋の上に上ってみたら、ちょうど二上山に沈むところだったのです。
ただし、三輪駅からでは二上山の谷間には沈みませんでした。雄岳の頂上近くに沈みましたね。 お天気は絶好でした。ちょっとカメラの選択を誤りました。これはスマホカメラによるものです。
山影に大きな太陽が次第に吸い込まれていく様子は、ただならぬ光景でした。やはり、何か感じるものがあります。古代の人もそうだったのでしょう。
大神神社の巨大な鳥居(道路をまたぐ鳥居では日本最大とか)をかすめて沈もうとする夕日。三輪駅に向かう途中、大神神社二の鳥居を出てJR桜井線の線路横から撮ったもの。

お天気に恵まれて、疲れはしましたが、心は満たされて東京に戻って来ました。←これは21日の話です。今日も、疲れましたが、収穫を得て、心豊かに東京に戻ってきました。
詳しくは後日。
さて、お花見しないと、満開になってしまった東京は、散ってしまいますね。ではまた。
☆



















 2005年
2005年 2013年
2013年