平成26年度も今日で終わりですね。
明日から新年度スタートです。
先日卒業した担任生徒のうちの何人かも、新入社員として明日が第一歩の日となりますし、前の学校で担任した学年も、専門学校や短大に進んだ人たちは、この春就職でしょう。
明日が入社式で、今日はドキドキの夜かもしれません。
東京は桜が満開です。入学式にはピークが過ぎてしまいますが、入社式にはちょうどいいタイミングですね。
今日は早めに職場を退出して、歩道を歩きながら、学校の桜を、満月近い月と一緒に撮りました。向こうから歩いて来る人も多かったので、スマホで歩きながらパシャッと1枚だけでしたが、桜のピンクが幻想的に写りました。でも月が見た目より小さくしか映りませんでしたね。合成しないと大きくは見えないかな。

明日、それぞれの場所で新しいスタートを切る人たちに、今夜の桜と月の写真を贈ります。
私の社会人のスタートは、バブル絶頂期だったのですが、最初に役人として就職したときは、なんだか希望と異なる意外な職場だったので、初日から辞めたいような気分になりました(笑)(景気もよかったので別の仕事に乗り換えるのも簡単な気がした)。しかし、「入社式」の中で、「継続は力なり」という言葉を聞いて、そうなのかな・・・と思って、がんばってみることにしました。
以後、17年働いて、突然教員に転職しました。
二度目の「入社式」で心に残ったのは、「実り多い人生を」という言葉でした。
今は、教員としてはスタートが遅くても、実り多い人生にすべく、前向きに職業生活を送っています。
この3月卒業した担任生徒には、これからの人生で理不尽なことに遭遇しても逃げるな。と最後に伝えました。悪は勝手にコケるから、自分が悪くないんだったら、自分の方から逃げるな、と。
戦国武将・真田幸村の兵は、敗れはしましたが、「日本一の兵(つわもの)」とたたえられるほど勇猛で、大坂夏の陣でも、敵に背を向けるように倒れて死んでいた者はおらず、みんな前を向いて倒れていたということです。
倒れるときは前を向いて倒れろ。逃げないでほしい、と私は願います。
一生懸命やっていれば、必ずいいことがあります。たくさんの困難なことに遭遇するには違いないでしょうが、逃げずに乗り越えていってください。試練を乗り越えるたびに、成長している自分に気づくはずです。
自分の選んだ道で、がんばれ!応援しています。
☆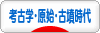 にほんブログ村
にほんブログ村
明日から新年度スタートです。
先日卒業した担任生徒のうちの何人かも、新入社員として明日が第一歩の日となりますし、前の学校で担任した学年も、専門学校や短大に進んだ人たちは、この春就職でしょう。
明日が入社式で、今日はドキドキの夜かもしれません。
東京は桜が満開です。入学式にはピークが過ぎてしまいますが、入社式にはちょうどいいタイミングですね。
今日は早めに職場を退出して、歩道を歩きながら、学校の桜を、満月近い月と一緒に撮りました。向こうから歩いて来る人も多かったので、スマホで歩きながらパシャッと1枚だけでしたが、桜のピンクが幻想的に写りました。でも月が見た目より小さくしか映りませんでしたね。合成しないと大きくは見えないかな。

明日、それぞれの場所で新しいスタートを切る人たちに、今夜の桜と月の写真を贈ります。
私の社会人のスタートは、バブル絶頂期だったのですが、最初に役人として就職したときは、なんだか希望と異なる意外な職場だったので、初日から辞めたいような気分になりました(笑)(景気もよかったので別の仕事に乗り換えるのも簡単な気がした)。しかし、「入社式」の中で、「継続は力なり」という言葉を聞いて、そうなのかな・・・と思って、がんばってみることにしました。
以後、17年働いて、突然教員に転職しました。
二度目の「入社式」で心に残ったのは、「実り多い人生を」という言葉でした。
今は、教員としてはスタートが遅くても、実り多い人生にすべく、前向きに職業生活を送っています。
この3月卒業した担任生徒には、これからの人生で理不尽なことに遭遇しても逃げるな。と最後に伝えました。悪は勝手にコケるから、自分が悪くないんだったら、自分の方から逃げるな、と。
戦国武将・真田幸村の兵は、敗れはしましたが、「日本一の兵(つわもの)」とたたえられるほど勇猛で、大坂夏の陣でも、敵に背を向けるように倒れて死んでいた者はおらず、みんな前を向いて倒れていたということです。
倒れるときは前を向いて倒れろ。逃げないでほしい、と私は願います。
一生懸命やっていれば、必ずいいことがあります。たくさんの困難なことに遭遇するには違いないでしょうが、逃げずに乗り越えていってください。試練を乗り越えるたびに、成長している自分に気づくはずです。
自分の選んだ道で、がんばれ!応援しています。
☆













