前回の続きで、去年の紅葉の季節に吉野・長谷寺を訪ねた時の話題です。
2016年から運行を開始した、近鉄の「青の交響曲(シンフォニー)」という名前の観光特急列車があります。大阪阿倍野橋を出て橿原神宮前を通り、吉野までのルートです。1日に2往復しかないのですが、時間が合うからもしかして空席ないかなと窓口で当日尋ねたのですが、空いていませんでした。まあそうですよね。
橿原神宮前駅のホームでその「青の交響曲」に遭遇しました。車内にはすてきな明かりが灯り、何やらおいしそうなものを食べている乗客たち。ホームでそれを見ていたお客さんが「喫茶店やな。」とか話していました。

吉野駅に着いた時にも、ホームにその列車はありました。いい雰囲気ですね。大阪から吉野に遊びに来る人には特にいいかもしれません。
吉野駅は近鉄吉野線の終点になるわけですが、私は、飛鳥までは電車で来たことはあっても、その先は未知の領域で、車中、とてもわくわくしました。寂しいくらいの里山にどんどん分け入っていく感覚・・・京都や奈良といった都から、こんな遠くまで、天武天皇、持統天皇、藤原道長、源義経、後醍醐天皇、豊臣秀吉・・・まだまだいますがおびただしい歴史上の人物が、訪れ、滞在してきた場所なんだなあ・・・と、不思議な気持ちになりました。秋でもあるし、寂しい風景も途中に見られますが、昔から多くの有名無名の人々が往来した地域であり、歴史の積み重なりを感じられるような空気が漂っている気がしました。
「吉野駅」に降り立ってみて、改めて「吉野」という地名の風雅さを感じました。
「よき人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よよき人よく見つ」
今書きながら、こんな歌があったよな、と心に浮かびましたが、これは天武天皇が吉野宮に来た時に作った歌だそうですね。『万葉集』の巻1(27)にあるようです。
「昔のりっぱな人が、よき所としてよく見て『よし(の)』と名付けたこの吉野。りっぱな人である君たちもこの吉野をよく見るがいい。昔のりっぱな人もよく見たことだよ。」
吉野は、紅葉が散り始めていて、平日だったので人も多くなく、のんびりと、風情を楽しむことができました。途中でおそばを食べたりしましたが、やや混雑してました。桜の季節や休日はもっとごった返して大変なんでしょうね。
金峯山寺については前回も少し書きましたが、巨大な蔵王権現さんの「特別御開帳」をやっていました。仁王門は国宝だそうですが、修理していました。この仁王門の修理勧進のための御開帳でした。オリンピックがあるから化粧直しなのか、奈良などのかなりのお寺では、改修工事をやっています。どこもかしこも・・・という感じ。長谷寺もそうでしたし、東大寺も少し前に行ったらそうでした。
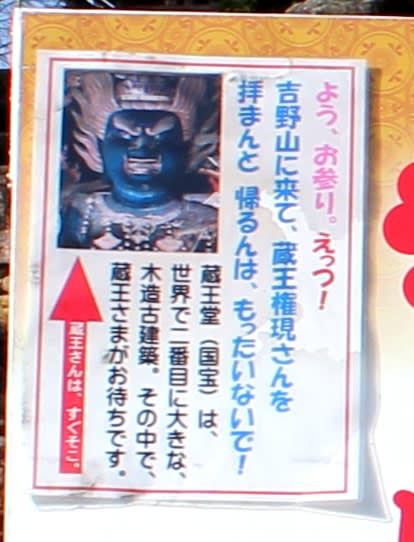
蔵王権現の御開帳は、料金がちょっと高めでしたが、お守りの木札と「特製エコバッグ」をいただきました。何しろ蔵王権現さんは、ものすごく巨大です。写真は不可でしたのでありませんが、像の前の畳スペースに座って、見上げるようにしてしばらく拝観させていただきました。濃い青の、憤怒の表情で迫力があります。こんな山の上にこんな大きなものが・・・と感銘を受けます。一見の価値はあります。
また、その権現さんの足下に障子で仕切った小さいスペースがいくつかあって、お寺の方に誘導してもらってその中に一人ずつ入ってお祈りするような場所がありました。名前を忘れてしまったのですが、面白い名前でした。懺悔の部屋みたいなもののようでした。権現さんに心を打ち明けて祈る場所です。お金は別料金だったのか、よくわかりませんでした。

「南朝皇居 吉水神社」という看板に導かれて、そちらにも立ち寄りました。この「皇居」というのも正確なのかわかりませんし、境内に音声がスピーカーで流れて有料エリアにお客さんを呼び込むような感じなどが違和感ありました。宮司さんなんでしょうか、気さくな感じでご自分でお札などを売りさばいたり、入場料を受け取ったりしていました。
中には義経や秀吉などのゆかりの品が展示されていました。

室内から遠くに望む金峯山寺が、とても美しく見えて、他のお客さんも声をあげていました。
春には「一目千本」の桜を見渡せる場所がありました。
吉水神社前の坂の紅葉もきれいで(以前の記事にも掲載)、そこの途中の狛犬さんも、一眼レフ効果でなんとなくよさげに撮れたので載せておきます。

吉野はまだまだ後醍醐天皇ゆかりの寺など奥深くにたくさんあるようでしたが、我々はほんの少し歩いただけで戻って来ました。いつか桜の季節にでも宿泊するなどしてゆっくり来ようと思います。
戻る途中で、「静亭」という、義経の彼女の静御前にちなむお店に入りました。静御前が舞を舞ったという勝手神社の前にあります。
http://www.yosino-sizukatei.sakura.ne.jp/index.html
ここで、吉野といったら「くず」だよな、と、くずの甘味をいただくことにしました。

確か、くずしることくず餅のセットだったと思います。もちろんおいしかったですよ。
気候も穏やかで、静かで、秋の吉野の空気をゆっくり味わうことができました。良き、吉野の旅でした。
とりあえず今日はこんなところで。次は、長谷寺のことでも書きましょう。
2016年から運行を開始した、近鉄の「青の交響曲(シンフォニー)」という名前の観光特急列車があります。大阪阿倍野橋を出て橿原神宮前を通り、吉野までのルートです。1日に2往復しかないのですが、時間が合うからもしかして空席ないかなと窓口で当日尋ねたのですが、空いていませんでした。まあそうですよね。
橿原神宮前駅のホームでその「青の交響曲」に遭遇しました。車内にはすてきな明かりが灯り、何やらおいしそうなものを食べている乗客たち。ホームでそれを見ていたお客さんが「喫茶店やな。」とか話していました。

吉野駅に着いた時にも、ホームにその列車はありました。いい雰囲気ですね。大阪から吉野に遊びに来る人には特にいいかもしれません。
吉野駅は近鉄吉野線の終点になるわけですが、私は、飛鳥までは電車で来たことはあっても、その先は未知の領域で、車中、とてもわくわくしました。寂しいくらいの里山にどんどん分け入っていく感覚・・・京都や奈良といった都から、こんな遠くまで、天武天皇、持統天皇、藤原道長、源義経、後醍醐天皇、豊臣秀吉・・・まだまだいますがおびただしい歴史上の人物が、訪れ、滞在してきた場所なんだなあ・・・と、不思議な気持ちになりました。秋でもあるし、寂しい風景も途中に見られますが、昔から多くの有名無名の人々が往来した地域であり、歴史の積み重なりを感じられるような空気が漂っている気がしました。
「吉野駅」に降り立ってみて、改めて「吉野」という地名の風雅さを感じました。
「よき人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よよき人よく見つ」
今書きながら、こんな歌があったよな、と心に浮かびましたが、これは天武天皇が吉野宮に来た時に作った歌だそうですね。『万葉集』の巻1(27)にあるようです。
「昔のりっぱな人が、よき所としてよく見て『よし(の)』と名付けたこの吉野。りっぱな人である君たちもこの吉野をよく見るがいい。昔のりっぱな人もよく見たことだよ。」
吉野は、紅葉が散り始めていて、平日だったので人も多くなく、のんびりと、風情を楽しむことができました。途中でおそばを食べたりしましたが、やや混雑してました。桜の季節や休日はもっとごった返して大変なんでしょうね。
金峯山寺については前回も少し書きましたが、巨大な蔵王権現さんの「特別御開帳」をやっていました。仁王門は国宝だそうですが、修理していました。この仁王門の修理勧進のための御開帳でした。オリンピックがあるから化粧直しなのか、奈良などのかなりのお寺では、改修工事をやっています。どこもかしこも・・・という感じ。長谷寺もそうでしたし、東大寺も少し前に行ったらそうでした。
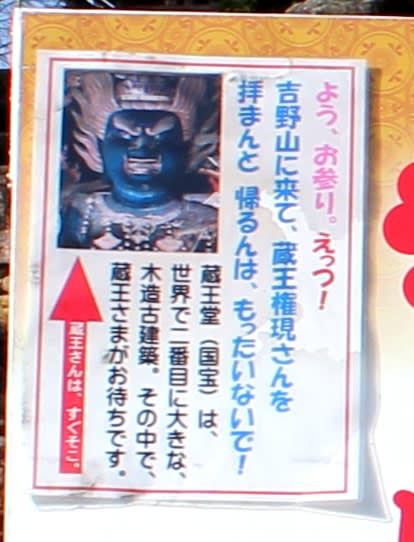
蔵王権現の御開帳は、料金がちょっと高めでしたが、お守りの木札と「特製エコバッグ」をいただきました。何しろ蔵王権現さんは、ものすごく巨大です。写真は不可でしたのでありませんが、像の前の畳スペースに座って、見上げるようにしてしばらく拝観させていただきました。濃い青の、憤怒の表情で迫力があります。こんな山の上にこんな大きなものが・・・と感銘を受けます。一見の価値はあります。
また、その権現さんの足下に障子で仕切った小さいスペースがいくつかあって、お寺の方に誘導してもらってその中に一人ずつ入ってお祈りするような場所がありました。名前を忘れてしまったのですが、面白い名前でした。懺悔の部屋みたいなもののようでした。権現さんに心を打ち明けて祈る場所です。お金は別料金だったのか、よくわかりませんでした。

「南朝皇居 吉水神社」という看板に導かれて、そちらにも立ち寄りました。この「皇居」というのも正確なのかわかりませんし、境内に音声がスピーカーで流れて有料エリアにお客さんを呼び込むような感じなどが違和感ありました。宮司さんなんでしょうか、気さくな感じでご自分でお札などを売りさばいたり、入場料を受け取ったりしていました。
中には義経や秀吉などのゆかりの品が展示されていました。

室内から遠くに望む金峯山寺が、とても美しく見えて、他のお客さんも声をあげていました。
春には「一目千本」の桜を見渡せる場所がありました。
吉水神社前の坂の紅葉もきれいで(以前の記事にも掲載)、そこの途中の狛犬さんも、一眼レフ効果でなんとなくよさげに撮れたので載せておきます。

吉野はまだまだ後醍醐天皇ゆかりの寺など奥深くにたくさんあるようでしたが、我々はほんの少し歩いただけで戻って来ました。いつか桜の季節にでも宿泊するなどしてゆっくり来ようと思います。
戻る途中で、「静亭」という、義経の彼女の静御前にちなむお店に入りました。静御前が舞を舞ったという勝手神社の前にあります。
http://www.yosino-sizukatei.sakura.ne.jp/index.html
ここで、吉野といったら「くず」だよな、と、くずの甘味をいただくことにしました。

確か、くずしることくず餅のセットだったと思います。もちろんおいしかったですよ。
気候も穏やかで、静かで、秋の吉野の空気をゆっくり味わうことができました。良き、吉野の旅でした。
とりあえず今日はこんなところで。次は、長谷寺のことでも書きましょう。





















 ボランティアの方がいらっしゃって、説明してくださいました。その住宅跡から見ると、さっきの「さかい利晶の杜」の屋根は、茶釜に見えるのだということを教えてもらいました。
ボランティアの方がいらっしゃって、説明してくださいました。その住宅跡から見ると、さっきの「さかい利晶の杜」の屋根は、茶釜に見えるのだということを教えてもらいました。














