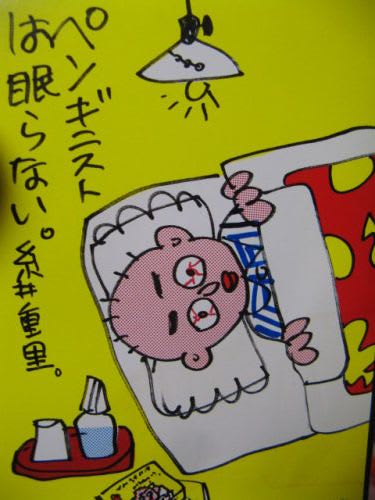「エスノ」という用語。それを盛んに使い出したのは1982年だった、ということを、この休みに雑誌をめくりつつ想い出す。
既に、トーキングヘッズの「リメイン・ライト」(1980年)も、そのプロトタイプであったイーノとの「マイ・ライフ・イン・ザ・ブッシュ・オブ・ゴースツ」(1981年・使用した音源の個人情報・権利関係で発表遅れてしまい、前後逆発表)という歴史的2枚は発売後のこと。

【トーキングヘッズのベーシスト、ティナ・ウェイマス】
その源流にはパンク・スカ等一連の事件があり、エスニック・他民族の音楽を取り込み融合させることは、とうの昔に始まっていたのであった。
ジョン・ライドンの「ロックで無ければ何でもいい」という発言に表現されている通り、多様な音の融合が展開されていた。
クラッシュ、というと、つい「怒れる・体制側への抵抗」的イメージに言われるが、実際の作品にはレゲエ、ダブ、カリブの音が入り、曲によってさまざまな色調を出していた。
(それは、相当後にポール・ウェラーが結成したスタイルカウンシルと、自分の中ではかぶる部分がある。)

■アンディ・パートリッジ 「Shore Leave Ornithology (Another 1950)」(From「Take Away」1980)■

1982年「エスノ」と盛んに言葉として出したのは音楽雑誌であり・おっしゃれーと思い込んでいたスノッブたちが読むようなサブカルチャー雑誌だったり。。。
(今、みうらじゅんさんが「サブカル」という使い方をしているものは、元々在った「サブカルチャー」とは意味合いが異なり、かなりズレた概念である。)

【アンディ・パートリッジ】
後に筑紫哲也が「新人類」とユビ差した、中森明夫、野々村文宏といった類の連中が使うようなイメージが「エスノ」という言葉には、どうも付きまとっていた。
要は、音楽そのものよりも「エスノ」と書いたり・言ったりしたかったのだろう、という連中の顔が浮かんでしまう。
(湯村輝彦さんなどが言うならば、しっくり来るけれど。)

【「へたうま」時代の湯村さんイラスト】
確かに1982年という年は、それまでつちかってきたモノたちが不思議な融合をし、ポップな形で浮かび上がった年だった。
ニューウェイヴ花盛りで、素晴らしいアルバムだらけの年だった。
和歌山県のみかんだらけの道みたいに、オレンジ色に染まり、そこいらじゅうにジューシーな果実が、難なく手の届くところにあるような幻覚じみた年。

音そのものがそれまでにはあり得ない、そんな革新的音楽が産まれ続ける、といった過激な場所からポップな地点へ。
それらは電子楽器そのものの発展を無視は出来ず、というか同時並行的に進む。
その後、1983年のアート・オブ・ノイズを経由して、機械音で埋め尽くす方面と、その外側へ「NO」と移動する方向とに分岐していく。
そうして(自分の体感としては)1986年に、それらは全て終わってしまう。
何がどうのこうの、という差異無き後の世界が、自分にとっての1987年以降となる。
***
「ボーダーレス」という用語が盛んに使われたのは、80年代終盤だったと思う。
「まっさか~、そんなものは架空の未来のこと」と思っていたFM放送の多局化は、あっさりと1988年「J-WAVE」の登場を契機に実現してしまう。
1989年には「ワールドミュージック」となる、曖昧模糊と「なんでもアリ」な霧の真っ只中、つまらない音楽ばかりが「中心なる場所」で紹介されていた。
上記「エスノ」が、原始的な音そのものの回路を探る、果敢なるミュージシャンたちの格闘の断片として、キズ跡をのちの時代に残した一方で、「ボーダーレス」も「ワールドミュージック」も、主体的な関わりの中で産まれたものではなかった。
『周囲が私を攻めてくる(かのような状況)・体内に侵入してくる(かのような状況)』(それは1986年自分が見た幻覚に似て)という受動的な様相のつまらない時代を表現していた。
それは、その後、グローバル時代と呼ばれたものと同一だが、「ボーダーレス」と言えるだけ、まだマシだったかもしれない。
何せ、まだ「ボーダー」=境目がわずかでも存在しえたから、「ボーダーレス」と言えたのだから。
80年代の終わりにアンビエントの新しい解釈と、それまで在った構造を変更した事態は、ここでは別として。