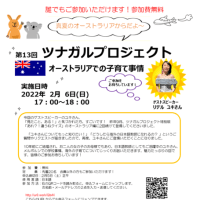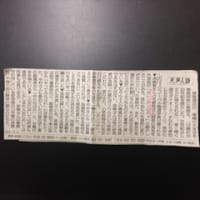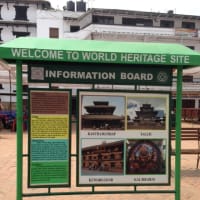去る9月22日(日) 「J-shine創立10周年フォーラム in 中部」が金城学院大学で開催され、200人超える現場の先生たちが集まりました。
当日は午後から私もワークショップ「これだけは使いたい Classroom English」を大学の外国人の先生と一緒に担当させていただき、計100名ほどの参加者と楽しいひとときを過ごしました。
'J-shine'というのは2003年に「小学校での英語教育の普及・発展を支援する」という趣旨のもと作られた「特定非営利活動法人」で、正式名称を「NPO小学校英語指導者認定協議会」といいます。
私が児童英語講師を養成する「キッズイングリッシュプログラム(早期英語教育コース)」を担当する金城学院大学は昨年J-shineの認定校となりました。今回そのため、会場として選ばれました。
小学校英語は2002年に「総合的な学習の時間」の中でスタートしましたが、昨年からは5-6年全員が「外国語活動」として英語を学んでいます。但し、算数や国語のような「教科」ではなく、道徳のような「領域」としての科目にはいっています。
今回のフォーラムはこの「領域」にある英語が近い将来「教科」になるかどうか?なるとしたらどのように?ということに焦点があてられ、活発なディスカッションがなされました。
私個人としては、小学校英語は、
1.まずは「音」から学び、
2.英語でコミュニケーションをする楽しさを体感してほしい。
そのためには、やはりスキルを持った英語の「専科教員」が教えてほしいと思っています。
現在はクラス担任が中心となって、外国人のALTがはいったりしてティームティーチングを行っていますが、担任の先生の英語に対する負担は計り知れません。また教え方も様々、トレーニングも不十分です。
私たちは人間ですから、どうしても自分の経験がもとになって「教えられた」ように「教えて」しまう傾向がある。そうなると小学校英語が、中学英語の前倒しのように「読み書き」からはいる危険性があると思うのです。
そういった危険性を排除するためには「体育の先生」や「音楽の先生」のように専科の「英語の先生」を小学校に配置していただき、フォニックスを中心に音から楽しく学習をし、思春期である「9歳の壁」の前にどんどん人と話す「コミュニケーションの楽しさ」を英語で味わってほしいと思います。
これからまだまだ誰が教えるのか?どうやって教えるのか?中学との連携はどうなるのか?評価方法はどうするのか?など議論されて決めていかなくてはいけないことが山ほどありますが、それでも、好奇心が旺盛な小学生たちが将来英語でほかの国の人たちと話しができるよう、小学校から一貫したカリキュラムのもとに英語をスタートさせてほしいと切に願います

左から、的馬、mpi竹村社長、J-shine理事 松香洋子先生、金城学院大学 馬場先生と、フォーラム終わってホット一息。
当日は午後から私もワークショップ「これだけは使いたい Classroom English」を大学の外国人の先生と一緒に担当させていただき、計100名ほどの参加者と楽しいひとときを過ごしました。
'J-shine'というのは2003年に「小学校での英語教育の普及・発展を支援する」という趣旨のもと作られた「特定非営利活動法人」で、正式名称を「NPO小学校英語指導者認定協議会」といいます。
私が児童英語講師を養成する「キッズイングリッシュプログラム(早期英語教育コース)」を担当する金城学院大学は昨年J-shineの認定校となりました。今回そのため、会場として選ばれました。
小学校英語は2002年に「総合的な学習の時間」の中でスタートしましたが、昨年からは5-6年全員が「外国語活動」として英語を学んでいます。但し、算数や国語のような「教科」ではなく、道徳のような「領域」としての科目にはいっています。
今回のフォーラムはこの「領域」にある英語が近い将来「教科」になるかどうか?なるとしたらどのように?ということに焦点があてられ、活発なディスカッションがなされました。
私個人としては、小学校英語は、
1.まずは「音」から学び、
2.英語でコミュニケーションをする楽しさを体感してほしい。
そのためには、やはりスキルを持った英語の「専科教員」が教えてほしいと思っています。
現在はクラス担任が中心となって、外国人のALTがはいったりしてティームティーチングを行っていますが、担任の先生の英語に対する負担は計り知れません。また教え方も様々、トレーニングも不十分です。
私たちは人間ですから、どうしても自分の経験がもとになって「教えられた」ように「教えて」しまう傾向がある。そうなると小学校英語が、中学英語の前倒しのように「読み書き」からはいる危険性があると思うのです。
そういった危険性を排除するためには「体育の先生」や「音楽の先生」のように専科の「英語の先生」を小学校に配置していただき、フォニックスを中心に音から楽しく学習をし、思春期である「9歳の壁」の前にどんどん人と話す「コミュニケーションの楽しさ」を英語で味わってほしいと思います。
これからまだまだ誰が教えるのか?どうやって教えるのか?中学との連携はどうなるのか?評価方法はどうするのか?など議論されて決めていかなくてはいけないことが山ほどありますが、それでも、好奇心が旺盛な小学生たちが将来英語でほかの国の人たちと話しができるよう、小学校から一貫したカリキュラムのもとに英語をスタートさせてほしいと切に願います


左から、的馬、mpi竹村社長、J-shine理事 松香洋子先生、金城学院大学 馬場先生と、フォーラム終わってホット一息。