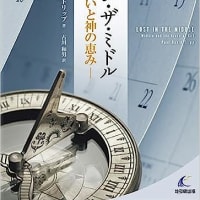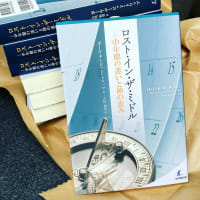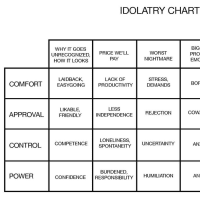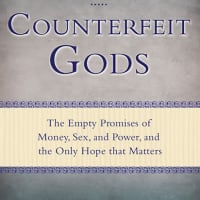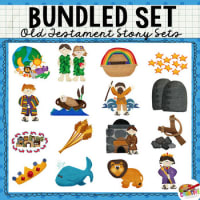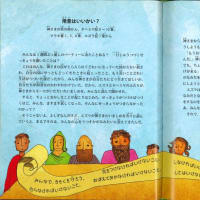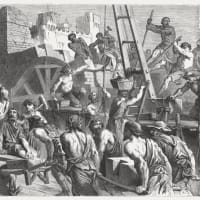2017/10/15 使徒の働き九章32-43節「癒やしの先にあったもの」
新しい翻訳聖書は11月から試します。招詞、交読文、聖書箇所で前に映し出して感想を伺います。読み比べるとやはり違いも多くて、今日の箇所では主な地名も変わっています。
1.ルダとヨッパ(リダとヤッフォ)での二つの奇蹟
前回31節で大きな段落が一区切りしました。エルサレム教会の発展と、ユダヤ当局からの迫害は、新しくサマリヤへの宣教に展開し、迫害者の先鋭だったサウロの回心という思いもかけない事件になりました。こうして教会は前進し続けた。そうまとめた上で、この32節からは、久しぶりにペテロが登場して、大きな新しい段落が始まっていきます。勿論それをペテロはまだ知りません。一〇章から異邦人のキリスト者が次々に生まれていく新しい展開をまだ知らない中、二つの出来事があった。いわば、今日の箇所は、導入、「枕」です。
32節の
「あらゆる所」
はエルサレム周辺をあちこちまんべんなく、という意味です。そして彼はルダに来ました。エルサレムから40kmほど北西の町です。そこの聖徒の中にいたアイネヤは八年寝たきりで[1]、ペテロは彼に
「イエス・キリストがあなたをいやしてくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい」
と命じました。癒やされたを見て、ルダとルダを含む周辺のサロン(シャロン)地方の人々はみな主に立ち返ったのです。
ルダから更に16km北西にあるのが港町ヨッパです。そこにも主の弟子たちの共同体がありましたが、タビタという女性が亡くなって、弟子たちは彼女の遺体を丁寧に洗い、屋上の間において、ルダのペテロを呼びに二人の使いを送りました。奇蹟を期待したからなのか、タビタとペテロが親しかったからなのか、は分かりません。ただ、復活という奇蹟は使徒の働きでも二つしかありません[2]。ペテロならよみがえるという理解はなかったはずです。ともかく、ルダにいたペテロは、ヨッパからの使いに乞われて20km近くを歩いてヨッパに行きました。そしてそこでタビタ(ドルカス)を痛む女性たち、ドルカスの作ってくれた下着や上着、またドルカス自身の遺体を見て、彼はどうしたわけかみんなを外に出して跪いて祈ります。そして遺体の方を向いて
「タビタ、起きなさい」
と言うと、彼女は生き返るのですね。そして、他の弟子たち、聖徒たち[3]は慰めを受け、町中に知られて、多くの人々が主を信じたのです。
しかし肝心なのはこの続きの43節です。
「43そして、ペテロはしばらくの間、ヨッパで、皮なめしのシモンという人の家に泊まっていた。」
こうしてヨッパに来た事が次の一〇章でカイザリヤのコルネリオとの出会いに繋がるのです。言わばヨッパに来たことはカイザリヤに行くための準備でした。ペテロは知りませんでしたが、実は、主はペテロをカイザリヤに遣わすため、ルダで大きな癒やしをなさり、次にヨッパに導かれたのです。ルダとヨッパの二つの奇蹟は、ただ奇蹟の力や初代教会の信仰などを言いたいのではありません。この大きな流れから切り離して、奇蹟だけを取り上げても何も分からないし、どんな結論も的外れなのです。
2.ヨッパに来た理由
初代教会にどれほど奇蹟や癒やしがあったのかは分かりません。ここのルダとヨッパの出来事も特筆される出来事であって、こんな奇蹟ばかりがいつもあったのではないでしょう。ルダにもヨッパにも大勢の病人がいて、毎日誰かしらが死んでいたはずです。教会はそういう病や死を祈っていつも乗り越えていたなら、この出来事自体、大きな反響はなかったでしょう。これがたぐいまれな出来事だったからこそ、周囲の人々は主に立ち返り、主を信じたのです。私たちは、主なる神がどんな病も癒やすことが出来、死からの復活さえなし得る神を信じています。しかしそれを主がいつどのようになさるかは、主御自身がお決めになることです。私たちは信じて、期待して祈りますが、私たちが信じるから奇蹟が起きたり、信仰が足りないから癒やされなかった、などと考えるのは甚だしい見当違いです。主はそんな小さく、無慈悲な神ではありません[4]。主はアイネヤを癒やされましたが、ルダには他にも大勢病人はいたでしょう。タビタを復活させてくれましたが、そこにいたやもめたちの夫までよみがえらせたわけではありませんでした。ペテロだって、先にユダヤ当局の迫害で多くの仲間を失ったのです。彼らを看取り、悲しみ、迫害者サウロを恐れたのです。そういう多くの死を味わっていた教会で、なぜかタビタがよみがえらされたこの奇蹟は起きました。主がタビタを贔屓されたからでも、人々の願いが特別に強かったからでもなく、ただ主が前にも後にもないこの特別な奇蹟を、ペテロを通してなさった、人知を越えたご決断に他なりません[5]。
元々ペテロはたまたまルダに来た所、偶然アイネヤと出会いました。そしてアイネヤの癒やしが評判になったことで、自分がルダにいることがヨッパに伝わりました。図らずもタビタが死んで、弟子たちはペテロを呼ぶためルダに使いを出し、こうしてヨッパに来たのです。ペテロにとってもこの二つの奇蹟や、その結果の大勢の回心は本当に驚きだったでしょう。また彼は、タビタが貧しいやもめたちに仕え、下着や上着を何枚も手で縫って作っていた美しい交わりを見ました[6]。夫を亡くした女性たち、癒やされない人、変えられない過去がある一方、そこで助け合い、出来る形で仕え、かけがえのない絆で結ばれているかけがえのない交わりを見ました。そして、そこに不思議な癒やしや奇蹟も不思議にも経験させられました。そうしたひと言では言えない体験の旅路が、実は次のカイザリヤでの新しい展開に続いていたのです。
3.皮なめし職人シモンの家に
最後の43節で
「皮なめしのシモン」
の家にペテロが泊まったと印象的な記述があることも見ておきましょう。皮なめしは、死体や血を扱うので、ユダヤ教的には汚れた卑しい仕事でした[7]。ちょうどイエスがエリコで取税人ザアカイの家に泊まると仰った時、全員が不平を呟き始めたように、ペテロがタビタをよみがえらせたと聞いて主を信じた大勢の人も、ペテロが皮なめしのシモンの家に泊まっていると聞いたら、途端にドン引きしたのではないでしょうか。しかしペテロはそのシモンの友となり、彼の家に泊まり、一緒に食事をし、過ごしました。奇蹟の力でみんなを惹き付け、一人でも多くの人を入信させようなどという生き方はここにありません。シモンが卑しめられている皮なめしのままで、ペテロは一緒にいたのです。見下された人、病人、悲しんでいる人に対し、神の力で、陽の当たる場所に無理矢理連れて行こうとはしませんでした。卑しめられているままの彼とともにいて、悲しみもあれば、奇蹟もある生活-神の力を味わうこともあれば、華やかな奇蹟などないこともある生活を、そのままを分かち合うようです。そして、そのような彼の歩みは、次の異邦人伝道へと導かれていました。それさえも、もっと華やかなどころか、皮なめしよりももっと卑しめられ、疎んじられていた異邦人たちとの出会い、交わりでした。更に低く、更に自由になっていく旅でした。
主イエス御自身、大勢の(しかし全員ではない)人を癒やされ、数名の死者をよみがえらせました。しかし目指しておられたのは癒やしや奇蹟自体ではなく、十字架と復活です。それによって、私たちを神の子としての新しい生き方に招き入れることです。主は全ての罪を赦して、私たちを神と和解させてくださいます。そして、私たちが自分で造り上げた差別や敵意の壁からも出て来て、主に愛されている者同士としての豊かなつながりに生かしてくださいます。傷や限界や違いを受け入れ合う新しい生き方に導いておられます。奇蹟ばかりではありませんが、確かに主の不思議な御業も沢山あります。また、人に仕え慰めている美しい尊い姿も私たちの回りに鏤(ちりば)められています。そうした出来事や慰めや出会いに教えられ、励まされ、プライドを砕かれ、恵みを分かち合う旅路の途中にいます。私たちの願う筋書きではなく、神御自身が十字架をもって始められた深いご計画の中で生かされ、導かれていることを思わされるのです。
「主よ。不思議にも生かされて、あなたに出会い、今この教会でともに礼拝していること。あなたが導かれた尊いご計画です。一人一人の命や人生や悲しみもあなたが抱きしめておられるように、私たちも互いに尊び合わせてください。聖なる恵みのゴールに向けて希望を持たせて、その旅路、今ここにもある奇蹟に気づかせて、私たちに愛を与えて心から新しくしてください」

[1] 中風が脳卒中などの後遺症で手足や半身の麻痺のことです。「八年の間も床に着いて」は「八歳のときから」とも訳せます。
[2] この箇所と二〇章7-12節の「ユテコ」の復活の2箇所。
[3] 「聖徒」はキリスト者を指す言い方ですが、使徒の働きでは九13で初めて使われました。それはアナニヤがサウロを受け入れるようにと命じる主の幻に対して「主よ。私は多くの人々から、この人がエルサレムで、あなたの聖徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。」という言葉です。この「ひどい目に遭わされた」存在である聖徒たちが、32節ではルダに、41節ではヨッパにいて、小さなコミュニティを形成していたのです。そのひどい目に遭わされてきた彼らが、タビタの復活から慰めを受けた、と考えると、彼らの傷が深く慰められる出来事であったことを僅かながら想像することができます。
[4] もちろん今も癒やしはあります。病気が治る、という奇蹟さえ少なからず起きています。しかしそもそも医療も健康状態も神が用いてくださり、人の努力、学究を通して、病気が治療され、そのわざに携わる医療制度が確立しているのです。医師たちも、自分たちが病気を治すのではなく、体の持っている生命力や治癒力が働くのを助けるに過ぎないと言います。今私たちが健康であることもアタリマエではありません。今日生かされていることが、神の御業、いのちの主の贈り物だと気づこう。単純な話、この一世紀当時の人々が21世紀の先進国に生きる私たちを見たら、驚異的な長寿で、驚くほど低い死亡率にうらやむことでしょう。それでも私たちが、病気や痛みに文句を言い、神の癒やしがないなどと言ったら、「不老不死を望むのか」と呆れられるのではないでしょうか。
[5] それも、イエスが会堂司ヤイロの死んだ娘をよみがえらせた、あの「タリタ、クミ」の奇蹟とソックリな奇蹟(マルコ五35-43、ルカ八49-56、参照)です。自分がイエスを真似るようにして起きたのです。ペテロはそこにどんな不思議な思い、恐れ多い思いを抱いたでしょうか。因みに、二つの復活の類似点は、死人の復活の他、人々の悲しみ、人払い、「タビタ・クミ」と「タリタ・クミ」、起き上がったこと。相違点は、ペテロは祈ったがイエスは祈らなかったこと、イエスは死んでいた少女の手を取って起こすが、ペテロは生き返って起き上がったタビタに手を貸して彼女を立たせたこと、「タリタ」(娘よ=実の父娘に勝るイエスとの関係性)と「タビタ」(個人名)、イエスは誰にも話すなと言われ、ペテロはみんなに見せて周囲に知れ渡ったこと。両者を、元は一つの出来事だったと取る人もいますが、相違点も多くあるのです。
[6] 36節で「タビタ、訳すとドルカス」つまりカモシカだとありますが、わざわざギリシャ語に訳すような、特別に印象深い、名前通りの働きをした人、ということでしょう。
[7] 「今、イスラエルに旅行すると、シモンの家と言われる場所があるそうですが、岬の突端のような離れたところだそうですね。川向こう、そこも近くありながら、愛の届かない地の果てです。地の果ては、ただ地理的に遠くにあるだけでなく、具体的な隣人との関係で、私たちが住んでいる地域にもあります。」(後藤敏夫、『神の秘められた計画』、いのちのことば社、2017年、71頁)