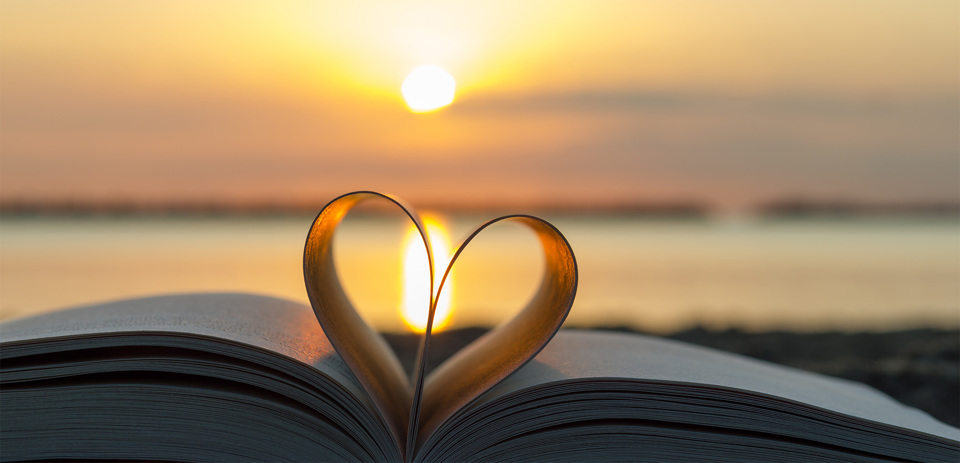2017/11/19 ハ信仰問答96「もっと良い見えない方法」マタイ24章1-2節
十戒の第二戒を見ます。
「偶像を作ってはならない」。
第一戒でも偶像のことをお話ししました。偶像崇拝にはあらゆる形のものがあると先週確認しました。第二戒はどう違うのでしょうか。第一戒では、本当の神、天地を造られて、聖書を与えてくださった神の他に神を持ってはならない、でした。神ならぬものを神とする、という意味での偶像崇拝です。それは第一戒の禁止事項でした。この第二戒はそれを踏まえた上で、
問96 第二戒で神は何を望んでおられますか。
答 わたしたちが、どのような方法であれ神を形作ったり、この方が御言葉の中でお命じになった以外の仕方で礼拝をしてはならない、ということです。
つまり、天地の造り主、聖書の神を礼拝すると言いながら、そこに偶像を持ち込んでしまうことを戒めています。真の神への礼拝に、自分たちに都合のよい像や形、方法を持ち込み、結局は、神を礼拝するのではなく、自分に都合のよい礼拝をすること。それが禁じられているのです。そして、わざわざそう言われていることが示すように、私たちが実によくやらかしがちな、いいえ、やらかさずにおれない間違いです。
特にこのハイデルベルグ信仰問答の背景である宗教改革の時期、当時の教会には、会堂の中にたくさんの像がありました。十字架にはイエスがついており、マリアとイエス、聖書の物語、神の像などがたくさん置かれていたのです。それは、聖書の物語をよくわかるためであって、決してこれを拝んだりお願いをしたりするためではない、とは言っていました。しかし、当然ながら実際には、民衆の中にはこうした像を崇める人、神格化する考えが蔓延していました。まだ文字も読めない人が多い時代、聖書も読めないし、教育もない人に分かりやすい絵や像は確かに親しみやすく、インパクトがありました。インパクトがありすぎて、そちらを崇めたて、イエス・キリストよりも像や形に縋りつくようになったのです。つまり、礼拝の方法に「わかりやすいもの」「目に見えるもの」を持ち込むと、礼拝や信仰そのものが大きく変質してしまうのです。ですから
問97 それならば、人はどのようなかたちをも作ってはならないのですか。
答 神は決して模写されえないし、またされるべきでもありません。被造物については、それが模写されうるとはいえ、人がそれを崇めたりまたはそれによってこの方を礼拝するためにそのかたちを作ったり所有したりすることを、神は禁じておられるのです。
問98 しかし、かたちは、一般信徒の教育手段として教会で許されてもよいのではありませんか。 答 いいえ。わたしたちは神より賢くなろうとすべきではありません。この方は御自分の信徒を、物言わぬ偶像によってではなく御言葉の生きた説教によって教えようとなさるのです。
ユダヤ人は旧約聖書の時代、神殿に偶像を持ち込んで、まさにこの第一戒と第二戒の違反を重ねました。その反省を込めて、それ以降、彼らは厳格に像を造らず、潔癖に生きていました。イエスの時代、ローマ帝国が芸術の文化を持ち込んだ時、たくさんの摩擦がありました。たとえばローマのコインには皇帝の像が刻まれていました。
ユダヤがローマ帝国の属州になったとき、これを使うのは大変な抵抗があり、神殿への献金には認めず、ユダヤのお金への両替がなされました。そのように徹底した像の排除をしたのです。しかしそれでこの第二戒が守れたのでしょうか。いいえイエスと初代教会との間に確執となったのは、像を排除して神を礼拝した神殿そのものの偶像化でした。弟子たちが立派な神殿を見てイエスに興奮気味に
「この神殿をご覧ください」
と言ったとき、イエスは神殿も何もかも跡形もなく崩れる日が来るとおっしゃいました。神殿の大祭司たちは、教会から向けられた自分たちの見えない問題への指摘に耳を傾けるよりも、神殿を冒涜したけしからん奴らだと応酬しました。
今の教会もそうです。イエス像やマリア像、聖像や聖画をなくしても、建物を誇ることもあります。会堂が立派だとか、賛美が美しい、音響機器が充実している、牧師が素晴らしい…なんにせよ、キリストが下さった福音や、この恵みの神への礼拝よりも、自分たちの手っ取り早く、居心地の良いものが礼拝の中心となるのです。神が定めたのではない、方法や形を持ち込むと、それは助けではなく、足を引っ張り、全く違う信仰にしてしまうのです。
人間同士でさえ、互いに完璧に理解することは出来ません。「あの人はこんな人だよ」と決めつけた途端、そこには人格的な温かみある関係は持てなくなります。まして「神はこんな方だ、今起きた出来事はこんな意味があるに違いない、神がおられるならきっとこうしてくださるはずだ」と決めつけることはどうでしょう。神は無限で永遠のお方です。私たちは有限で時間の中を生きている、本当に小さな存在です。神が無限である、ということさえ自分の限りある理解の中で小さくしか想像できない、貧しい存在です。

C・S・ルイスの『悪魔の手紙』という本で、悪魔がこんなことを言います。「もし人間が神に向かって、『私の考えているあなたではなく、あなたが知っておられるあなたの御心の通りにしてください』と祈るようになれば、我々には打つ手がなくなる」。私たちが知っているのは、どこまで行っても、永遠なる神のごく一部です。神の考えは、本当に大きく、広く、いつも驚かされます。神の恵みは、限りなく深く、豊かで、絶えず胸が熱くなります。その大きさをいつも弁えるからこそ、自分には思いがけないこと、理解できないことが起こっても、そこにも神が働かれ、益となさり、栄光を現わしてくださると信じるのです。神は私たちに、居心地の良い生活を保障されません。むしろ、私たちが閉じこもっている小さな世界、神を知らない奴隷のような生き方から、神の子どもとしての広やかな世界に連れ出してくださるお方です。それを私たちが引き下げて、神ご自身まで自分の見える形に引き下ろしてしまうとしたら、もったいないことです。
イエスは見える世界に神の栄光を見せられました。空の鳥を、野の花を見なさい、困っている人を見なさい、パンを食べ杯を飲みなさい、と言われました。見えるものは大事ではない、ではなく、今目の前にあるもの、神が作られた見せる世界の一つ一つが神の栄光を豊かに現しています。それでは足りないからと何かを持ち込み拝むことは不要です。むしろ見える世界、今ある世界、自然や目の前の人の中に、神がどのようなお方が現わされている。私たちも、神の栄光を現わすために、命を与えられている。そう気づかされるとき、ますます神の偉大さ、恵み深さに賛美をするようになるのです。