
著者は大学を卒業後、廣済堂出版に入社。初めて自身で企画した『公文式算数の秘密』を38万部のベストセラーにしたという。その後、文芸書を手掛けたいという思いから、角川書店に入社し、『野性時代』の副編集長、「月刊カドカワ」編集長、取締役編集部長を経て、1993年に幻冬舎を設立した。幻冬舎の代表取締役社長である著者が、己の人生の生い立ちと読書との関わり、読書が持つ意味を熱く語る。読書をする側からの読書論と併せ、編集者として数多くの作家と関わり、24年間で23冊のミリオンセラーを生み出すに至った経緯、本を生み出す側の裏話を交えて、本と読書への思いを語る。
我々は、読書により一人の一生では経験できないことを学ぶのであり、読書の量がその人の人生を決めるのだと力説する。本書には著者の読書に対する激しい言葉がぶつけられている。
著者は優れた「認識者」という土台を築かなければ、優れた「実践者」になることは不可能だという。そして「認識者になるためには、読書体験を重ねることが不可欠だ」という信念を持つ。挫折を含めた己の人生における読書を糧にして、また編集者という仕事を通じて、認識者から実践者として生きてきたと自負していると感じる。
「読書とは自己検証、自己嫌悪、自己否定を経て、究極の自己肯定へ至る、最も重要な武器なのである」(p220-221)と言う。「読書で得た認識者への道筋は、矛盾や葛藤をアウフヘーベンしなくては意味がない。それが『生きる』ということだ。認識者から実践者へ」(p221)突き進んでこその人生なのだと言う。それは「自己実現の荒野へ」突き進むことなのだと。
著者は、単なるお楽しみの読書やいわゆる教養として知識を積み重ねる、流行の情報を得るだけの読書を真っ向から否定する。人生を切り開いていくために、本質的なものを読み、読書から己がどう感じるかを重視する。「お前はどう生きるのか」という問いを突きつけられる読書体験を語る。本書は6章構成になっている。その第6章の末尾を「血で血を洗う読書という荒野を、僕は泣きながら突き進むしかない」という一文で締めくくる。『読書という荒野』というタイトルは、この一文からとられたようだ。
本書では著者の人生プロセスにおける読書との関わり方が赤裸々に語られて行く。
幼少年時代の家庭環境・苛めと読書への傾倒、高校時代の読書と反骨精神。読書から社会・世界の矛盾や不正、差別に怒り、大学時代に左翼思想に傾倒し政治行動にも踏み込むが、赤軍派のように踏み抜くことができなかった挫折とその頃の読書。人生前半の読書体験がダイナミックに語られる。
社会に出てから、著者は編集者としての人生を選択する。なぜ編集者になったのかを語るとともに、編集者として寄り添いミリオンセラーを生み出した作家と如何に関係づくりをしたか。どんなつきあい方をしてきたかの裏話がつづられていく。それは一種の武勇伝に通じ、また極端から極端への行動をしてきたという破天荒さを暴露した語りでもある。こんな編集者人生もあるのか・・・・・・。多分一つの極端事例ではないだろうかという気もする。だから、読んでいておもしろい。第3章のタイトルは、「極端になれ! ミドルは何も生み出さない」である。このタイトルはそれを実践した著者の持論なのだろう。
第2章「現実を戦う『武器』を手に入れろ」では、吉本隆明・高野悦子・奥浩平の著書や日本赤軍の奥平剛士・安田安之・岡本公三の乱射事件という行為を熱っぽく語る。それは左翼に傾倒していた時期の著者の心に結びつく。
その一方で、第6章の「血で血を洗う読書という荒野を突き進め」では、三島由紀夫が「楯の会」を結成し、最後には陸上自衛隊・市ヶ谷駐屯地に押し入り、割腹自殺を遂げたあの衝撃的な事件を語る。あの事件において配られた三島の「檄文」と三島の最後の演説の全文を引用している、「自らの観念に殉じて死ぬ生き方」をとった三島由紀夫について、「言葉を突き詰めてしまった者が、必然的に選ばざるを得ない最後である」(p213)と評し、「僕は、彼の自決そのものが一つの文学だと考えている」(p214)と論じている。
極端から極端への振幅を持つ読書遍歴の中で、著者は「自己検証、自己嫌悪、自己否定」を繰り返してきたという。桁外れの読書と人生の吐露が興味深く、かつおもしろい。そこが本書の読ませどころになっている。
第3章から第6章にかけては、編集者となった著者が様々な作家と関わり、ベストセラアーを生み出すに至った裏話をしている。それは作家と著者(編集者)との生身のぶつかり合いである。愉快な・豪快な・特異とも言える深い濃密な関わりあいのエピソードに溢れていている。ここに取り上げられ具体的なエピソードが書き込まれている作家たちの名前を列挙しておこう。それぞれの作家との関係性がおもしろい読み物になっている。
五木寛之、石原慎太郎、中上建治、村上龍、林真理子、草間彌生、坂本龍一、つかこうへい、である。
他にも著者が編集者として関わりを深めた作家やアーティスト、読書という観点で影響を受けたとして取り上げている人々と作品が沢山登場している。省略する。
最後に著者の読書に対する激越な思いについて、その語録を一部紹介しよう。後は、一度本書を開いてみるとよい。
*人間としての言葉を獲得するにはどうすればいいのか。それは、「読書」をすることにほかならない。 p3
*読書で学べることに比べたら、一人の人間が一生で経験することなど高が知れている。読書をすることは、・・・・・・そこには、自分の人生だけでは決して味わえない、豊穣な世界が広がっている。そのなかで人は言葉を獲得していくのだ。 p4
*僕はかねがね「自己検証、自己嫌悪、自己否定の三つがなければ、人間は進歩しない」と言っている。・・・・読書を通じ、情けない自分と向き合ってこそ、現実世界で戦う自己を確立できるのだ。 p6-7
『こころ』(付記:夏目漱石著)を読んで初めて、僕は「自己検証、自己嫌悪、自己否定」という概念を実感した。 p29
*読書体験によって多様な人間、多様な人生を追体験し、人間や社会に対する洞察力を手に入れるべきなのだ。 p11
僕が考える読書とは、実生活では経験できない「別の世界」の経験をし、他者への想像力を磨くことだ。重要なのは、「何が書かれているか」ではなく、「自分がどう感じるか」なのである。 p15
*著者の気持ちと編集者の気持ちがカチッとはまったときに、たまたま、名作は誕生する。 p18
*僕の「血と骨」と言えるのが『マチウ書試論』だ。『マチウ書試論』を何百回とな読み返しているが、そのたびに新しい発見がある。 p61
『マチウ書試論』は自己の非倫理を倫理に反転する、私的闘争を賭けた吉本隆明の再生の書なのだ。 p63
*僕はいつも、「売れるコンテンツの条件は、オリジナリティがあること、極端であること、明解であること、癒着があること」と言っている。とはいえ、これはあくまでも結果的に導き出した法則にすぎない。 p85
*僕は人と会うときは、常に刺激的で新しい発見のある話、相手が思わず引き込まれるような話をしなければいけないと思っている。 p86
*本とは単なる情報の羅列ではない。自分の弱さを思い知らされ、同時に自分を鼓舞する、現実を戦うための武器なのだ。 p94
*感想こそ人間関係の最初の一歩である。・・・・だからこそ、「言葉」は武器なのだ。 p102
*表現とは結局自己救済なのだから、自己救済の必要がない中途半端に生きている人の元には優れた表現は生まれない。ミドルは何も生み出さない。 p127
*文学は、・・・・過剰か欠落を抱えた人間からしか生まれない。 p143
*確固たる世界を構築している作家の作品に触れることで、世界や人間の本質を体感できる。 p154
*本物の表現者は例外なく「表現がなければ、生きてはいられない」という強烈な衝動を抱えていることだ。 p164
*結局、作家と編集者は浄瑠璃でいう「道行き」のような関係なのだ。 p184
*一心不乱に本を読み、自分の情念に耳を澄ます時期は、必ず自分の財産になる。だから、手軽に情報が取れるようになっただけになおさら、意識して読書の時間を捻出すべきだと僕は考えている。 p192
ご一読ありがとうございます。
我々は、読書により一人の一生では経験できないことを学ぶのであり、読書の量がその人の人生を決めるのだと力説する。本書には著者の読書に対する激しい言葉がぶつけられている。
著者は優れた「認識者」という土台を築かなければ、優れた「実践者」になることは不可能だという。そして「認識者になるためには、読書体験を重ねることが不可欠だ」という信念を持つ。挫折を含めた己の人生における読書を糧にして、また編集者という仕事を通じて、認識者から実践者として生きてきたと自負していると感じる。
「読書とは自己検証、自己嫌悪、自己否定を経て、究極の自己肯定へ至る、最も重要な武器なのである」(p220-221)と言う。「読書で得た認識者への道筋は、矛盾や葛藤をアウフヘーベンしなくては意味がない。それが『生きる』ということだ。認識者から実践者へ」(p221)突き進んでこその人生なのだと言う。それは「自己実現の荒野へ」突き進むことなのだと。
著者は、単なるお楽しみの読書やいわゆる教養として知識を積み重ねる、流行の情報を得るだけの読書を真っ向から否定する。人生を切り開いていくために、本質的なものを読み、読書から己がどう感じるかを重視する。「お前はどう生きるのか」という問いを突きつけられる読書体験を語る。本書は6章構成になっている。その第6章の末尾を「血で血を洗う読書という荒野を、僕は泣きながら突き進むしかない」という一文で締めくくる。『読書という荒野』というタイトルは、この一文からとられたようだ。
本書では著者の人生プロセスにおける読書との関わり方が赤裸々に語られて行く。
幼少年時代の家庭環境・苛めと読書への傾倒、高校時代の読書と反骨精神。読書から社会・世界の矛盾や不正、差別に怒り、大学時代に左翼思想に傾倒し政治行動にも踏み込むが、赤軍派のように踏み抜くことができなかった挫折とその頃の読書。人生前半の読書体験がダイナミックに語られる。
社会に出てから、著者は編集者としての人生を選択する。なぜ編集者になったのかを語るとともに、編集者として寄り添いミリオンセラーを生み出した作家と如何に関係づくりをしたか。どんなつきあい方をしてきたかの裏話がつづられていく。それは一種の武勇伝に通じ、また極端から極端への行動をしてきたという破天荒さを暴露した語りでもある。こんな編集者人生もあるのか・・・・・・。多分一つの極端事例ではないだろうかという気もする。だから、読んでいておもしろい。第3章のタイトルは、「極端になれ! ミドルは何も生み出さない」である。このタイトルはそれを実践した著者の持論なのだろう。
第2章「現実を戦う『武器』を手に入れろ」では、吉本隆明・高野悦子・奥浩平の著書や日本赤軍の奥平剛士・安田安之・岡本公三の乱射事件という行為を熱っぽく語る。それは左翼に傾倒していた時期の著者の心に結びつく。
その一方で、第6章の「血で血を洗う読書という荒野を突き進め」では、三島由紀夫が「楯の会」を結成し、最後には陸上自衛隊・市ヶ谷駐屯地に押し入り、割腹自殺を遂げたあの衝撃的な事件を語る。あの事件において配られた三島の「檄文」と三島の最後の演説の全文を引用している、「自らの観念に殉じて死ぬ生き方」をとった三島由紀夫について、「言葉を突き詰めてしまった者が、必然的に選ばざるを得ない最後である」(p213)と評し、「僕は、彼の自決そのものが一つの文学だと考えている」(p214)と論じている。
極端から極端への振幅を持つ読書遍歴の中で、著者は「自己検証、自己嫌悪、自己否定」を繰り返してきたという。桁外れの読書と人生の吐露が興味深く、かつおもしろい。そこが本書の読ませどころになっている。
第3章から第6章にかけては、編集者となった著者が様々な作家と関わり、ベストセラアーを生み出すに至った裏話をしている。それは作家と著者(編集者)との生身のぶつかり合いである。愉快な・豪快な・特異とも言える深い濃密な関わりあいのエピソードに溢れていている。ここに取り上げられ具体的なエピソードが書き込まれている作家たちの名前を列挙しておこう。それぞれの作家との関係性がおもしろい読み物になっている。
五木寛之、石原慎太郎、中上建治、村上龍、林真理子、草間彌生、坂本龍一、つかこうへい、である。
他にも著者が編集者として関わりを深めた作家やアーティスト、読書という観点で影響を受けたとして取り上げている人々と作品が沢山登場している。省略する。
最後に著者の読書に対する激越な思いについて、その語録を一部紹介しよう。後は、一度本書を開いてみるとよい。
*人間としての言葉を獲得するにはどうすればいいのか。それは、「読書」をすることにほかならない。 p3
*読書で学べることに比べたら、一人の人間が一生で経験することなど高が知れている。読書をすることは、・・・・・・そこには、自分の人生だけでは決して味わえない、豊穣な世界が広がっている。そのなかで人は言葉を獲得していくのだ。 p4
*僕はかねがね「自己検証、自己嫌悪、自己否定の三つがなければ、人間は進歩しない」と言っている。・・・・読書を通じ、情けない自分と向き合ってこそ、現実世界で戦う自己を確立できるのだ。 p6-7
『こころ』(付記:夏目漱石著)を読んで初めて、僕は「自己検証、自己嫌悪、自己否定」という概念を実感した。 p29
*読書体験によって多様な人間、多様な人生を追体験し、人間や社会に対する洞察力を手に入れるべきなのだ。 p11
僕が考える読書とは、実生活では経験できない「別の世界」の経験をし、他者への想像力を磨くことだ。重要なのは、「何が書かれているか」ではなく、「自分がどう感じるか」なのである。 p15
*著者の気持ちと編集者の気持ちがカチッとはまったときに、たまたま、名作は誕生する。 p18
*僕の「血と骨」と言えるのが『マチウ書試論』だ。『マチウ書試論』を何百回とな読み返しているが、そのたびに新しい発見がある。 p61
『マチウ書試論』は自己の非倫理を倫理に反転する、私的闘争を賭けた吉本隆明の再生の書なのだ。 p63
*僕はいつも、「売れるコンテンツの条件は、オリジナリティがあること、極端であること、明解であること、癒着があること」と言っている。とはいえ、これはあくまでも結果的に導き出した法則にすぎない。 p85
*僕は人と会うときは、常に刺激的で新しい発見のある話、相手が思わず引き込まれるような話をしなければいけないと思っている。 p86
*本とは単なる情報の羅列ではない。自分の弱さを思い知らされ、同時に自分を鼓舞する、現実を戦うための武器なのだ。 p94
*感想こそ人間関係の最初の一歩である。・・・・だからこそ、「言葉」は武器なのだ。 p102
*表現とは結局自己救済なのだから、自己救済の必要がない中途半端に生きている人の元には優れた表現は生まれない。ミドルは何も生み出さない。 p127
*文学は、・・・・過剰か欠落を抱えた人間からしか生まれない。 p143
*確固たる世界を構築している作家の作品に触れることで、世界や人間の本質を体感できる。 p154
*本物の表現者は例外なく「表現がなければ、生きてはいられない」という強烈な衝動を抱えていることだ。 p164
*結局、作家と編集者は浄瑠璃でいう「道行き」のような関係なのだ。 p184
*一心不乱に本を読み、自分の情念に耳を澄ます時期は、必ず自分の財産になる。だから、手軽に情報が取れるようになっただけになおさら、意識して読書の時間を捻出すべきだと僕は考えている。 p192
ご一読ありがとうございます。















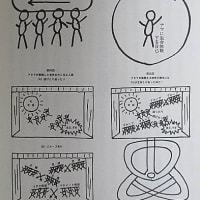




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます