
2012年3月20日の春分の日に、滋賀県米原市主催の「京極高次と奥琵琶湖歴史と文学の旅」という史跡巡りバスツアーに参加して、高島にある大溝城址その他を探訪した。この時、講師がこの大溝城について説明される際、京極高次が城主であった時の大溝城と奥琵琶湖の描写を引用された。それでこの本を知った。
本書は昭和41年(1966)3月に毎日新聞社から単行本として、昭和63年(1988)に講談社から『日本歴史文学館』の1冊(14巻)として出版されていた。角川、旺文社の文庫としても発刊されていたようだが、現在は古書扱いになっている。それが2008年4月に、水上勉勘六山房叢書という名称を表紙に併記される形で、上・下二巻で復刊された。だが、水上作品としてはどうもマイナーな位置づけになっているようだ。(見落としでなければ、1976~1978年に中央公論新社から発刊された水上勉全集には所載されていない。)
復刊の表紙に「勘六山房叢書」という名称がなぜ付されたのだろう? この名称でネット検索しても『湖笛』との関連でこの語句がヒットするだけである。「勘六山房」で検索すると、少しヒントが得られた。
「作家、故水上勉氏が主宰し、1993年に長野県東御市に作った工房。水上氏が最晩年の12年間を過ごし、執筆活動を始め、様々な創作活動を行った山房」だという。山房名の由来はわかったのだが、「勘六山房叢書」という表記は、やはり謎のまま・・・・
さて、本書は一言でいえば、京極高次が京極家を再興するまでの紆余曲折を小説化したものである。
佐々木氏を源流とし、守護職として北近江を支配していた京極氏は高次の父・高吉の代には没落していた。宇治・槇島(真木島)の戦いで信長に従った高次は近江の奥島5000石を与えられる。だが、明智光秀に加担したことで、秀吉に追われる身になる。高次が、同志安土万五郎と共に柏原村西北の山裾にある京極家菩提寺・清滝寺に隠れて住み、失意の人になっているところから話が始まる。
本書自体は、高次の妹、龍子が嫁いだ元若狭の国の領主、武田孫八郎元明が秀吉の呼び出しを受け、近江の国海津に出向するところから書き出されている。そして、元明は光秀に加担したと誹謗されて秀吉に切腹を迫られ、自害して果てる。その時、海津の宝幢院まで同行した家来の一人、熊谷佐兵衛は元明の非業の死を伝えるために逃げのび、若狭の神宮寺に戻り、元明の遺児武若と俊丸を追っ手から護ろうとする。その後、武若と佐兵衛は仇である秀吉に復讐することを誓う。龍子は既に丹羽長秀の家臣に連れ去られ、秀吉の許に送られてしまっていた。秀吉は3年前の朝倉攻めの時に若狭に立ち寄り、元明の妻、龍子を目にしていたのだ。
本書には3つの軸があると私は思う。高次が秀吉に追われる立場からどういう紆余曲折を経て、若狭一国の領主になりえたのかというプロセスそのものであり、これが主軸となる。そして、仇秀吉への復讐を誓う武若と熊谷佐兵衛の有為転変のプロセスが第2の軸となり、その二人の行動が高次の京極家再興の夢に悪影響を及ぼすかどうかという危険因子になり続ける。第3の軸は、元明の妻、武若の母である京極龍子が、その美貌の故に秀吉に目をつけられ、秀吉の側室として生きていかねばならなくなるという生き方である。この龍子が高次を陰から支えていくことになる。本書はこの3つの軸が織りなされていく構成と展開になっている。そこが本書の一つの読みどころだろう。
京極高次が光秀に加担し破れた後、高次の父・高吉への恩願を思う堀秀政が、秀吉の部下でありながら密かに清滝寺を訪れ、高次が逃げのびるように手助けをする。高次は秀政の勧告に従うことで、安土万五郎を実質上、秀吉に売ることになる。それが高次の悔いとして心に残る。秀政の要請を受けた小谷清兵衛の助けで窮地を脱した高次は、苦労の末に柴田勝家の許に身を寄せる。賎ヶ岳の合戦で、高次は佐久間盛政とともに行市山に陣取るが、ここからも敗退せざるを得なくなる。そして、武田家とも縁の深い若狭の万徳寺に落ちのびる。人生凋落の一途を辿るのだ。
この寺で、仙岳宗洞禅師に出会う。仙岳との対話を通じて、高次はそれまでの小我を捨て、京極家復興を第一義にするという大我に目覚めたと著者は語る。この後、丹羽長秀に招かれ、小浜の後瀬山にある小浜城に入り、秀吉から大溝5000石を与えられたとの達しを聞く(上/p197)。「京極は近江を興した勲功のある家柄じゃ。流浪させておくにはもったいない・・・・京極には大溝をやらねばならぬ・・・」。この大溝を若狭とともに所領していた丹羽長秀は越前・足羽城に異動する。ここから、秀吉の部下として、内心では秀吉を憎みながら、京極家復興という目的の下に、忠勤をはげむ高次として動き出す。そして、秀吉に頼まれて、この大溝城に茶々・はつの姉妹を一時預かることになる。この頃が秀吉による高次の力量試しの時期のように感じる。その陰には龍子の秀吉への助言があったとして描かれている。
秀吉の部下としての高次の内心を描写しつつ、外面的にはどのように行動して行ったかがストーリーとして展開されていく。その複雑な心理の動き、高次の懊悩が著者の書きたかったことであるように思う。また、秀吉の側室となった妹龍子のお陰で大名として取り立てられていっただけではなく、高次という人物の持つ能力が評価されていった側面を著者は描こうとしているように感じた。
ある意味で、高次の生き様のプロセスは変節の繰り返しである。しかし、そこに信長、秀吉、家康と戦国期から天下統一期に向かう中で「家」の復興を大命題にする一大名の生き様が如実に活写されている。
一方で、秀吉との関わりが深まるにつれて、秀吉に対する高次の見方が多角化し、総合的に捕らえながら評価する形に、高次の秀吉観が変化していくところも描く。この点も興味深い。
高次は、大溝5000石からスタートし、九州の役後に5000石加増される。天正18年(1590)の小田原征伐の功により近江八幡の八幡山城28000石、文禄4年(1595)に大津城6万石に封じられ、近江国内を順次異動していく。大名として頭角を現していき、京極家復興を成し遂げることになる。
高次は妹・龍子という背景があるにしても、秀吉の下で着々と実績を積み上げていく。しかし、心の底には秀吉から「謀叛者」とみられているという事実を忘れず行動する姿を描く。その高次が、茶々とはつを預かるのは、本書によると天正11年5月から天正14年10月までのようだ。そして、秀吉の許しを得てはつを娶るのは天正18年12月だと記す。一方で、姉妹を預かっている期間中の比良嵐の夜に、高次がはつと結ばれるシーンを描写している。「いくたび、はつと秘かな夜を契ったであろう」(下・p133)とも記す。秀吉に対して用心を重ねながら行動する高次が、昔から思いを寄せる相手だったとはいえ、大溝時代にそこまで本当に踏み切っただろうか。秀吉に知られれば、京極家再興の潰える理由になる話だと思うのだが・・・・ただ、小説の展開としては、そこに高次のロマンを感じさせるところでもある。
武若と佐兵衛は、高次をまず頼ろうとするが流浪をつづける高次には会えず、沖ノ島湖族に加わり、そこに居られなくなると瀬田の湖族に潜り込む。その後、大溝城主となった高次を頼って行くが、清滝寺に潜むように言われてそちらに一旦落ちて行く。だが即座に出奔し、その後徳川方に加わり、秀吉への復讐を遂げる機会をねらおうとする。この二人の動きが、高次を悩ますことになる。その一方で、高次は武若の復讐一徹の心に動かされ、大我のためといえども変節した自分に内心忸怩たる思いを抱き続けるのだ。このあたり高次の人間性が描き出されている。
大津城という交通の要衝、当時の地政学的に重要な拠点を任された高次が、この城において関ヶ原の戦い前夜に果たした役割が最後の押さえ所となっている。秀吉亡き後の西軍と徳川家康との狭間に置かれた高次の処し方、ある意味最後のその変節が高次の人生、京極家を決定したといえる。ここがやはり本書の読みどころのように思う。
本書で特に印象深かった章句を引用しておきたい。
*高次殿、あんたは、生きねばならぬ。生きるということは、白い一本道をのんきに歩くことではない。迷い迷うて歩くのが生きるというものじゃ。・・・・みんな同じ心の人間じゃ。 上・p187
*小さい我を張っていては道にふみ迷う。小我を捨てて、大我に生きることが、世に出る者の根本義じゃ。・・・・眼を閉じて、大きく活眼をひらかれい。 上・p188
*人間、死んでしまえば、それでお終いではないか。生きてこそ、苦しみの解かれもする喜びが味わえるというのに。死によって解放されるのはずるいと思う。 上・p189
*強い者は、運命を甘んじてうけ、運命の中に自分を見出して生きてゆく。運命にさからうことはたやすい。自滅の道がたどりやすいようにの・・・・ 下・p181
ところで、本書を読みながらいくつか疑問点も湧いて来た。著者は、「若狭守護群記」をかなり参照しているようだ。この書を確認できないので、この書に由来する記述なのかどうか定かではないが、いくつか気になる点がある。
*本書には、大徳寺の山内塔頭として桂春院という名称が何度も出てくる(上・p178、下・p57他)。ネット検索した範囲で、現在の大徳寺の塔頭に桂春院を見いだせなかった。同名で現存するのは、妙心寺の塔頭の中にある。当時の大徳寺には、桂春院という塔頭が存在したのだろうか。この点、気になる。
(禅寺の徒弟経験のある著者にこの点での思い違いがあるとは思えないし・・・・。応仁の乱で大徳寺の伽藍が焼失し、その後復興されてから、大火災に遭ったという事実はネット検索した限りなさそうである。龍子が幾度も桂春院を訪れているという描写があるので、それなりの塔頭でもあるはずなのだが・・・)
*高次は秀吉の達しとして、大溝5000石を当初から得たように著者は記す。これは事実だろうか。ウィキペディアでは、「天正12年(1584年)に近江高島郡の2500石を与えられる。その後は加増を重ね、天正14年(1586年)には高島郡5千石、・・・」と記されているのだ。この箇所も、史実を確認できる資料がないので、客観的な事実はどちらなのかが気になるところだ。(歴史小説といえど、明確な史実は改変できないはずなので。もちろんその描写のしかたはいろいろあるだろうが・・・)
*高次は茶々・はつ姉妹を大溝に預かるために伏見に赴く。ここで、著者は「高台なので、宇治川と淀川が合流する観月橋のあたりが一望に見わたせた。・・・・京極高次は、天正11年5月30日に、この桃山城についている」(上・p339)と記す。この記述には疑問がある。観月橋、桃山城という用語の使い方は歴史小説としては史実にそっているのだろうか。
手許の『新撰日本史図表』(監修・坂本賞三、福田豊彦 第一学習社)を見ると、安土桃山時代という時代区分になっているが、城名としては「伏見城」で表記されている。現在観月橋という橋が存在する。だが、そこは秀吉が伏見城を築くにあたり、宇治川の流れを変え、改修して後に「豊後橋」を架けた位置である。秀吉の当時に、「観月橋」が通称としても使われていたのだろうか。(現在の橋名を使用するなら、それを読者にわからせる別の文章の書き方ができると思う。)
現在の観月橋に至る少し手前で2つの川が合流する。しかし、ここで合流するのは宇治川と山科川である。現在、合流後は宇治川と呼ばれている。石清水八幡社のある八幡あたりで、桂川・宇治川・木津川が合流し淀川と称されるようになる。あの当時、伏見の港あたりまで、淀川と称されていたのだろうか。そうとも思えないのだが・・・
また、伏見城の造営開始は「文禄3年(1594)1.3であり、8.1に秀吉、伏見城に入る」と、ある年表に記す。上記『図表』にも「1594伏見城なる」と記す。別資料では、文禄元年(1592)に「豊臣秀吉 伏見指月に隠居城の造営を開始」とある。著者の記す天正11年は1583年であり、これらの史実記録と食い違う。
このように疑問もいくつかあるのだが、最後にひとつ記録しておきたい。
本書のところどころに出てくる琵琶湖の状景描写が、それぞれの人の心理描写の一環にもなっていて、両面から興味を惹かれた。以下はその描写の一端である。
*今しも杉木立が割れて、扇子を半ばすぼめたような視界がひらけている。前方に白い空がみえる。いや、空ではなかった。空の色と見まがうばかりの湖の水面がのぞいているのだった。 上・p5
*黒一色の葦の平原の向こうに、いま巨大な丸鏡を置いたように光る湖面がある。 上・p89
*賤ヶ岳の東は、白い山襞が紺青の琵琶湖すれすれに落ちこんでいる。水ははるか南の彼方まで、まるで雪の上に紺青の染料をしたたらせたように鮮明に浮いていた。 上・p128
*長命寺裏のなだらかな丘陵が湖へつき出して、ぽつんと点のように沖島だけがみえる。 上・p129
*湖面は大溝の出鼻をとりまいて、半紙を敷いたように白かった。 上・p201
*折から五月の緑に囲まれた湖面は、藍を溶かしたように美しかった。 上・p210
*いつみても変わりないはずの琵琶の水が、今日は冷たく沈んでいるような気がした。 上・p313
*陽の輝きはじめた湖面は朱をとかしたような色の中で、こまかいちりめん皺を光らせはじめた。
下・p83
*湖面へ桟橋がつき出ていて、いま、暮色になずみはじめた水面に点々と魞のさし竹がういてみえる。 下・p111
*琵琶湖は山の奥の暗い湖じゃと思うておった・・・ 下・p112
*高次は、整然とひろがる町並みを眺めたあと、遠い湖面を見やった。冬の朝である。清澄な空気は、陽を受けて、いま橙色に湖面の小波を輝かし、遠い山影をくっきりとうかべている。 下・p258
琵琶湖の表情がおもしろい。
ご一読、ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書を読みながら、関連語句とそこからの関心をネット検索してみた。
水上勉全集
勘六山房
京極氏 :ウィキペディア
京極高次 :ウィキペディア
京極龍子 ←京極竜子:ウィキペディア
武田元明 :ウィキペディア
京極家の菩提寺 清滝寺徳源院 :「近江の城郭」野暮氏
祥瑞庵 ← 祥瑞寺 :「一休さんのくにプロジェクト」
神宮寺 :小浜市
大徳寺 HP
大徳寺山内地図 :大徳寺HP
大徳寺塔頭 :「京都おもしろスポット」
妙心寺山内図 :妙心寺HP
桂春院 :ウィキペディア
妙心寺・塔頭 桂春院 :「京都を歩くアルバム」
大溝城/大溝陣屋 :「藤波イズム」
近江八幡城 :「ザ・登城」46(しろ)&光明子氏
近江八幡山城 :「近江の城郭」野暮氏
大津城 :ウィキペディア
大津籠城戦の八日間:「ランニング好きの研修トレーナーの日記」木村嘉伸氏
後瀬山城 :ウィキペディア
越前 北庄城(北ノ庄城) :「近江の城郭」
越前府中城 :「お城の旅日記」
堀秀政 :ウィキペディア
増田長盛 :ウィキペディア
淀川 :ウィキペディア
観月橋(豊後橋) :「ものシリーズ」
京都の豊後橋を知っていますか? :「民族学伝承ひろいあげ辞典」H.G.Nicol氏
巨椋池 :ウィキペディア
この中に、淀堤に触れています。
水坂峠 :「ORRの道路調査報告書」
水上勉の信濃を歩く :「東京紅團」

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
付記
この復刊版、巻末に「本文中明らかな誤植と思われる箇所は正しましたが、原則として底本に従いました。」(底本は『日本歴史文学館』14巻)としている。しかし、上下巻ともに、文章中に明らかに誤植と思われる箇所がかなり目についた。これはどこに問題があるのだろうか。ちょっと気になる。
本書は昭和41年(1966)3月に毎日新聞社から単行本として、昭和63年(1988)に講談社から『日本歴史文学館』の1冊(14巻)として出版されていた。角川、旺文社の文庫としても発刊されていたようだが、現在は古書扱いになっている。それが2008年4月に、水上勉勘六山房叢書という名称を表紙に併記される形で、上・下二巻で復刊された。だが、水上作品としてはどうもマイナーな位置づけになっているようだ。(見落としでなければ、1976~1978年に中央公論新社から発刊された水上勉全集には所載されていない。)
復刊の表紙に「勘六山房叢書」という名称がなぜ付されたのだろう? この名称でネット検索しても『湖笛』との関連でこの語句がヒットするだけである。「勘六山房」で検索すると、少しヒントが得られた。
「作家、故水上勉氏が主宰し、1993年に長野県東御市に作った工房。水上氏が最晩年の12年間を過ごし、執筆活動を始め、様々な創作活動を行った山房」だという。山房名の由来はわかったのだが、「勘六山房叢書」という表記は、やはり謎のまま・・・・
さて、本書は一言でいえば、京極高次が京極家を再興するまでの紆余曲折を小説化したものである。
佐々木氏を源流とし、守護職として北近江を支配していた京極氏は高次の父・高吉の代には没落していた。宇治・槇島(真木島)の戦いで信長に従った高次は近江の奥島5000石を与えられる。だが、明智光秀に加担したことで、秀吉に追われる身になる。高次が、同志安土万五郎と共に柏原村西北の山裾にある京極家菩提寺・清滝寺に隠れて住み、失意の人になっているところから話が始まる。
本書自体は、高次の妹、龍子が嫁いだ元若狭の国の領主、武田孫八郎元明が秀吉の呼び出しを受け、近江の国海津に出向するところから書き出されている。そして、元明は光秀に加担したと誹謗されて秀吉に切腹を迫られ、自害して果てる。その時、海津の宝幢院まで同行した家来の一人、熊谷佐兵衛は元明の非業の死を伝えるために逃げのび、若狭の神宮寺に戻り、元明の遺児武若と俊丸を追っ手から護ろうとする。その後、武若と佐兵衛は仇である秀吉に復讐することを誓う。龍子は既に丹羽長秀の家臣に連れ去られ、秀吉の許に送られてしまっていた。秀吉は3年前の朝倉攻めの時に若狭に立ち寄り、元明の妻、龍子を目にしていたのだ。
本書には3つの軸があると私は思う。高次が秀吉に追われる立場からどういう紆余曲折を経て、若狭一国の領主になりえたのかというプロセスそのものであり、これが主軸となる。そして、仇秀吉への復讐を誓う武若と熊谷佐兵衛の有為転変のプロセスが第2の軸となり、その二人の行動が高次の京極家再興の夢に悪影響を及ぼすかどうかという危険因子になり続ける。第3の軸は、元明の妻、武若の母である京極龍子が、その美貌の故に秀吉に目をつけられ、秀吉の側室として生きていかねばならなくなるという生き方である。この龍子が高次を陰から支えていくことになる。本書はこの3つの軸が織りなされていく構成と展開になっている。そこが本書の一つの読みどころだろう。
京極高次が光秀に加担し破れた後、高次の父・高吉への恩願を思う堀秀政が、秀吉の部下でありながら密かに清滝寺を訪れ、高次が逃げのびるように手助けをする。高次は秀政の勧告に従うことで、安土万五郎を実質上、秀吉に売ることになる。それが高次の悔いとして心に残る。秀政の要請を受けた小谷清兵衛の助けで窮地を脱した高次は、苦労の末に柴田勝家の許に身を寄せる。賎ヶ岳の合戦で、高次は佐久間盛政とともに行市山に陣取るが、ここからも敗退せざるを得なくなる。そして、武田家とも縁の深い若狭の万徳寺に落ちのびる。人生凋落の一途を辿るのだ。
この寺で、仙岳宗洞禅師に出会う。仙岳との対話を通じて、高次はそれまでの小我を捨て、京極家復興を第一義にするという大我に目覚めたと著者は語る。この後、丹羽長秀に招かれ、小浜の後瀬山にある小浜城に入り、秀吉から大溝5000石を与えられたとの達しを聞く(上/p197)。「京極は近江を興した勲功のある家柄じゃ。流浪させておくにはもったいない・・・・京極には大溝をやらねばならぬ・・・」。この大溝を若狭とともに所領していた丹羽長秀は越前・足羽城に異動する。ここから、秀吉の部下として、内心では秀吉を憎みながら、京極家復興という目的の下に、忠勤をはげむ高次として動き出す。そして、秀吉に頼まれて、この大溝城に茶々・はつの姉妹を一時預かることになる。この頃が秀吉による高次の力量試しの時期のように感じる。その陰には龍子の秀吉への助言があったとして描かれている。
秀吉の部下としての高次の内心を描写しつつ、外面的にはどのように行動して行ったかがストーリーとして展開されていく。その複雑な心理の動き、高次の懊悩が著者の書きたかったことであるように思う。また、秀吉の側室となった妹龍子のお陰で大名として取り立てられていっただけではなく、高次という人物の持つ能力が評価されていった側面を著者は描こうとしているように感じた。
ある意味で、高次の生き様のプロセスは変節の繰り返しである。しかし、そこに信長、秀吉、家康と戦国期から天下統一期に向かう中で「家」の復興を大命題にする一大名の生き様が如実に活写されている。
一方で、秀吉との関わりが深まるにつれて、秀吉に対する高次の見方が多角化し、総合的に捕らえながら評価する形に、高次の秀吉観が変化していくところも描く。この点も興味深い。
高次は、大溝5000石からスタートし、九州の役後に5000石加増される。天正18年(1590)の小田原征伐の功により近江八幡の八幡山城28000石、文禄4年(1595)に大津城6万石に封じられ、近江国内を順次異動していく。大名として頭角を現していき、京極家復興を成し遂げることになる。
高次は妹・龍子という背景があるにしても、秀吉の下で着々と実績を積み上げていく。しかし、心の底には秀吉から「謀叛者」とみられているという事実を忘れず行動する姿を描く。その高次が、茶々とはつを預かるのは、本書によると天正11年5月から天正14年10月までのようだ。そして、秀吉の許しを得てはつを娶るのは天正18年12月だと記す。一方で、姉妹を預かっている期間中の比良嵐の夜に、高次がはつと結ばれるシーンを描写している。「いくたび、はつと秘かな夜を契ったであろう」(下・p133)とも記す。秀吉に対して用心を重ねながら行動する高次が、昔から思いを寄せる相手だったとはいえ、大溝時代にそこまで本当に踏み切っただろうか。秀吉に知られれば、京極家再興の潰える理由になる話だと思うのだが・・・・ただ、小説の展開としては、そこに高次のロマンを感じさせるところでもある。
武若と佐兵衛は、高次をまず頼ろうとするが流浪をつづける高次には会えず、沖ノ島湖族に加わり、そこに居られなくなると瀬田の湖族に潜り込む。その後、大溝城主となった高次を頼って行くが、清滝寺に潜むように言われてそちらに一旦落ちて行く。だが即座に出奔し、その後徳川方に加わり、秀吉への復讐を遂げる機会をねらおうとする。この二人の動きが、高次を悩ますことになる。その一方で、高次は武若の復讐一徹の心に動かされ、大我のためといえども変節した自分に内心忸怩たる思いを抱き続けるのだ。このあたり高次の人間性が描き出されている。
大津城という交通の要衝、当時の地政学的に重要な拠点を任された高次が、この城において関ヶ原の戦い前夜に果たした役割が最後の押さえ所となっている。秀吉亡き後の西軍と徳川家康との狭間に置かれた高次の処し方、ある意味最後のその変節が高次の人生、京極家を決定したといえる。ここがやはり本書の読みどころのように思う。
本書で特に印象深かった章句を引用しておきたい。
*高次殿、あんたは、生きねばならぬ。生きるということは、白い一本道をのんきに歩くことではない。迷い迷うて歩くのが生きるというものじゃ。・・・・みんな同じ心の人間じゃ。 上・p187
*小さい我を張っていては道にふみ迷う。小我を捨てて、大我に生きることが、世に出る者の根本義じゃ。・・・・眼を閉じて、大きく活眼をひらかれい。 上・p188
*人間、死んでしまえば、それでお終いではないか。生きてこそ、苦しみの解かれもする喜びが味わえるというのに。死によって解放されるのはずるいと思う。 上・p189
*強い者は、運命を甘んじてうけ、運命の中に自分を見出して生きてゆく。運命にさからうことはたやすい。自滅の道がたどりやすいようにの・・・・ 下・p181
ところで、本書を読みながらいくつか疑問点も湧いて来た。著者は、「若狭守護群記」をかなり参照しているようだ。この書を確認できないので、この書に由来する記述なのかどうか定かではないが、いくつか気になる点がある。
*本書には、大徳寺の山内塔頭として桂春院という名称が何度も出てくる(上・p178、下・p57他)。ネット検索した範囲で、現在の大徳寺の塔頭に桂春院を見いだせなかった。同名で現存するのは、妙心寺の塔頭の中にある。当時の大徳寺には、桂春院という塔頭が存在したのだろうか。この点、気になる。
(禅寺の徒弟経験のある著者にこの点での思い違いがあるとは思えないし・・・・。応仁の乱で大徳寺の伽藍が焼失し、その後復興されてから、大火災に遭ったという事実はネット検索した限りなさそうである。龍子が幾度も桂春院を訪れているという描写があるので、それなりの塔頭でもあるはずなのだが・・・)
*高次は秀吉の達しとして、大溝5000石を当初から得たように著者は記す。これは事実だろうか。ウィキペディアでは、「天正12年(1584年)に近江高島郡の2500石を与えられる。その後は加増を重ね、天正14年(1586年)には高島郡5千石、・・・」と記されているのだ。この箇所も、史実を確認できる資料がないので、客観的な事実はどちらなのかが気になるところだ。(歴史小説といえど、明確な史実は改変できないはずなので。もちろんその描写のしかたはいろいろあるだろうが・・・)
*高次は茶々・はつ姉妹を大溝に預かるために伏見に赴く。ここで、著者は「高台なので、宇治川と淀川が合流する観月橋のあたりが一望に見わたせた。・・・・京極高次は、天正11年5月30日に、この桃山城についている」(上・p339)と記す。この記述には疑問がある。観月橋、桃山城という用語の使い方は歴史小説としては史実にそっているのだろうか。
手許の『新撰日本史図表』(監修・坂本賞三、福田豊彦 第一学習社)を見ると、安土桃山時代という時代区分になっているが、城名としては「伏見城」で表記されている。現在観月橋という橋が存在する。だが、そこは秀吉が伏見城を築くにあたり、宇治川の流れを変え、改修して後に「豊後橋」を架けた位置である。秀吉の当時に、「観月橋」が通称としても使われていたのだろうか。(現在の橋名を使用するなら、それを読者にわからせる別の文章の書き方ができると思う。)
現在の観月橋に至る少し手前で2つの川が合流する。しかし、ここで合流するのは宇治川と山科川である。現在、合流後は宇治川と呼ばれている。石清水八幡社のある八幡あたりで、桂川・宇治川・木津川が合流し淀川と称されるようになる。あの当時、伏見の港あたりまで、淀川と称されていたのだろうか。そうとも思えないのだが・・・
また、伏見城の造営開始は「文禄3年(1594)1.3であり、8.1に秀吉、伏見城に入る」と、ある年表に記す。上記『図表』にも「1594伏見城なる」と記す。別資料では、文禄元年(1592)に「豊臣秀吉 伏見指月に隠居城の造営を開始」とある。著者の記す天正11年は1583年であり、これらの史実記録と食い違う。
このように疑問もいくつかあるのだが、最後にひとつ記録しておきたい。
本書のところどころに出てくる琵琶湖の状景描写が、それぞれの人の心理描写の一環にもなっていて、両面から興味を惹かれた。以下はその描写の一端である。
*今しも杉木立が割れて、扇子を半ばすぼめたような視界がひらけている。前方に白い空がみえる。いや、空ではなかった。空の色と見まがうばかりの湖の水面がのぞいているのだった。 上・p5
*黒一色の葦の平原の向こうに、いま巨大な丸鏡を置いたように光る湖面がある。 上・p89
*賤ヶ岳の東は、白い山襞が紺青の琵琶湖すれすれに落ちこんでいる。水ははるか南の彼方まで、まるで雪の上に紺青の染料をしたたらせたように鮮明に浮いていた。 上・p128
*長命寺裏のなだらかな丘陵が湖へつき出して、ぽつんと点のように沖島だけがみえる。 上・p129
*湖面は大溝の出鼻をとりまいて、半紙を敷いたように白かった。 上・p201
*折から五月の緑に囲まれた湖面は、藍を溶かしたように美しかった。 上・p210
*いつみても変わりないはずの琵琶の水が、今日は冷たく沈んでいるような気がした。 上・p313
*陽の輝きはじめた湖面は朱をとかしたような色の中で、こまかいちりめん皺を光らせはじめた。
下・p83
*湖面へ桟橋がつき出ていて、いま、暮色になずみはじめた水面に点々と魞のさし竹がういてみえる。 下・p111
*琵琶湖は山の奥の暗い湖じゃと思うておった・・・ 下・p112
*高次は、整然とひろがる町並みを眺めたあと、遠い湖面を見やった。冬の朝である。清澄な空気は、陽を受けて、いま橙色に湖面の小波を輝かし、遠い山影をくっきりとうかべている。 下・p258
琵琶湖の表情がおもしろい。
ご一読、ありがとうございます。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書を読みながら、関連語句とそこからの関心をネット検索してみた。
水上勉全集
勘六山房
京極氏 :ウィキペディア
京極高次 :ウィキペディア
京極龍子 ←京極竜子:ウィキペディア
武田元明 :ウィキペディア
京極家の菩提寺 清滝寺徳源院 :「近江の城郭」野暮氏
祥瑞庵 ← 祥瑞寺 :「一休さんのくにプロジェクト」
神宮寺 :小浜市
大徳寺 HP
大徳寺山内地図 :大徳寺HP
大徳寺塔頭 :「京都おもしろスポット」
妙心寺山内図 :妙心寺HP
桂春院 :ウィキペディア
妙心寺・塔頭 桂春院 :「京都を歩くアルバム」
大溝城/大溝陣屋 :「藤波イズム」
近江八幡城 :「ザ・登城」46(しろ)&光明子氏
近江八幡山城 :「近江の城郭」野暮氏
大津城 :ウィキペディア
大津籠城戦の八日間:「ランニング好きの研修トレーナーの日記」木村嘉伸氏
後瀬山城 :ウィキペディア
越前 北庄城(北ノ庄城) :「近江の城郭」
越前府中城 :「お城の旅日記」
堀秀政 :ウィキペディア
増田長盛 :ウィキペディア
淀川 :ウィキペディア
観月橋(豊後橋) :「ものシリーズ」
京都の豊後橋を知っていますか? :「民族学伝承ひろいあげ辞典」H.G.Nicol氏
巨椋池 :ウィキペディア
この中に、淀堤に触れています。
水坂峠 :「ORRの道路調査報告書」
水上勉の信濃を歩く :「東京紅團」
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
付記
この復刊版、巻末に「本文中明らかな誤植と思われる箇所は正しましたが、原則として底本に従いました。」(底本は『日本歴史文学館』14巻)としている。しかし、上下巻ともに、文章中に明らかに誤植と思われる箇所がかなり目についた。これはどこに問題があるのだろうか。ちょっと気になる。















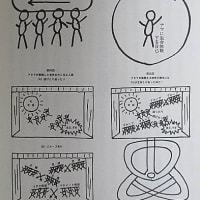




読了後、本書を見ながらまとめていたのですが、多分私の凡ミスなのでしょう。
今、該当箇所を再確認できない状態です。確認の上、原本が「海津」であれば、即座に訂正致します。
重ねて、御礼申し上げます。
さて、原本の確認とは別に、少しネット検索をしてみました。
以下、その結果の引用です。
水野氏史研究会
(1)名も無き戦国の牙城
http://mizunoclan.exblog.jp/9434734/
「これは戦国期に、近江国梅津西浜村(滋賀県マキノ町)から菅浦村(同県西浅井町)に出された書状である。」
(2)怨は忠義に勝れり
http://mizunoclan.exblog.jp/9474507/
「近江国梅津西浜村から菅浦村に出された援軍うかがいの書状」
義久一周忌
http://m.webry.info/d/blog.sasakitoru.com/200602/article_75.htm?i=&p=&c=s&guid=on
「法玉の父は六角氏被官の饗庭対馬守入道であり、北近江で自立した浅井亮政を牽制するため近江国梅津に在陣していた(24)。」
「若狭街道」を行く7 : 神戸あじさい紀行
http://ikesan.blog.eonet.jp/default/2010/08/7-a4e4.html
”西近江道は北陸道今庄を起点として南越の山、木の芽峠を
越え、敦賀の道ノ口で若狭の道へと分かれ、近江国に近い
山中宿を経て近江梅津に至る街道。
この街道は、北国の重要港敦賀から琵琶湖まで物資を輸送する
最短距離で敦賀・梅津間が七里半であったことから
「七里越え」といわれた。このみちは陸路梅津から湖西を経て
京に通じていたことから「西近江道」といった。”
親鸞聖人の生涯(9) :住職のつぶやき
http://www.shosenji.or.jp/tsubuyaki/shinran9.html
「島で一夜を明かされた聖人は、翌日再び小舟で湖上を北上され、今の滋賀県高島市マキノ町梅津に着かれました。梅津とは古くから北陸への湖上交通の要所として栄え、昔の書物にもその地名は再三出ておりますが、今は桜並木が続き、春は咲き誇る桜が湖面に生える観桜の名所とのことであります。」
「梅津」という表記で説明されている別の事例がありました。
国立国会図書館・近代デジタルライブラリー 国立国会図書館
を少し検索してみると、
近江郡町村里程便覧 中井久治郎 編 明28.9
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/765492
16/20 のコマに、
「高島郡海津村」の項に、「西濱」という地名が特記されています。
というのを見つけました。
このあたりに、ご指摘との関連がひょっとしたらあるのかもしれません。
あくまで推測の域を出ていません。
良い課題をいただき、ありがとうございます。
原本を遅ればせながら、先ほど確認できました。
本書では、上巻の冒頭「湖北悲愁」の章のp6に「海津は丹羽殿の御領地、・・・」、p8に「海津へ呼び出すのだったら」「海津に着いたのは」と記されていました。
やはり、私の単純ミスでした。
早速、本文の該当箇所を訂正いたしました。
中川様、ご指摘について改めて御礼申し上げます。
一方で、ネット検索でヒットした「梅津」と表記事例について、県立、市立、某大学の各図書館で関連書籍を調べてみました。しかし、現在までのところ、私自身では見つけ出すことができませんでした。