
源氏の故郷 鴻巣市 吉見町
NHKの12年の大河ドラマ「平清盛」をご覧になった方は、平安時代の後期に平家とか源氏とかの武士が台頭、保元の乱、平治の乱を経て、平清盛が権勢を握るに至る過程をご承知のことだろう。
保元の乱で崇徳上皇側について敗れた源氏の源為義、子の為朝(ためとも 鎮西八郎)、この乱では平清盛と組んで、父や弟を敵に回した為義の子で、為朝の兄の源義朝(よしとも)の名も覚えておられよう。
義朝は、3年後の平治の乱では、平清盛の失脚を狙い、破れて長男義平(悪源太)とともに殺される。
その義朝の遺児が、鎌倉幕府を打ち立てた源頼朝(三男)、後に頼朝に殺される異母弟の範頼(のりより 六男)、義経(九男)である。
まるで歴史のおさらいのようで申し訳ない。
「ふれあい鴻巣ウオーキング」のCコースを歩いていて、この源氏の面々の祖と範頼の旧跡があるのを初めて見て驚いた。
鴻巣市と比企郡吉見町は源氏の故郷なのだというのだから。
まずお目にかかったのが、「伝・源経基(つねもと)館跡」である。源経基とは何者か。
この館跡は、埼玉県指定史跡になっている。立て看板の説明によると
経基は、(平安時代初期9世紀後半の)清和天皇の皇子貞純親王の第六子で、弓馬の道に長じ、武勇をもって知られた。(臣籍降下で)源姓を賜って、「源朝臣(あそみ)」と称した。938(天慶元)年、武蔵介(むさしのすけ 後に武蔵守=むさしのかみ)となって、関東に下り、この地に館を構えた。
とある。清和天皇の孫というわけだ。
「城山」と呼ばれる山林で、森林公園になっている。発掘調査でも経基の館だという証拠は見つかっていない。
帰ってから調べてみると、「清和源氏」の中で、経基の子孫の系統が最も栄えた。ここに出てくる源氏の名は、いずれも経基の系統である。
Cコースの折り返し点は、吉見観音(安楽寺)。上る階段の脇に「蒲冠者(かばのかじゃ) 源範頼旧蹟」の石柱がある。
上ると立派な三重塔が立っていた。説明書には、「鎌倉時代、範頼は約18mの三重大塔と約45m四面の大講堂を建設した」とあった。
近くに範頼の館跡だと伝えられる「息障院(そくしょういん)」(写真)もある。この地には今でも、大字に「御所」という地名が残っている。
範頼は確か、義経とともに平家を滅ぼした後、頼朝に謀反の疑いをかけられ、伊豆の修善寺に幽閉されて殺されたはずではなかったか。
だが、吉見町のホームページなどによると、平治の乱で、一命を助けられた頼朝が伊豆に流され、義経が京都の鞍馬の寺に預けられた際、範頼は安楽寺に身を隠して、この地の豪族・比企氏の庇護を受けて成長した。頼朝が鎌倉で勢力を得た後も吉見に住んでいたと思われ、館の周辺を御所と呼ぶようになった、と書かれている。
範頼の子孫は五代にわたってこの館に住んでいて、「吉見氏」を名乗った。
範頼については不明なことが多く、吉身町の東側の北本市には、「範頼は生き延びて、北本市石戸(いしと)宿で没した」という説もある。
石戸の東光寺には、大正時代に日本五大桜の一つとされた天然記念物に指定された「蒲ザクラ」の一部が残っている。お手植えのサクラで樹齢8百年。根元にある石塔は、範頼の墓と伝えられる。
埼玉県内には、このような源氏ゆかりの旧跡がいくつかある。
NHKの12年の大河ドラマ「平清盛」をご覧になった方は、平安時代の後期に平家とか源氏とかの武士が台頭、保元の乱、平治の乱を経て、平清盛が権勢を握るに至る過程をご承知のことだろう。
保元の乱で崇徳上皇側について敗れた源氏の源為義、子の為朝(ためとも 鎮西八郎)、この乱では平清盛と組んで、父や弟を敵に回した為義の子で、為朝の兄の源義朝(よしとも)の名も覚えておられよう。
義朝は、3年後の平治の乱では、平清盛の失脚を狙い、破れて長男義平(悪源太)とともに殺される。
その義朝の遺児が、鎌倉幕府を打ち立てた源頼朝(三男)、後に頼朝に殺される異母弟の範頼(のりより 六男)、義経(九男)である。
まるで歴史のおさらいのようで申し訳ない。
「ふれあい鴻巣ウオーキング」のCコースを歩いていて、この源氏の面々の祖と範頼の旧跡があるのを初めて見て驚いた。
鴻巣市と比企郡吉見町は源氏の故郷なのだというのだから。
まずお目にかかったのが、「伝・源経基(つねもと)館跡」である。源経基とは何者か。
この館跡は、埼玉県指定史跡になっている。立て看板の説明によると
経基は、(平安時代初期9世紀後半の)清和天皇の皇子貞純親王の第六子で、弓馬の道に長じ、武勇をもって知られた。(臣籍降下で)源姓を賜って、「源朝臣(あそみ)」と称した。938(天慶元)年、武蔵介(むさしのすけ 後に武蔵守=むさしのかみ)となって、関東に下り、この地に館を構えた。
とある。清和天皇の孫というわけだ。
「城山」と呼ばれる山林で、森林公園になっている。発掘調査でも経基の館だという証拠は見つかっていない。
帰ってから調べてみると、「清和源氏」の中で、経基の子孫の系統が最も栄えた。ここに出てくる源氏の名は、いずれも経基の系統である。
Cコースの折り返し点は、吉見観音(安楽寺)。上る階段の脇に「蒲冠者(かばのかじゃ) 源範頼旧蹟」の石柱がある。
上ると立派な三重塔が立っていた。説明書には、「鎌倉時代、範頼は約18mの三重大塔と約45m四面の大講堂を建設した」とあった。
近くに範頼の館跡だと伝えられる「息障院(そくしょういん)」(写真)もある。この地には今でも、大字に「御所」という地名が残っている。
範頼は確か、義経とともに平家を滅ぼした後、頼朝に謀反の疑いをかけられ、伊豆の修善寺に幽閉されて殺されたはずではなかったか。
だが、吉見町のホームページなどによると、平治の乱で、一命を助けられた頼朝が伊豆に流され、義経が京都の鞍馬の寺に預けられた際、範頼は安楽寺に身を隠して、この地の豪族・比企氏の庇護を受けて成長した。頼朝が鎌倉で勢力を得た後も吉見に住んでいたと思われ、館の周辺を御所と呼ぶようになった、と書かれている。
範頼の子孫は五代にわたってこの館に住んでいて、「吉見氏」を名乗った。
範頼については不明なことが多く、吉身町の東側の北本市には、「範頼は生き延びて、北本市石戸(いしと)宿で没した」という説もある。
石戸の東光寺には、大正時代に日本五大桜の一つとされた天然記念物に指定された「蒲ザクラ」の一部が残っている。お手植えのサクラで樹齢8百年。根元にある石塔は、範頼の墓と伝えられる。
埼玉県内には、このような源氏ゆかりの旧跡がいくつかある。

















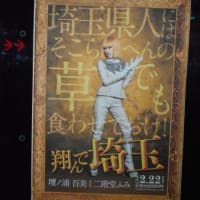


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます