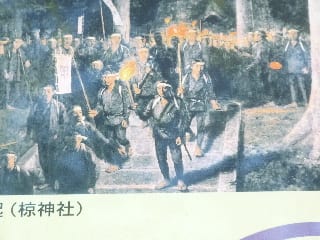「らき☆すた」 鷲宮神社 久喜市
11年の初詣には、いつものように近くにあるさいたま市の調(つきのみや)神社や氷川神社ではなく、茨城県境に近い久喜市鷲宮町の鷲宮神社へと足を延ばした。
景行(けいぎょう)天皇の時代に、日本武尊(やまとたけるのみこと)が造営したとされ、土器を作る部族である土師氏の祖神「天穂日命(あめのほひのみこと)」などを祭る。このため、「土師宮(はじのみや)」が「鷲宮」に変わったという。
関東最古の神社と言われ、関東のお酉(とり)様の元祖とされる。
藤原秀郷、源義家、源頼朝など関東の武将に尊崇され、徳川家康からも寺社としては別格の400石の朱印地を与えられている。川越市の喜多院の500石に次ぎ、武蔵一ノ宮の氷川神社の300石を上回っていた。今も源義家の駒つなぎの桜が残っている。中世から伝わる神楽「土師一流催馬楽(はじいちりゅうさいばら)神楽」が有名だ。関東神楽の源流とも言われる国指定重要無形民俗文化財である。
この神社にはかなり昔、車で出かけたことがある。約3トンと県内一の重さを誇る「千貫神輿」を見たことを覚えている。
1789年(江戸寛政年間)にできたもので、縦・横1.4m。担ぐのに1回180人が必要とのこと。毎年9月第1日曜日にお出ましになる。
元日に出かけたのは、この町がこの神社のおかげで「らき☆すた」ブームに湧きかえっているというからだ。
にわか勉強でネットを検索し、新聞をめくり、やっと「らき☆すた」とは、英語の「ラッキー・スター」(幸運の星)の略語と分かった。
埼玉県は幸手市出身(現在はさいたま市に転居)の原作者美水(よしみず)かがみさんが「マンガ界の幸運の星となれ」という願いをこめてつけた名前だという。その願いはみごと実現、「らき☆すた」は美水さんにも鷲宮町にも幸運を呼び込んだ。
ペンネームの美水かがみさんはその名前の響きからてっきり女性と思っていた。男性とのことだ。春日部共栄高校の出身だから、舞台になっている鷲宮神社も幸手のこともよく知っている。
それぞれ名前は変えてあるものの、漫画の中で主人公の二人は「柊かがみ・つかさ」という名の神社の宮司の双子の娘で、その友達は幸手に住んでいて、通っている学校は春日部となっている。
「神社は鷲宮神社で高校は共栄高校がモデル」と作者もインタビューで認めている。埼玉の東北部を舞台にした極めて地域性の強い4コママンガ漫画である。
「萌えアニメ」などという言葉も、もちろん知らなかった。 女子高生の日常生活をゆったりとコミカルに描いた漫画で、思わず「そうだ そうだ」とうなずいてしまうのが特徴だとか。
これが07年からテレビアニメになって「テレ玉」(てれび埼玉)など全国各地で放映されると、人気が爆発、6巻で合わせて300万部を超え、中国、韓国、タイ、英語版も出たという。
アニメ放映が始まった07年ごろから全国の「らき☆すた」オタクが鷲宮神社を聖地とみなし、人気スポットになり「聖地巡礼」の先駆けとなった。そのあげく、10年の初詣は前年の倍に近い30万人、13年には47万人に達した。47万人とは大宮氷川神社に次ぐ人出である。例年8万人前後だったという。
このアニメの監督を務めた竹本康弘さん(47)も、19年7月の京アニの放火事件の犠牲者になった。
その陰には、鷲宮商店会の努力もある。漫画、アニメの版権を持つ角川書店の協力も得て、ネットでファンを募り、売り出したキャラクター商品のデザインや価格なども話し合って決めた。
このファンとの交流がこのブームつくりに多いに役立ったようだ。神社の鳥居の前に古民家を改造して「大酉茶屋」をオープン、町も神社のアニメのキャラクターに「特別住民票」を発行した。
7月7日には「柊姉妹誕生祭」、9月第1日曜日に門前どおりで開かれる「土師祭」では、千貫神輿と並んで「らき☆すた神輿」も担がれる。
1日午後2時過ぎ、東武伊勢崎線鷲宮駅に降り立つと、「らき☆すた」の幟が目立つ通りに長い参拝の列が続き、最後尾では「お参りに2時間以上かかるのでは」とガードマン氏。
神社の鳥居近くでは、埼玉新聞が元日第2部特集の「サイタマニアでいこう!」を売っていた。作者とのインタビューなどが掲載されていて、この原稿でも大変お世話になった。
経済効果は14年までに約20億円と試算され、このような町おこしを進めた鷲宮商店会(齋藤勝会長)は、その功績を買われ13年11月21日、全国約1700商工会が加入する第53回商工会全国大会で、最も顕著な実績を挙げた商工会に贈られる「21世紀商工会グランプリ」を獲得した。
このブームは、たとえ観光資源は乏しくとも、何か核になるものとアイデアさえあれば、新しい資源を開発できることを教えている。問題はこのブームがいつまで続くかである。