
古墳と言えば、ヤマト王権の所在地大和地方や宮崎県などが頭に浮かぶ。ところが、古墳時代後期には、鴻巣市東裏の生出塚(おいねづか)遺跡に東日本最大級、国内でも屈指の埴輪生産遺跡が発見されているとおり、古墳の中心地は東日本だったようだ。
県北の本庄市では、かつて2百基近くの古墳があったというから、古墳の付属品である埴輪の出土も多い。
その中でも1999年に古墳時代後期(6世紀後半)の「前の山古墳」(同市小島、現在は消滅)から出土した「笑う埴輪」3基は、12年にパリの日本文化会館で開かれた「笑いの日本美術史 縄文から19世紀まで」展に出品され、全国的な話題になった。
この展覧会は07年、「東京の森美術館」で開かれ、30万人が訪れた「日本美術が笑う」展を基にしたものだった。
13年8月末、久しぶりに本庄市を訪ねた帰りに、市立歴史民俗資料館を訪ねたら、この3基を中心とする笑う埴輪にお目にかかれた。
身長110cmを超すこの埴輪は、いずれも身体の前面に盾を抱えているので、「盾持人物埴輪」と呼ばれる。埴輪には人物のほかに、動物、家、家具などを象ったものもあれば、人物でも、力士、貴人、琴弾きなど多種多様の形のものがある。
盾持埴輪は、普通の埴輪の二倍の大きさ。盾で悪霊を古墳から守るため、顔は他の人物埴輪より大きく造られ、威圧的な風貌のものが多いという。大きくて恐い顔をしているのが普通なのだ。
3基の盾持埴輪で見て驚くのは、①丸い両耳が大きく突き出している②鷲鼻が突き出している③顎がしゃくれているーーことである。
それに、三日月型の目の目尻が垂れ、口が横に長く大きく開き、まるで笑っているような印象を与えるのだ。目尻が下がり、口角がちょっと上がっているからだ。
盾に隠されているので、腕や手は見えない。脚も円筒状になっているので無い。埴輪は、目はくり抜いてつくるので、瞳がない。これは世界的にも珍しい目の表現方法だという。
埴輪にはもともと歯が表現されないのに、どういうわけか、この3基には石などで歯を表現した跡があるらしい。本庄市の坊主山古墳や高崎市で出土した埴輪にも歯があるが、全国でも珍しいという。
「歯をむいて笑う」姿を表したのかなと思った。資料館でもらった「笑っている埴輪たち、集合」の図を見ると、歯はあっても笑っていない埴輪(高崎市)もある。
笑っているような埴輪は、盾持ちではないものの、群馬県太田市、茨城県高萩市でも出土している。
本庄市ではこの3基のほか、坊主山古墳の前述の歯付き埴輪、山ノ神古墳の埴輪(いずれも盾持ちではない)も明らかに笑っているようだ。
「全国的に本庄市内に最も集中している。本庄市は笑う埴輪の里だ」と、市立民俗資料館の館長を務めていた増田一裕氏は、本庄市のはにわ展の解説で書いている。この原稿の多くは、その解説によるところが多い。
本当は恐い顔のはずの埴輪が、なぜ笑っているのか、
思いつきながら、「笑う」には、面白、おかしいから笑うという以外に、「馬鹿にして笑う(嘲笑する)」という意味もある。「笑殺(笑って問題にしない)」とか「一笑に付す」「笑い飛ばす」という言葉もある。
古墳に忍び寄る悪霊など、恐い顔ではなく、「笑いの力で打ち払ってしまえ」という願いが込められているのかもしれない。
慣習を打ち破った、当時の前衛的な埴輪造りに聞いてみたいものである。1400年の時を経て、この謎への回答が迫られているような気がする。
「笑う埴輪」は、埴輪の「はに」、本庄市の「ほん」を取った本庄市のマスコット・キャラクターの「はにぽん」のモデルになり、市民にも親しまれている。
県内では1930(昭和5)年、熊谷市の野原古墳群から「踊る埴輪(男女立像)」が出土している。
左手を上げたポーズから「踊る埴輪」が定説になっていたが、最近、「馬子が馬を曳いている姿」説が有力になっているという。
本物は、重要文化財として東京国立博物館に展示されている。地元の県道深谷・東松山線にかかる押切橋南の小さな公園には「踊る埴輪」のレプリカが立ち、親しまれている。

















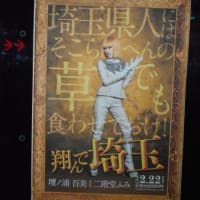


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます