寺山修司の写真ワークスの展示があったので行ってきました。
「写真屋・寺山修司/摩訶不思議なファインダー」展
@BLD GALLERY
もう第1期の展示は終わってしまったようですが、年明けから第2期が始まります。(1/9~2/28)
寺山修司についてはいろいろと知っている割にはよく知らないのですが(なんじゃそりゃ)短歌や映画や芝居やとくれば当然写真だってやっているだろうに、あまり寺山の写真というのは意識したことがなかった。
で、それなりに想像して向いましたですよ。あの天井桟敷みたいな面々が、異形・奇形をさらしつつ廃墟とか場末とかいう雰囲気のところでポーズをとっていることだろうと。
で、行ってみたら・・・まったくそのとおりのイメージが並んでおりました^^;
期待通りなんですけれど、期待通りにしても一定水準のインパクトがあるだろうと踏んでいたのですが、意外にも、写真としての彼らは、おとなしく、企図され、予定調和的にフレームに納まっていたのです。
もしかすると写真においてはその枠組破壊的な寺山パワーはそがれてしまったのかもしれません。とするとこれは結構由々しき問題で。何故写真だけがかれの想像/創造の発露をかくもたやすく馴致してしまうことができるのか?これはよく考える必要がありましょう。。
同じようなイメージであっても、横尾忠則や丸尾末広の提示する画像のほうがその禍々しさに満ちています。やはり絵というものは想像力の本質をぐっとつかむことができるのでしょうか。必要なものは描き、不必要なものは排除する。意識無意識の強権が表現をコントロールします。
しかし写真というものは、どんなに構図や被写体を選ぼうとも、そこには意図するもの以上の情報を含んでいます。ロラン・バルトを引くまでもなくそれこそが写真のもう一方の深淵でもあるわけですが、寺山はその写真の深淵に踏み込むことを意識していなかったのではないかと思われます。あの寺山とあろう人が、あくまで選んだ構図、選んだ被写体、選んだ表現内容としての写真を追求してしまった結果が、このなんともいえぬワタシのちょっとした落胆なのではないでしょうか。
それが証拠に(?)パネルの写真とは別に、写真をいろいろな素材(色紙、銀紙、あるいは写真を壁面や人物などに映写したものを再度撮影、等)で変調した試作物が展示されていましたが、そちらの、写真から離れていった作品群のほうがよほど面白かったのですから。
・・と思いつつも、一方では、これまたバルトがいうように、写真の深淵が口開くのはとことん個人的な体験である、ということも思い出しています。今回のワタシの失望は、寺山ばかりに問題があるのではない。ワタシの個人的な像体験として成立しなかっただけ、でもあるのでしょう。
なので、観る人によっては、トラウマのようにあれらの写真を見ることができるのかもしれません。
写真は面白く、ときに近寄りがたい。
****
とかいいながらこれは購入しました。
バルトの名著
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ
↑なにとぞぼちっとオネガイします。
「写真屋・寺山修司/摩訶不思議なファインダー」展
@BLD GALLERY
もう第1期の展示は終わってしまったようですが、年明けから第2期が始まります。(1/9~2/28)
寺山修司についてはいろいろと知っている割にはよく知らないのですが(なんじゃそりゃ)短歌や映画や芝居やとくれば当然写真だってやっているだろうに、あまり寺山の写真というのは意識したことがなかった。
で、それなりに想像して向いましたですよ。あの天井桟敷みたいな面々が、異形・奇形をさらしつつ廃墟とか場末とかいう雰囲気のところでポーズをとっていることだろうと。
で、行ってみたら・・・まったくそのとおりのイメージが並んでおりました^^;
期待通りなんですけれど、期待通りにしても一定水準のインパクトがあるだろうと踏んでいたのですが、意外にも、写真としての彼らは、おとなしく、企図され、予定調和的にフレームに納まっていたのです。
もしかすると写真においてはその枠組破壊的な寺山パワーはそがれてしまったのかもしれません。とするとこれは結構由々しき問題で。何故写真だけがかれの想像/創造の発露をかくもたやすく馴致してしまうことができるのか?これはよく考える必要がありましょう。。
同じようなイメージであっても、横尾忠則や丸尾末広の提示する画像のほうがその禍々しさに満ちています。やはり絵というものは想像力の本質をぐっとつかむことができるのでしょうか。必要なものは描き、不必要なものは排除する。意識無意識の強権が表現をコントロールします。
しかし写真というものは、どんなに構図や被写体を選ぼうとも、そこには意図するもの以上の情報を含んでいます。ロラン・バルトを引くまでもなくそれこそが写真のもう一方の深淵でもあるわけですが、寺山はその写真の深淵に踏み込むことを意識していなかったのではないかと思われます。あの寺山とあろう人が、あくまで選んだ構図、選んだ被写体、選んだ表現内容としての写真を追求してしまった結果が、このなんともいえぬワタシのちょっとした落胆なのではないでしょうか。
それが証拠に(?)パネルの写真とは別に、写真をいろいろな素材(色紙、銀紙、あるいは写真を壁面や人物などに映写したものを再度撮影、等)で変調した試作物が展示されていましたが、そちらの、写真から離れていった作品群のほうがよほど面白かったのですから。
・・と思いつつも、一方では、これまたバルトがいうように、写真の深淵が口開くのはとことん個人的な体験である、ということも思い出しています。今回のワタシの失望は、寺山ばかりに問題があるのではない。ワタシの個人的な像体験として成立しなかっただけ、でもあるのでしょう。
なので、観る人によっては、トラウマのようにあれらの写真を見ることができるのかもしれません。
写真は面白く、ときに近寄りがたい。
****
とかいいながらこれは購入しました。
 | 写真屋・寺山修司―摩訶不思議なファインダーフィルムアート社このアイテムの詳細を見る |
バルトの名著
 | 明るい部屋―写真についての覚書ロラン バルトみすず書房このアイテムの詳細を見る |
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ↑なにとぞぼちっとオネガイします。















 amazon
amazon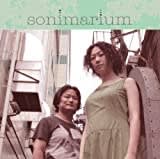 amazon
amazon
あれは制約された中できらっと光る才能が表れていたような記憶があります。写真ももしかするとそれに近い正統派なものではないかと想像しました。
写真の制約が無条件の被写にあるとすると、寺山の作品はそれにあまり意識が行っていないように思えました。意図したものだけが写るのだと錯覚しているかのような。
歌の場合は確かに制約が言葉を輝かせているでしょうね。歌集を持っています。