
 アンドレイ・タルコフスキー「鏡」の本
アンドレイ・タルコフスキー「鏡」の本馬場広信:監修 宮澤淳一・馬場広信:訳
リブロポート1994
入手したてのほやほや。

アンドレイ・タルコフスキーの映画「鏡」に関する
丁寧な資料集成です。
シナリオ詳細の採録、監督の作業ノート訳、構想段階のヴァリアント、当局への申請書、派生した小説訳、映画で使用された詩、映画のスティル写真、プライベート写真、等々・・・
大変な労作であり、海外HPなどでも評価が高いようです。
が、リブロポートは出版部門が撤退したとのことで、現在は入手が困難、再販も望み薄なようです。
偶々監修者のHP経由で入手可能ということを知り、以前申し込んでいた物が
昨日届いたというわけです。
なにはともあれうれしい!というのが今の私。
本の厚み、装丁の渋さ、図版の美しさ・・・私にとって本は「読む物」の前に「愛でる物」なのです。わたし絶対に本フェチです。電子図書なんてきらいです。
なので愛でるだけで終わっている本もままありますが・・・
・・・で、話戻すと、
タルコフスキーに関しては、意外と資料という形で整理された物は少ないと感じています。
映画の内容からして、あたかも神話か何かのように「解読」をしようとする研究書が
多いのではないかな。
この本は、「鏡」の制作に関して残された物を集めて、映画作家としてのタルコフスキー、映画としての「鏡」をもっと清濁あわせて研究できるようにという、うたい文句通りの資料集。
監修者の馬場氏は、非営利のアンドレイ・タルコフスキー協会およびアンドレイ・タルコフスキー出版会を設立し、この本の制作に7年を費やしたとのことで、高い志を感じます。
あとがきには、この本の売れ行きによっては「「ストーカー」の本」なども次の企画として出せるので、購入者はお友達等にすすめてくれ、という主旨のことが書かれている。
ああ、やはり出版当時に購入すべきだったのだ。
現状ではリブロポートは撤退し、「「ストーカー」の本」には出会えていない。
「ストーカー」の本、「ソラリス」の本、「ノスタルジア」の本・・なんてそろえたら
私は失神してしまうでしょう。
今からでもできることがあったら、その実現にむけて協力しよう!
しかし!
馬場氏・宮澤氏とも、現在は各分野の評論等でご活躍されていますが、
調べてみるといずれも私より年下でした。(^^;)敬服のほかありません。
***
映画の方は、最初に観たときは例によって途中数カ所で
すやすや眠ってしまったせいかピンときませんでした。
でもDVDで先日観直した時にはとてもしっくりきました。
おそらくタルコフスキーの作品のなかでもいちばん個人的・独白的なものであり、
とっつきにくく、「独善的」とかいわれてしまうものだと思います。
でも回を重ねることによって、意外に筋が通っており、深く入り込むことができるものだと感じました。
登場する少年の視点に立ってみれば、納屋の火事のこと、髪を洗う母の姿、叔母?の家を訪ねたときのこと・・など、断片的な、でも甘く切なくつながっている物語を、誰もが持っているんじゃないかと思う。
今回この資料集を得たことで、たとえば映画の中で、監督の母の写真が使われているなどの
情報を得ることができた。
もう一度じっくり観てみよう。

でもDVD版には、画面の明るさやサウンドトラックなどで、オリジナル版との差異の問題があるらしい。このへんもちゃんと踏まえておかないといけない。
一般的には字幕にもしばしば誤りがあるケースもあるらしいし、DVD観るのも楽じゃないなあ。















 amazon
amazon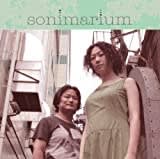 amazon
amazon
まあ、「見なくては…」という強迫観念で見ても仕方ないとも思いますし、自分の精神的な脆弱さをここで披露するのもおかしな話ですね。
Mani_Maniさんがこちらで採り上げられる映画や、バッハなどの音楽は、私にとって「高尚なもの」という感じに映るのですが、Mani_Maniさんにとっては純粋にエンタテインメントなのでしょうか。
芸術的なものに触れる場合、嫌悪や苦痛をともなうこともあると思うのですが…。
ところで、Mani_Maniさんも「本フェチ」だとか。
私とまったく同じ症状をお書きになっているので、ついヒザを打ちました。
私も本について書いている記事がありますので、トラックバックさせていただきました。
もちろん、例によってMani_Maniさんの裁量で削除していただいて結構です。
うーんあまり考えたことがなかった(^^;)。若干の「高尚なもの」コンプレックスがあるのを認めつつですが、自分の性格は「落ち着くもの、心安らぐもの」に惹かれるのだと思います。一方で「ちょっと探求する」のが好きなのです。
なのでたとえばバッハですと、聴けばこころ安らぎますし、探求して向き合えば大きな対象です。
だからここちよく接しているという点ではエンタテインメントとしていると言っていいんだと思います。
作家性の高いもの、という点で考えると、バッハはその題材や作品の様式美の高さから、むしろ作家性は薄く、作品の完成度が高いんだと言えると思うんです。モーツアルトなどは作品の完成度も高いですけど作家の個性がぷんぷんしますよね、そういうのはあまり好みません。作家性の高いものにふれるときの苦痛はむしろ避けて歩いているのかもしれません。
うまく答えられませんが・・・
といいつつ、私もどっちかというとロックばっかし聴いて育ったクチでして、いまではスピッツのファンだったりMISIAのファンクラブ会員だったりするんです(笑)
ただ、お察しとは思いますが私もいま弱っている時期でありまして(^^;)でブログもバッハとかに偏っているんだと思います。
TBは基本的に歓迎です。