5月11日~22日(月)
没後初の回顧展ということで、初期の絵画作品にはじまって、ニキの創作の軌跡を追った展示だった。

有名な「NANA」のシリーズを見るといつも「土偶」と思ってしまう。
大地豊穣の母、グレートマザーのイメージ。
しかしこの豊穣は、伝統社会や文明のなかで培われたものではない。
ニキという個人の内面を徹底的に掘り下げた結果出てきた物なのだ。
そこがすごいと思う。
神経症からの癒しとして描かれた初期の絵画から、
グロテスクなオブジェ、射撃絵画といった前衛の時代を経て、
NANAに代表されるポップでユーモラスな立像へ。
その軌跡は、内面の吐露から、それの破壊、そして再構築、その絶えざるくりかえしだったのだ。
特に前衛の時代は壮絶だ。内面にかなりぐちゃぐちゃ詰め込まれたものがあって、しかもそれを一度ならず何度か打ち壊しては再構築していったんだなあ、とそんな印象だ。
また、「力」というリトグラフのシリーズがあって、獰猛な竜に手綱がついていて、それを女性が握っている絵柄のシリーズ。
女性(=自分)の内面には獰猛な竜がいて、女性は御しがたいそれをなんとか手なずけていく、という構図は、
ニキの内面の激しさとともに、それを自覚しつつ、ポップで包容力のある作品として昇華していった彼女のしたたかさを感じさせた。
夫となったジャン・ティンゲリのことば、「技術ではない、夢こそが全てだ」という言葉のみに勇気づけられて、原初の衝動やただひたすら自分自身をみつめることによって、自由な女性としての豊穣や成熟の表現を、ひとり黙々と発見し表現していったニキの軌跡がよくわかる展示だった、という点ではなかなか成功した回顧展ではないかしら。
ただ、大型の作品の数が少なく、物足りない。
会場のキャパの問題もあろうが、神秘的でユーモラスでもある古代の神々の像とかがあったらもっと全体像がつかめただろうと想像する。
まあ、また機会があったら那須に出向くのもいいかも。

































 amazon
amazon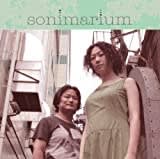 amazon
amazon