 | ベートーヴェン:交響曲第9番 |
| ベーム(カール),ジョーンズ(ギネス),トロヤノス(タティアーナ),トーマス(ジェス),リッダーブッシュ(カール),ウィーン国立歌劇場合唱団,ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| ユニバーサル ミュージック クラシック |
ベートーヴェン交響曲第9番 カール・ベーム+ウイーンフィル+ウイーン国立歌劇場合唱団
ベームはやはりウィーンフィルと録音したブラームス全集で好印象を持っているのと、たぶん75年の来日公演を放映したものの録画をよく観ていた。ベト7だったな。録画では老齢の指揮者が指揮台の手摺りにもたれながら手先をひょいと動かすと、ジャン!!と壮麗な音がするので可笑しかったが、演奏は素晴らしく、指揮者とオケの阿吽の呼吸の妙技を堪能したもんじゃ。
この第9はベームの最初のベートーヴェン全集からの分売ということのようです。
信頼と期待を持って聴き始めたのですが、おや?第1楽章冒頭の激しいテーマがどうも粗いというかユルイ気がする。ふむむ。
ユルイというかちょっと放埓な感じで第1楽章前半は過ぎてゆく。このところかっちりしたきびきび系ばかり聴いているせいでそう聴こえるのか?
テンポはベームにしては中庸。なんとなく冒頭の違和感をひきずりつつも中盤からはさすがに豊かな響きを見せつつ終える。
冒頭リズムの甘い感じはどうもホルン隊のせいかもしれんな?と感じスコアで追ってみる。
オーボエがなんかぺらぺらな紙のような音なのは録音のせい。
第2楽章は走り出しゆったりめのテンポ。このくらいのテンポも好きだな。特に自分が弾く場合はこのくらいが平和だ(笑)
第2楽章の中盤からすこしテンポアップするが、そのあたりから急にオケの締りがよくなってくるような気がする。これこれ。これが聴きたい。こうなると律儀な繰り返しも冗漫に感じない。いいねえ。
第3楽章はさすが堂々としたものだ。ゆったりしたテンポの中にしっかりセクションごとのうねりを作り出している。1stVnが奏でる変奏メロディがあわてず落ち着いている裏で、管楽器が和声の壁をつくるシーン、管楽器の抑揚がよくコントロールされていてグルーヴ感がある。こういうバッキングが実にかっこいい。
例の4番ホルンも申し分ない(まあもうちょっとボリューム感があってもいいかもですが)
しかし、うーんと感心したのはやはり第4楽章だった。音楽様式のパノラマのような曲だが、とくに二分音符を1拍とするようなバロック以前の古風な書式による部分などは、遅~いテンポで一音一音丁寧に紡いでいく。じっくりそれを聴いているとなにか一種の行のようだ。響きを受け止めているうちに長い音楽史をそっくり包み込んだまま天とつながっているようななにやら神秘的な心地すらする。
感動とはまた違う、じっくり内省の末の境地という感じはやはりベームらしいという気がする。と同時に、この第4楽章の持つ力の底知れなさを知らしめる演奏でもある。すごい曲だよなあ。ほんとに。
***
録音にときおりふっと断絶感があるのは、つないだ部分なのかなあ?とてもここでは繋げないだろう?というところでも感じることがあるのだが。
つないでいるとしても、全楽章通じて最初から通しで演奏しているような、終盤へ向けての意志の持っていきかたを感じるところはよくできているのだが。













 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ














 amazon
amazon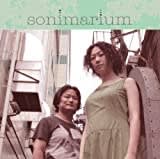 amazon
amazon