いや~~~~~~~~~~~~~~~っ!
行ってきました
聴いてきました
観てきました
サイモン&ガーファンクル来日公演@東京ドーム!
なにしろあのビッグネームが
伝説のデュオが
栄光の60年代が
目の前で(いや、遠かったですけど)
歌っているのです。
往年の名曲を
それぞれのソロ曲を
サイショは嬉しかったんですけれど
終盤はその希有な時間を持てたことに感極まり
「明日に架ける橋」を歌い上げた二人の姿に思わず涙してしまいましたよ。
なんだかんだとやはりいいですよS&G
二人とも声質は多少変わっていはいるものの、
歌の「良さ」の部分はまったく変わっていないという印象でした。
質は少し変わっても、アーティーはまちがいなくアーティーでしたし、
ポールはどうしようもなくポールでありました。
そのおとろえのなさにまずは感心しました。
まあ、容姿はしっかり衰えてましたけどね
(特にポール(笑)アートはわりと歳取ってない)
ライブDVDやCDを聴くと、同じ曲でも毎回少しずつ歌い回しが違っていて、
どれだけリハをするのかわかりませんが、その違いを少しも外す事なくしっかりハモる呼吸の合い方もまた感動的です。
曲折ありとうの昔に解散した彼らですが、ときおり再結成してきかせる息の合ったハーモニーは、二人のつよい結びつきを感じますね~
というわけで、バックバンドを従えて、あるいはポールのギター1本で、と多彩に構成された刺激的なステージでした。
***
まだツアー中なのでセットリストは後日~
といってもソロ作品はあまりおさえてないので
分からない曲も何曲かアリ
事前に勝手に「やるかも/やってほしい/やってほしいけどたぶんやらないだろうリスト」をつくってCD焼いたりしてたんだけど、なかなかジャストミートな選曲でしたよ^^
ちょっとマイナーな曲もリストに入れたら、ちゃんとやってくれましたし。
特に終盤やったあれとかね
終盤からアンコールの選曲はそれはもう滂沱という感じで;;
そういや席の後ろのほうで、始まる前にアンコールの曲目を同伴者に教えているヤツがいて
非常に迷惑でした^^;
そういうのは知っててもクチにしちゃいかんでしょうに。。
それもいい歳した大人ですよ
で、お客さんの年齢層、高め~~(笑)
もちろん当然ですけどね。
なかにあんまり若い子が混じっていると、だれか孫を連れてきたんかい?みたいな世代ですよね~
ビートルズなどとちがってS&Gはいまいち若い世代に浸透していないような気もするので、頑張ってほしいです(誰が何を?)
****
【追記】
ようやくセットリストをあげても良さそうです。
アートとポールのソロには知らない曲もあったので、
あちこちのwebのリストを参考にしました
曲順もね。
01. Old Friends ~ Bookends Theme
02. Hazy Shade of Winter
03. I Am a Rock
04. America
05. Kathy's Song
06. Hey Schoolgirl
07. Be Bop A Lula
(ここらへんは若い時はこんなのやってましたという雑談の中で歌われましたね)
08. Scarborough Fair
09. Homeward Bound
10. Mrs Robinson
11. Slip Slidin' Away
12. El Condor Pasa
(Garfunkel solo)
13. Bright Eyes
14. A Heart in New York
15. Perfect Moment ~ Now I Lay Me Down to Sleep
(Simon solo)
16. Boy in the Bubble
17. Graceland
18. Still Crazy After All These Years
19. Only Living Boy in New York
20. My Little Town
21. Bridge Over Troubled Water
(アンコール)
22. Sound of Silence
23. The Boxer
24. Leaves That Are Green
25. Cecilia
いや~
なかでもおっと思った選曲はKathy's SongとOnly Living Boy in New Yorkでしょうか。
ポールのソロでうたわれる前者は前半に出てきて、やっぱりこのうたは彼にとっては大事な歌なのでしょう
from shelter of my mind
through the window of my eyes
I gaze beyond the rain-drenched streets
to England where my hearts lies
ってとこが好きです。rainってのがね
後者は、勝手に青のイメージのある曲だと思っていたら
照明も青っぽかったので、おお~という感じでした。
なんか飛行機が出てくる歌ですね。
スゴい好きな歌だ。
あとは、The dangling conversationとか、song for the askingとかがあったら最高だな。
そうそう、演奏陣もそうとう年齢層高めだったんだけど(笑)
けっこうすごかった。
ギターのおじさんはと中チェロやケーナなどもプレイして目立っていた。
キーボードプレイヤーは1曲だけテルミンを弾いていた。ボクサーの間奏の旋律をあれでやっていたんだけど・・・う~む、あれだけのためにテルミンか!!
【追記終わり】
***
スタジオ盤
どれも名盤ですが、ワタシは後期に行くほど好きですね。
あと、このライブアルバムがすごくいい!
↓
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ
↑なにとぞぼちっとオネガイします。




 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ



























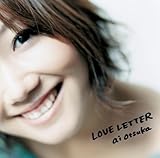












 amazon
amazon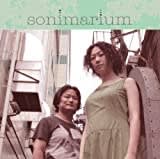 amazon
amazon