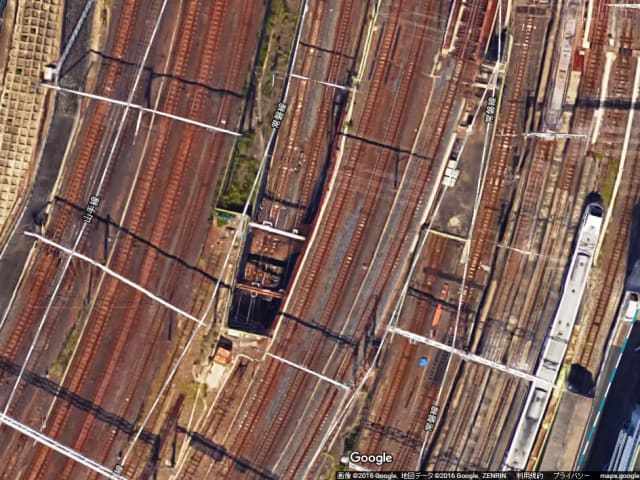こんにちは。新年度がはじまりました。と言ってももう3日ですが・・・汗
年度が明けたら仕事もラクになる予定だったんですが、なんだかんだで引きずっていて模型三昧というわけにはいきません。残念!
こういうモンモンとした心理に巧みに入り込んでくるのがポチリの誘惑ですね。
先日ブラス電機の大きな買い物をしてしまったばかりなのに、まあ発売はまだ先だからいいか♪みたいなノリで、富の153系の予約注文を入れてしまいました。
東海道筋のクモニ付きフル編成をいきたいところですが、あまり散在ばかりできないのとMyレイアウトの規模を考え、房総急行の7連を再現すべく基本+増結(M)+サロという陣容でオーダーした次第。

さて、そのレイアウトの方ですが“初鹿野ライクなセクション”の「のり面保護工」に着手すべく、石粉粘土で地面の塗り重ねをしたところ、乾燥したらこのようなひび割れが数か所発生してしまいました。練る際に水分を多めに含ませた影響と思われますが、下地が吸水性抜群のクッキングペーパーだったため急速に吸水されてしまったのも一因かも知れません。山肌も実際はもう少し大きな凹凸があるようなので、その表現も兼ねてさらに粘土を盛り付けて補修したいと思います。

ついでにいくつか不満のある個所を修正することにしました。これは山側の犬走り部分の路盤用マットをカットしているところ。このままだとバラストを撒いた時に扁平になってしまうので、しっかり“盛り上がり”感を出すために掘り下げることにしました。そのままにして実感的でなくなってしまった場所が何か所もあるので、せめてメインの見せ場は雰囲気を壊さないようにということで・・・


こちらはセクションの端部。フレキの枕木の間が接着剤で埋まってしまっていたので、部分的に枕木を抜いて新しいものに差し替えているところです。樹脂マットへフレキの固定は、防音・防振効果をなるべく消さないように接着剤をメインに、小クギをサブで使用しているのですが、この端部のように、なるべくズレが生じないようにしたい部分は「接着剤過多」になる傾向があり、バラスト散布前の除去に苦労しています。。

そして補修最大のヤマ場はこれ。つまずいて転んだ拍子に山に手を突っ込んでしまいまして・・・泣
軌道面まで貫入しなかったのが不幸中の幸い。新聞紙とクッキングペーパーの貼り重ねでなんとか補修できそうです。

バラスト撒きは粛々と・・・と言いたいところですが、いささか煮詰まってきて根気が続かなくなっています。以前はこのくらいの区間は2回くらいで撒いてしまったのですが、今では「とりあえず片側だけ・・・」というありさまで。。

ということで、忙しいなりに少し時間ができてくると思うので、レイアウトと並行して車両工作も少しずつ再開したいと思います。
よろしければ1クリックお願いします。
 にほんブログ村
にほんブログ村
年度が明けたら仕事もラクになる予定だったんですが、なんだかんだで引きずっていて模型三昧というわけにはいきません。残念!
こういうモンモンとした心理に巧みに入り込んでくるのがポチリの誘惑ですね。
先日ブラス電機の大きな買い物をしてしまったばかりなのに、まあ発売はまだ先だからいいか♪みたいなノリで、富の153系の予約注文を入れてしまいました。
東海道筋のクモニ付きフル編成をいきたいところですが、あまり散在ばかりできないのとMyレイアウトの規模を考え、房総急行の7連を再現すべく基本+増結(M)+サロという陣容でオーダーした次第。

さて、そのレイアウトの方ですが“初鹿野ライクなセクション”の「のり面保護工」に着手すべく、石粉粘土で地面の塗り重ねをしたところ、乾燥したらこのようなひび割れが数か所発生してしまいました。練る際に水分を多めに含ませた影響と思われますが、下地が吸水性抜群のクッキングペーパーだったため急速に吸水されてしまったのも一因かも知れません。山肌も実際はもう少し大きな凹凸があるようなので、その表現も兼ねてさらに粘土を盛り付けて補修したいと思います。

ついでにいくつか不満のある個所を修正することにしました。これは山側の犬走り部分の路盤用マットをカットしているところ。このままだとバラストを撒いた時に扁平になってしまうので、しっかり“盛り上がり”感を出すために掘り下げることにしました。そのままにして実感的でなくなってしまった場所が何か所もあるので、せめてメインの見せ場は雰囲気を壊さないようにということで・・・


こちらはセクションの端部。フレキの枕木の間が接着剤で埋まってしまっていたので、部分的に枕木を抜いて新しいものに差し替えているところです。樹脂マットへフレキの固定は、防音・防振効果をなるべく消さないように接着剤をメインに、小クギをサブで使用しているのですが、この端部のように、なるべくズレが生じないようにしたい部分は「接着剤過多」になる傾向があり、バラスト散布前の除去に苦労しています。。

そして補修最大のヤマ場はこれ。つまずいて転んだ拍子に山に手を突っ込んでしまいまして・・・泣
軌道面まで貫入しなかったのが不幸中の幸い。新聞紙とクッキングペーパーの貼り重ねでなんとか補修できそうです。

バラスト撒きは粛々と・・・と言いたいところですが、いささか煮詰まってきて根気が続かなくなっています。以前はこのくらいの区間は2回くらいで撒いてしまったのですが、今では「とりあえず片側だけ・・・」というありさまで。。

ということで、忙しいなりに少し時間ができてくると思うので、レイアウトと並行して車両工作も少しずつ再開したいと思います。
よろしければ1クリックお願いします。