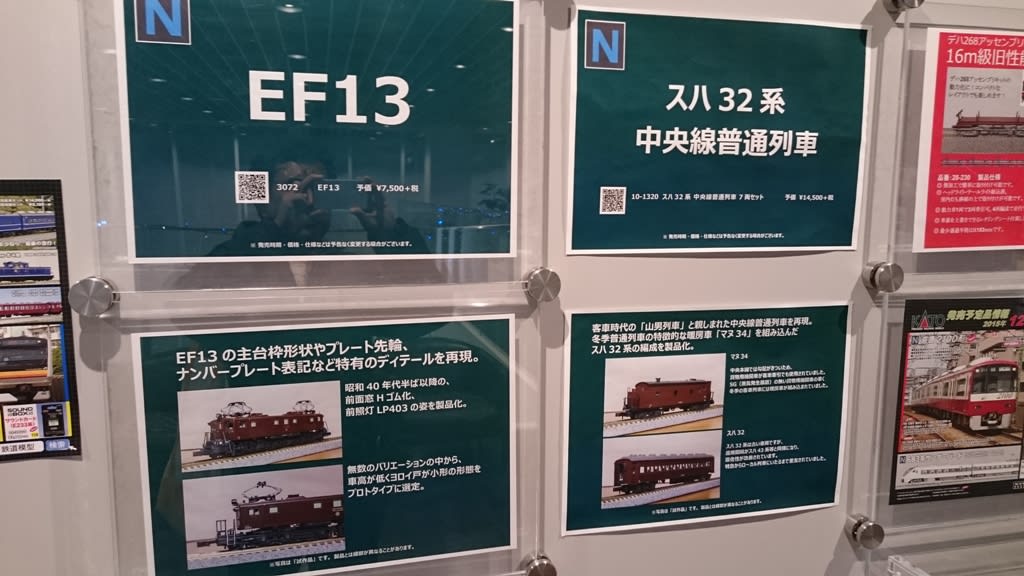こんばんは。
明けて25日。2016年も、はや1ヶ月近く経ってしまいました。早い早い・・・
記録的な寒気団の襲来とのことで、わが家から見える夕焼け富士もひと際くっきりと浮かび上がっていました。

昨日の段階でPVCマットに貼っておいたカーブポイント2本。接着剤が乾いたところでさっそく周囲をカットします。

こんな形でとりあえず道床つきカーブポイントのできあがり。予想通りかなりラクです。

マットの裏側に多用途接着剤を塗り所定の位置にカーブポイントを固定。さらに端部は小釘を打ってレール位置がずれないようにします。

相対するポイントはコード100レールなので、コード83レールとうまくつなぐためにヤスリで高さを縮めます。まずレール踏面を端から2cmくらいの部分まで、なだらかに変化するように削ります。

続いてレール底面もジョイナーが入る部分を軽く削っておきます。念のため、底面のサイドも軽くヤスリを当てて幅を狭めておきました。

こちらはPVCマットの代わりに厚紙を貼り付けておきます。ヤード出入庫線は道床を省略しているため、マットの厚さ6mmぶんを徐々に下げなければならないのですが、マットを精度よくテーパー状に削るのは難しいため、他の勾配区間と同様に橋台を置いて、その上に載せるようにしたものです。

絶縁ジョイナーを挟んで3本のカーブポイントを固定したところです。内回り側がやや角折れ気味になってますが、カーブと勾配の3次元の制約のなかで何とか収めることができました。

反対側からみたところです。外回りと内回りで高低差が大きいため、まるでスイッチバックのようになってしまいました。スイッチバックは単線・客車時代の中央線を象徴する施設なので、かくなるうえは“なんちゃってスイッチバック”として、お立ち台需要にも応えられる作り込みをしたいと思います。(笑)

よろしければ1クリックお願いします。
 にほんブログ村
にほんブログ村
明けて25日。2016年も、はや1ヶ月近く経ってしまいました。早い早い・・・
記録的な寒気団の襲来とのことで、わが家から見える夕焼け富士もひと際くっきりと浮かび上がっていました。

昨日の段階でPVCマットに貼っておいたカーブポイント2本。接着剤が乾いたところでさっそく周囲をカットします。

こんな形でとりあえず道床つきカーブポイントのできあがり。予想通りかなりラクです。

マットの裏側に多用途接着剤を塗り所定の位置にカーブポイントを固定。さらに端部は小釘を打ってレール位置がずれないようにします。

相対するポイントはコード100レールなので、コード83レールとうまくつなぐためにヤスリで高さを縮めます。まずレール踏面を端から2cmくらいの部分まで、なだらかに変化するように削ります。

続いてレール底面もジョイナーが入る部分を軽く削っておきます。念のため、底面のサイドも軽くヤスリを当てて幅を狭めておきました。

こちらはPVCマットの代わりに厚紙を貼り付けておきます。ヤード出入庫線は道床を省略しているため、マットの厚さ6mmぶんを徐々に下げなければならないのですが、マットを精度よくテーパー状に削るのは難しいため、他の勾配区間と同様に橋台を置いて、その上に載せるようにしたものです。

絶縁ジョイナーを挟んで3本のカーブポイントを固定したところです。内回り側がやや角折れ気味になってますが、カーブと勾配の3次元の制約のなかで何とか収めることができました。

反対側からみたところです。外回りと内回りで高低差が大きいため、まるでスイッチバックのようになってしまいました。スイッチバックは単線・客車時代の中央線を象徴する施設なので、かくなるうえは“なんちゃってスイッチバック”として、お立ち台需要にも応えられる作り込みをしたいと思います。(笑)

よろしければ1クリックお願いします。