
(写真はアラレタマキビです)
中学生の研究は、東京都科学教育振興会、読売新聞社主催の日本学生科学賞・東京都の部で最優秀賞になったとのこと。その研究が「海辺の科学」という本の中に掲載されていました。
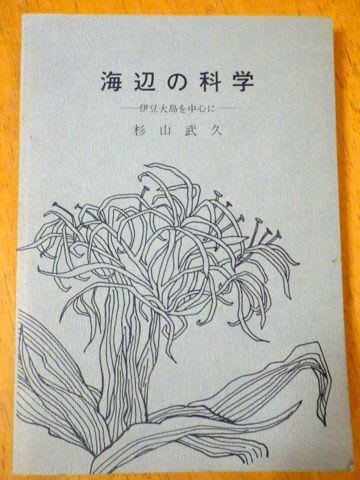
本の中には、生徒達がフィールドでの観察から様々な疑問を感じ、それを解決するために自分たちで方法を考えていった過程が記録されていました。
全く動かない貝に対しての「生きているの?」という疑問から始まり、海水をかけたり、真水をかけたり、光に対する反応を調べたり…。本ですぐに答えを見つけるのではなく、自分たちで答えを探していく行程が素晴らしかったです。
その本の中から、私が「!」と思ったこと…
「海水をかけると動き出すけれど、真水をかけると動きが止まる。」
「光と反対の方向に移動する。」
「そうなんだ~!」
現場で観察したくなって、先日太陽が沈む直前に海岸に行って来ました。
太陽の角度はこれぐらいでした。

「タマキビは光に背を向けているのだろうか?」
ワクワクしながら岩場をのぞいて見たら…
あれ?

なんか思ったよりバラバラ…。
あ、そうか、彼らにとって「光と反対の方」というのは「暗い方」…すなわち、溶岩の穴や隙間なのかも。全部太陽に背をむけているような光景を想像していましたが、そんなわけないですよね(笑)
さらに海水をかけたら動き出すのかと期待して潮溜まりの水をかけてみましたが、タマキビは微動だにしません…。うむむ~、手でピチャピチャかけるぐらいでは、水の量が少ないのかも?
なんだか納得できなかったので、今日も再度、同じ場所に行って来ました。
昼11時頃、ほとんどのタマキビたちは、いつものように穴の中。
でも溶岩の表面に出ているものが何匹かいました。

なんだか堂々としています!
餌でも食べに出て来たのでしょうか?(動かないけど・笑)
海水中に入っているものもいました。

本には「炎天下にいるタマキビは蓋を閉じて岩に着いているが、海水を岩にかけると足でくっつく。」と書いてあったので、調べてみました。
ホントだ!

蓋を閉じたまま、なにやら糊のようなもので岩に貼り付いています。
蓋をすることで、乾燥から身を守っているのでしょうか?
さて、夕方になってから、またまた同じ場所に行ってみました。

海は昼よりも荒れていて、時々白い波の飛沫が上がっていました。
驚いた事に、たくさん居たタマキビたちが1匹も居なくなっていました!
海が荒れて来たから避難したのでしょうか??

「あんなに居たのに,どこにいったんだろう?」
不思議に思って水の中の小石の下も調べましたが、姿がありませんでした。
海も荒れていて近づけないので、違う場所にいた5匹を持ち帰って観察する事にしました。

「海水の中では良く動く」…本のとおりです!
(潮溜まりではほとんど動きがないような気がするのですけど?)
仲間に接近中。

あ、登ります!

おんぶ~。

裏から見ても可愛いです!

水を持ち上げます。

水を乗せたまま出てきます。

脱出~。

美しい水のヴェールを身につけているのが、なんとも素敵です。
しばらく放っておいたら、みんな水面上に出て来ました。

ほんとうに水が嫌いなんですね~。
本には「淡水に入れると2~3日で死んでしまうが、乾燥した空気中では約9ヶ月も生きている。」と書いてありました。
で、ケースの蓋をあけてみたら、みんなそれぞれの道を歩きはじめました。
水の中に帰るもの、縁に留まるもの、そして新天地へ冒険の旅にでるもの…

いや~、生き物って本当に多様ですね。(実感)
ところで、この先の展開はどうなるんでしょう?
タマキビ達は、水の存在を感じて、あまり離れずにいるのでしょうか?
このまま朝までおくのが怖いような、楽しみなような…笑。
溶岩の小さな穴の中に入って、いつもジッとしているように見えるタマキビたち。
実は不思議がいっぱいの、面白い生き物だったのですね。
これから溶岩の上で暮らすこの小さな生き物を観察するのが、楽しくなりそうです。
(カナ)



































 海にはこんな子達も生きていました
海にはこんな子達も生きていました まだ生きていました。ほら動かないで!
まだ生きていました。ほら動かないで!























