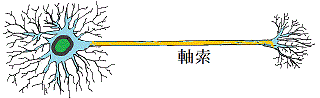きょう、昼に散歩していたら、親が子に向かって「話したら負けよ」と言っている親子とすれ違った。そのとき、「だるまさん、だるまさん、にらめっこしよう。笑ったら負けよ」という子どものときの遊びを思い出した。これは、「笑う」という情動を意識すればするほど、その情動を意識が制御できないことを利用した遊びである。
伊藤亜紗の『どもる体』(医学書院)が扱っている問題は、人間の脳のなかに、自分がコントロールできない自分がいるということだった。どもりを直そうとすると、自分が自分でなくなるという、どもる当事者たちの率直な話を書いていた。
私は、最近、統一された「自己」というものはないと思うようになった。笑う自分も、笑うまいとする自分も、自己。どもる自分も、どもるまいとする自分も、自己。いろんな自分が争わなければ、悩むこともない。
笑うまいとする自分、どもりを直そうとする自分は、対人関係のなかで生じた自分である。対人関係のなかで生じた自分は、言葉で自分を分析し、脳のなかにたくさんいる自分を言葉でコントロールしようする。そんなことができるはずがない。
伊藤亜紗は、『記憶する体』(春秋社)のエピソード10「吃音のフラッシュバック」で、どもらずに話せるようになった「柳川太希さん」が、どもる他の人を見たくないと言う。どもっていたときのトラウマがフラッシュバックするからだと言う。
このようなことをも「トラウマ」というのかと思うが、嫌な思い出は、しっかりと、人間の脳のなかで長期記憶になっている。長期記憶は削除できない。思い出さないようにするしかない。
もちろん、トラウマをもっている人に向かって、思い出すなと言っても無駄であるし、ますます、嫌な思い出を意識するようにさせる。「思い出すな」と絶対に言ってはならない。
「柳川さん」は、昔、保育園で、みんなの前で立って話すように仕向けられたとき、「発作みたいな感じで動機が激しくなって」しゃべれなくなったという。
自己主張をみんなの前ですることは、競争社会で勝ち抜くために有用かもしれないが、それが別に正しい生き方ではない。勝たなくても生きていける。
保育園によっては、「みんなの前で立って話す」ことが、個性を育てる教育で、名門幼稚園や名門小学校の「お受験」に役立つと考えている。間違っている、間違っている、許さないぞ。それは支配―被支配の構造を固定化させる行為だ。
「柳川さん」のトラウマは、思い出したとき、当時の保育園の園長や保育士はグズだったと思うことで、ダメージを弱めることができる。
対人関係のなかで生じた「自分」のなかには、現実社会の掟を維持しようとする保守的監視人が内在化した「自分」がある。監視人の「自分」は、ほかの多くの「自分」を劣っていると非難する。そういう監視人の「自分」にみずから気づき、それを排除する」と、人は楽になれる。
人は言葉を使うようになったばかりに、言葉を通じて、他人が、社会の掟が、脳のなかに監視人や命令者として入ってくる。
どもらずに話せるようになるため、「柳川さん」は非常に苦労したのであろう。コントロールできない自分とコントロールしたい自分とが妥協したのであろう。いまにも壊れそうな妥協であるから、どもる他人を見れないのだろう。
どもることは悪くない、どもることは悪くない、と心から納得できるまで、コントロールされる自分とコントロールしたい自分との休戦の不安定は続くと思う。