
けさの朝日新聞に、台湾のIT相オードリー・タン(唐鳳)が子供たちに「学校行けなくても構わない。でも、学ぶことをやめてはいけません」というメッセージを寄せたという記事があった。
もちろん、インタネットを通じて、直接、子どもたちにそう呼びかけたのではなく、朝日新聞の記者のインタビューにそう答えたのである。したがって、これは、記者とオードリー・タンとの合作のメッセージかもしれない。
それでも、ハンコを追放する、マイナンバーカードを使わせる、しか言わない日本のIT相の竹本直一よりも、ずっと、マシである。京大法学部卒で、菅義偉の子分ということだけである。
タンのいう「学ぶ」ということは、どういう意味であろうか。記者のインタビューにつぎのように答えている。
〈私も長いこと学校を休みました。今はネットがありますし、図書館があります。ネット上で意見を交わせるサイトは、相手の考えを学べる場です。学校に行けなくても構わない。〉
「学ぶ」は、知識だけでなく相手の考えを知るということのようである。しかし、タンの場合は、両親が彼女を守っていたのでないか。何も知らないでネットで人とつながった場合、学校と同じく傷つけられるだけかもしれない。
ネットでの学習は、ハッキリとした目的をもって、自分の問いに答えようとする知識をさがした方がよい。そして、また、ネットで得られる知識のレベルが低いから、図書館の利用が必要となる。ネットの知識はいつも表面的で、とっかかりとしては機能するが、深さがない。
図書館は、私が子どものとき、日本では、子どもと大人との読める蔵書の場が分けられていた。子どもであった私に許される本が制限されていたのである。
私は大学のある町に住んでいたから、専門書がある本屋があった。毎日、学校が終わると、その本屋に行き、専門書を立ち読みしていた。べつに素養があるわけでなく、頭のなかがチンプンカンプンになって痛くなると、夕食のため家に帰った。食事を終えて、読んだことを自分なりに考えなおし、自分の知的体系を作っているうちに眠くなった。私は、早く寝床につく子どもだった。
タンが「考える」ということを強調していないのは意外である。これは、記者に興味がないから、インタビューでは出なかったのではないか。
タンは理想とする教育についてつぎのように答えている。
〈それぞれの子の性格や特性に合わせた教育で才能を伸ばす。また、考え方の異なる相手でも友達になれるようにすることです〉
〈(具体的には)3つの要素があります。好奇心を尊重し、自発を促す。どんな年代のどんな背景を持つ人でも対話できるようにする。そして考え方が違っても、ともに成長できるよう導いていくことです〉
これって、自分が両親や周りの人からうけた教育環境をそのまま話しているのではないか。不登校の子どもたちをみていると、それから、ほど遠い所にいる子も少なくない。助けてあげたいと私は思うのだが、NPOで活動していても、私を必要としている子とつながらない。
政府の洗脳教育の場に ついていけない子どもを、私どもの所にあずけていただけないだろうか。幸せだった私の子ども時代を分け与えたい。











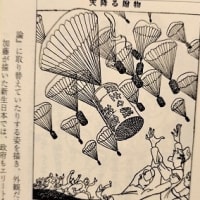

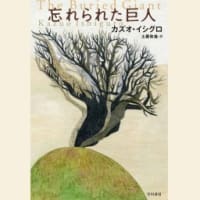






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます