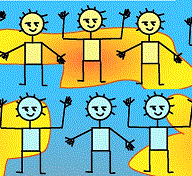わたしは、小学校や中学校で古文や漢文を教える必要がないと思っている。高校でも選択科目で充分であると思っている。教える漢字もできるだけ少なくし、将来はゼロにすべきだと思う。また、国語の教科書を横書きにすべきだと思う。
親子のコミュニケーションを維持するための日本語教育なら、現代文で十分である。しかも、平易に書かれた現代文を国語の教科書の素材に選ぶのがよい。難しい文は、内容がないから,わざと難しく書いていることが多い。大事なメッセージを書く人は、多くのひとたちに読んでもらえるよう、平易だが誤解を生まない文を書く。
わたしは、日本文化を否定しているのではない。覚えさすことが教育だという考えを否定しているのである。覚えることは、過去の考え方にしたがうという態度につながる。批判的知性を育てるには、覚えすぎない教育が重要だと考える。
明治時代に、欧米の翻訳を業績とする学者が、やたらと漢字を組み合わせ、「造語」をつくった。当時は、それだけ、思想を述べるのに日本語は貧困だった。儒学は、天下国家を論じることができるが、自由とか平等とか個人とか人権とか、いう概念がなかった。
しかし、今は違う。明治時代の造語を、使ってもいいものと、使うべきでないものと、より分ける必要がある。また、外国から輸入した概念だったら、原語を使うのも、おすすめだ。
漢字が使えないと、「こうえん」が「公園」か「講演」か「公演」か「後援」か区別つかなくなる。しかし、「公園」には「ひろば」「あそびば」「はなぞの」「さくらのその」と、いろいろな言い換えがあり、こちらのほうが言葉のイメージがずっと広がる。
わたしの子ども時代に、耳で聞いてわかる日本語を、話そうという運動が、ラジオ放送であった。例えば、「市立中学校」は「いちりつ ちゅうがっこう」と、「国鉄」は「くにてつ」と言った。
漢字が使えなくなると、どこで文節がきれるのか、読みづらくなる。これは、現在の日本語表記法に問題がある。江戸時代の読みものは、ひらかなが中心であったが、文節単位で、文字列を切り離すので、多くの人が理解するのに不便を感じなかった。
最近のライトノーベルやネット小説は、漢字をへらしても読みやすい文にするため、書き言葉の工夫をしている。例えば、「嘘をつく」は「ウソをつく」と書くとか、「、」を多用するとか、している。
漢字の書き順、ハネとかノビとかは、左ぎっちょの子には大きな負担となる。横書きにすると、日本語の間にハサマった数字や外国語が読みやすくなる。
もちろん、覚えることを少なくし、考えることを多くする努力は、国語だけでなく、英語や理科でも必要である。