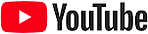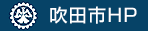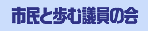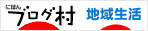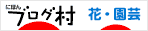未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
連合自治会三役会議
午前中は事務所で作業をした後、午後から会議です。
今年度の連合自治会副会長を引き受けたため、会長、副会長、書記の三役会議に出席することになりました。
とはいっても、会議場は「すかいらーく」、フリードリンクで3時間ほどねばって会議をしました。(もちろん、ドリンク代を会議費としては落としませんよ!各自の自腹です)
次回定例会の下打ち合わせやら、夏祭り(盆踊り)の下打ち合わせやら、これまで参加したことのなかった地域の行事の組み立てがよくわかって、勉強になります。
このような縁の下の力持ち的作業があってこその地域活動なんだなぁと改めて地域の役員さんたちに感謝します。
今年度の連合自治会副会長を引き受けたため、会長、副会長、書記の三役会議に出席することになりました。
とはいっても、会議場は「すかいらーく」、フリードリンクで3時間ほどねばって会議をしました。(もちろん、ドリンク代を会議費としては落としませんよ!各自の自腹です)
次回定例会の下打ち合わせやら、夏祭り(盆踊り)の下打ち合わせやら、これまで参加したことのなかった地域の行事の組み立てがよくわかって、勉強になります。
このような縁の下の力持ち的作業があってこその地域活動なんだなぁと改めて地域の役員さんたちに感謝します。

コメント(0)|Trackback()
住民投票条例3
もうすでに新聞やテレビニュースでご存知の方も多いと思いますが、吹田市長へ市民から直接請求のあった住民投票条例が4月臨時議会にて否決となりました。
前のコメントでも、私の考えの一端をご紹介しましたが、臨時議会を終えて、どんな風に考えたかについてお伝えいたします。
<前提として>
私は「住民投票」そのものについては以下の論点5にも書いたように賛成です。
しかし、住民投票に賛成であることが、直ちに「梅田貨物駅が吹田操車場跡地へ移転されることの市民の意思を問う投票条例の制定」に賛成であると結びつくものではありません。
なぜなら、提案されている条例案には不備、齟齬があり、このまま不備があると思われる条例案を賛成することはできないのではないかと思ったからです。
<論点1:条例案の不備をどう考えるか?>
地方自治法の解説書によれば
1.直接請求による条例案に不備があったとしても市長はそのまま議会に提案しなければならない
2.直接請求による条例案は形式が一応整備されていればよく、立法技術上の多少の不備は問わない
これらは、議会審議の中で修正することも可能であるからとのことです。
今回は、本会議でも委員会でも議員からの修正案は提出されず、結果として当初直接請求された時点での条例案で最終の討論採決となりました。
議員として、不備があるとわかっている議案に賛成しても良いのだろうか?ととても悩みました。
しかし、質疑の中で、
1.市長は「もしこの条例案が可決された場合、住民投票を行う」と述べたこと
2.当然、不備のある条例のままでは住民投票を行おうにも行えないので、実施できるよう条例改正案を速やかに議会提案する必要があること
と考え、このまま可決することは可能と考えました。
<論点2:最終着工合意は2月10日に済んでいるが?>
1.2月10日最終合意以降も直接請求のための署名を集められたこと
2.また請求代表者からの要望書に「最終合意にかかわらず早期に住民投票を実施してほしい」と書かれていたこと
3.質疑の中で、もし住民投票を実施し、反対が多かったとしても着工合意を撤回することはできないとの答弁がありました。
4.一方、たとえ万が一着工合意を撤回できないとしても、それでも市民の意思はどうであったかを知りたいという市民からの多数のハガキが届いていました。
(私のところには、市民の思いが一言欄に込められたハガキが約150通届きました。もっとたくさんのハガキが届いた議員もいるようです)
ともかく市民全体の意思を問いたいという請求者たちの思いを重く受け止めました。
<論点3:大きな乖離はないのか?>
1.住民投票は市の重要事項について「市議会並びに行政と民意との間に意見の大きな乖離がある」ときに行うものであり、今回は重要事項ではあるが、大きな乖離はないので、住民投票する必要はないというのが市長の意見です。
2.直接請求者たちは大きな乖離があると認識しているから、必要数以上の署名約4万を集め直接請求してきました。
これこそ大きな乖離だともいえます。
<論点4:説明責任は果したのか?>
他の議員の質疑の中で、
1.市は事業者に対して最善の取りうる限りの環境施策を行うように求めている
2.事業が実施されても吹田の環境に及ぼす影響は微々たるものである
3.財政的にも大変なときではあるが、まちづくり可能用地の取得は吹田にとってメリットである
と行政は答えました。
これらのことは、特別委員会や議会の中でもこれまでも行政として述べてきたとは思いますが、それでもなお、吹田の環境悪化を心配し、財政の悪化を危惧する市民がいるということは、行政としての説明責任を果したつもりでも十分ではなかった、あるいは説明責任を果してもなお市民の心配や危惧はぬぐえなかったということです。
<論点5:住民投票(直接民主主義)と議会制政治(間接民主主義)>
1.そもそも間接民主主義は、現代社会において直接民主制を採るのが不可能だから、止むを得ず採用している。
2.とすれば、少しでも直接民主主義のチャンスがあるのなら、優先して取り入れるべきである
3.現実的には直接民主主義は間接民主主義の補完ということですが、本来の価値としては直接民主主義は間接民主主義よりも上位であるはず
4.市長や議員は選挙で選ばれた市民の代表だけれど、市民はすべてを白紙委任したのではない
5.もし、市長や議会の意思が主権者である市民の意思とずれている、つまり乖離していると感じた場合、主権者としての市民の意思を投票によって市長や議会に示すこと、これが住民投票制度の意味である。
したがって、市民が市長や議会と乖離していると考え、地方自治法の手続きに基づいて直接請求してきたものを、議会は否決すべきではない、と考えました。
<結論>
以上のことを総合的に考え、私は以下のことを条件として、この議案に賛成することにしました。
1.条例案が可決された場合、住民投票を速やかに実施できるよう、必要な条例改正案をできるだけ速やかに議会に提出すること。
2.住民投票の結果如何にかかわらず、市の重要事項に大きな影響を与えると考えられるので、住民投票の賛否いずれか過半数を占めた票数が、投票資格者の3分の1以上となったとき、市長、市議会、市民はその結果を尊重しなければならないという一文を入れること。
3.住民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めること。また、広報活動および情報の提供に関しては事業についての賛否両論を公平に扱うことという一文をいれること。
最後に、今後提案される予定の(仮称)自治基本条例案に盛り込まれる予定の住民投票制度については、地方自治法に規定されていることより一歩進め、市長や議会の意思が主権者である市民の意思とかけ離れていると考える市民がたとえば有権者の8分の1以上おり、それらの署名があった場合には議会承認の手続きを踏まずとも自動的に住民投票できるような規定を盛り込むことを提案します。
前のコメントでも、私の考えの一端をご紹介しましたが、臨時議会を終えて、どんな風に考えたかについてお伝えいたします。
<前提として>
私は「住民投票」そのものについては以下の論点5にも書いたように賛成です。
しかし、住民投票に賛成であることが、直ちに「梅田貨物駅が吹田操車場跡地へ移転されることの市民の意思を問う投票条例の制定」に賛成であると結びつくものではありません。
なぜなら、提案されている条例案には不備、齟齬があり、このまま不備があると思われる条例案を賛成することはできないのではないかと思ったからです。
<論点1:条例案の不備をどう考えるか?>
地方自治法の解説書によれば
1.直接請求による条例案に不備があったとしても市長はそのまま議会に提案しなければならない
2.直接請求による条例案は形式が一応整備されていればよく、立法技術上の多少の不備は問わない
これらは、議会審議の中で修正することも可能であるからとのことです。
今回は、本会議でも委員会でも議員からの修正案は提出されず、結果として当初直接請求された時点での条例案で最終の討論採決となりました。
議員として、不備があるとわかっている議案に賛成しても良いのだろうか?ととても悩みました。
しかし、質疑の中で、
1.市長は「もしこの条例案が可決された場合、住民投票を行う」と述べたこと
2.当然、不備のある条例のままでは住民投票を行おうにも行えないので、実施できるよう条例改正案を速やかに議会提案する必要があること
と考え、このまま可決することは可能と考えました。
<論点2:最終着工合意は2月10日に済んでいるが?>
1.2月10日最終合意以降も直接請求のための署名を集められたこと
2.また請求代表者からの要望書に「最終合意にかかわらず早期に住民投票を実施してほしい」と書かれていたこと
3.質疑の中で、もし住民投票を実施し、反対が多かったとしても着工合意を撤回することはできないとの答弁がありました。
4.一方、たとえ万が一着工合意を撤回できないとしても、それでも市民の意思はどうであったかを知りたいという市民からの多数のハガキが届いていました。
(私のところには、市民の思いが一言欄に込められたハガキが約150通届きました。もっとたくさんのハガキが届いた議員もいるようです)
ともかく市民全体の意思を問いたいという請求者たちの思いを重く受け止めました。
<論点3:大きな乖離はないのか?>
1.住民投票は市の重要事項について「市議会並びに行政と民意との間に意見の大きな乖離がある」ときに行うものであり、今回は重要事項ではあるが、大きな乖離はないので、住民投票する必要はないというのが市長の意見です。
2.直接請求者たちは大きな乖離があると認識しているから、必要数以上の署名約4万を集め直接請求してきました。
これこそ大きな乖離だともいえます。
<論点4:説明責任は果したのか?>
他の議員の質疑の中で、
1.市は事業者に対して最善の取りうる限りの環境施策を行うように求めている
2.事業が実施されても吹田の環境に及ぼす影響は微々たるものである
3.財政的にも大変なときではあるが、まちづくり可能用地の取得は吹田にとってメリットである
と行政は答えました。
これらのことは、特別委員会や議会の中でもこれまでも行政として述べてきたとは思いますが、それでもなお、吹田の環境悪化を心配し、財政の悪化を危惧する市民がいるということは、行政としての説明責任を果したつもりでも十分ではなかった、あるいは説明責任を果してもなお市民の心配や危惧はぬぐえなかったということです。
<論点5:住民投票(直接民主主義)と議会制政治(間接民主主義)>
1.そもそも間接民主主義は、現代社会において直接民主制を採るのが不可能だから、止むを得ず採用している。
2.とすれば、少しでも直接民主主義のチャンスがあるのなら、優先して取り入れるべきである
3.現実的には直接民主主義は間接民主主義の補完ということですが、本来の価値としては直接民主主義は間接民主主義よりも上位であるはず
4.市長や議員は選挙で選ばれた市民の代表だけれど、市民はすべてを白紙委任したのではない
5.もし、市長や議会の意思が主権者である市民の意思とずれている、つまり乖離していると感じた場合、主権者としての市民の意思を投票によって市長や議会に示すこと、これが住民投票制度の意味である。
したがって、市民が市長や議会と乖離していると考え、地方自治法の手続きに基づいて直接請求してきたものを、議会は否決すべきではない、と考えました。
<結論>
以上のことを総合的に考え、私は以下のことを条件として、この議案に賛成することにしました。
1.条例案が可決された場合、住民投票を速やかに実施できるよう、必要な条例改正案をできるだけ速やかに議会に提出すること。
2.住民投票の結果如何にかかわらず、市の重要事項に大きな影響を与えると考えられるので、住民投票の賛否いずれか過半数を占めた票数が、投票資格者の3分の1以上となったとき、市長、市議会、市民はその結果を尊重しなければならないという一文を入れること。
3.住民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めること。また、広報活動および情報の提供に関しては事業についての賛否両論を公平に扱うことという一文をいれること。
最後に、今後提案される予定の(仮称)自治基本条例案に盛り込まれる予定の住民投票制度については、地方自治法に規定されていることより一歩進め、市長や議会の意思が主権者である市民の意思とかけ離れていると考える市民がたとえば有権者の8分の1以上おり、それらの署名があった場合には議会承認の手続きを踏まずとも自動的に住民投票できるような規定を盛り込むことを提案します。
コメント(1)|Trackback()
?