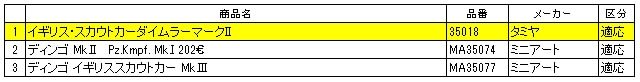志摩リンと土岐綾乃が渡った「デス・ブリッジ」こと畑薙大吊橋に着きました。大井川エリアの聖地巡礼では最も最奥に位置し、車やバイクで行っても沼平ゲートからは片道2.7キロを歩かないと行けない難度の高さから、ゆるキャン巡礼者の大半がいまだに行けていないと聞きます。志摩リン、土岐綾乃も相当な苦労をしたうえで来ていますから、気楽に行ける場所でないのは確かです。
御覧のとおり、現在の畑薙大吊橋は平成元年の竣工です。それ以前からあった木造の吊り橋を金属製で架け直したものといいますが、それからでももう33年が経過しているわけです。
財務省の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」のなかに「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」という項目があり、さまざまなものの耐用年数が書かれていますが、橋も含まれます。吊橋の耐用年数に関しては、木造なら10年とあります。金属製吊橋に関する記述は見当たりませんが、「金属造のもの」としての「橋」については45年と書かれますので、いまの金属製の畑薙大吊橋もそれに準じるものとみてよいかと思われます。あと10年ぐらいはもつということでしょう。

自撮りの最中に、吊橋がカシャ、カシャ、というような妙な音を立てているのに気付いて思わず橋を見てしまいました。

よく見ると、向こうから吊橋を渡ってくる人影が見えました。さきに望遠モードで捉えたカップルだったようで、こちらに渡り切った際に挨拶してきましたので、向こうに何かあるのかを聞きました。「普通の登山道みたいですけど、なんかクマが出るそうで、クマ注意の看板があるんで、すぐに引き返してきたんですけど」と答えてきました。向こうも、ゆるキャンのコミックでこの吊り橋を知って来たということでした。やっぱり同じ目的だったか、と笑ってしまいました。

では、と私も高所恐怖症に震えつつ渡りはじめました。というか無理してでも渡らないと、はるばるここにやってきた意味がありません。小学生の頃に超苦手だった平均台よりはマシじゃないか、と思いつつも、覚悟を決めて足を踏み出しました。

土岐綾乃いわく「足場ほっそ!!」・・・いや普通に他の吊橋と似たような足場の幅ですけど・・・。

志摩リンいわく「手すりスカスカ!!」・・・いや他の吊り橋だって手すりはこんなものでしたけど・・・。

そして二人が「めちゃくちゃ高っ!!」・・・いやこの程度の高さは・・・めちゃくちゃ高っ!!

眼下の畑薙湖に水があった場合の湖面からの高さが約30メートルだそうです。ということは干上がってる状態ではもっと高さがあるわけです・・・。・・・めちゃくちゃ高っ!!高所恐怖症にの身には地獄・・・。

やめて・・・!やめてちょうだい・・・!高い、という日本語をここで言わせないでちょうだい!!高い、って何?・・・そんな恐ろしくて難しい日本語はやめてちょうだい・・・!
というか、なんでここを渡る羽目になるわけ?長さ181.7メートル・・・・、ウヒョヒョヒョ・・・。(アホかお前は)

恐怖と緊張と錯乱に震えつつも後ろを振り返りました。畑薙湖の北端が奥まで伸びているのが分かりました。僅かな水流が白い湖底に細く流れているのも視認出来ました。というか、極力下を見ないようにしていました。

ただ、周囲の景色は大変に良かったので、高所恐怖症さえなかったなら、普通に楽しめたと思います。紅葉の時期にはもっと美しい景色だっただろう、と思いました。 (続く)