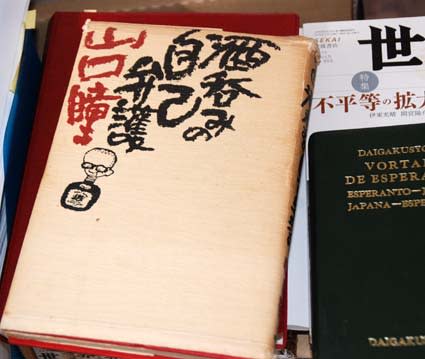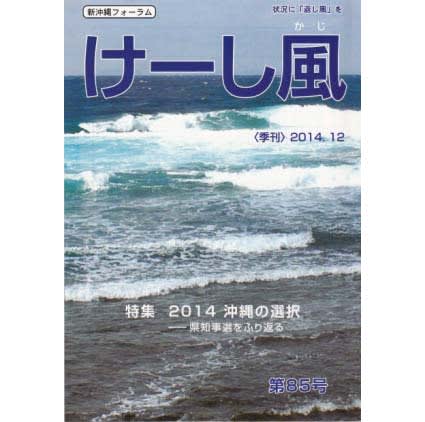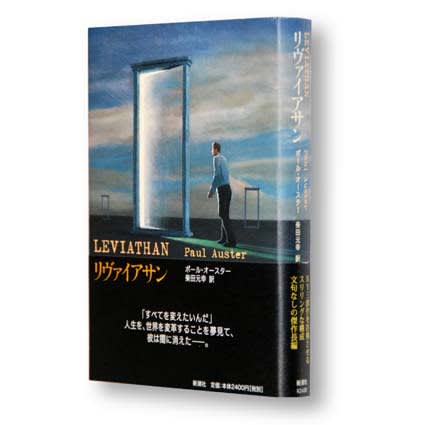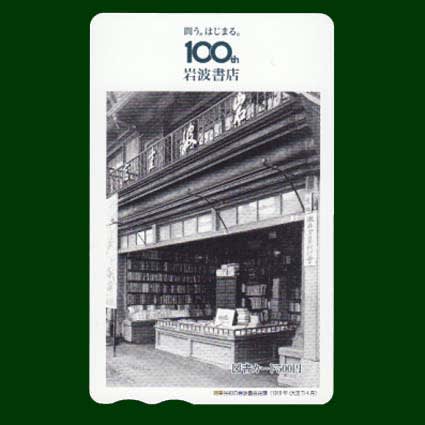崎山多美の作品は、エッセイ集の『南島小景』を残して単行本はほぼ制覇した。本書もご多分に漏れず入手しにくい一冊だが、運良く沖縄の古書店のホームページで見つけて即刻購入した。Amazonの中古で図書館の払い下げ本が核安で出ているけれど、シールやゴム印などに加え、補強のビニールが全面に張られ、製本も崩れている場合がしばしばだ。これではいくら安くても購入する気はしない。
今回入手したのはほとんど無傷で状態が良い上に、定価よりわずかに高目で、まあ良心的な価格であった。このレベルだと、Amazonの中古で出れば8000円くらいついているから、それではちょっと手が出ない。
本書は以前図書館で一度借りたことがある。何冊かまとめて借りたものだから、期限の2週間で読み切れず、そのまま返してしまった。崎山多美の作品としては「水上往還」(『くりかえしがえし』に収録)があまりにもよかったものだから、それ以上の期待が本書になかったこともある。
表題の「ゆらてぃく ゆりてぃく」は崎山多美独特のシマ言葉をまじえた文体で、それが幻想的な雰囲気を醸し出す。
物語の舞台は「保多良ジマ」という南の果てにある架空の小島である。この島ではすでに何十年も「赤子」が戸籍簿に登録されたことがない。いつの頃からか、「子供は作らないことを暗黙の美徳にするという風潮がシマビトの心を支配していた」。そのために、シマは80歳以上の老人ばかりになってしまっていた。男女の交わりがなかったわけではない。しかしそれが、子孫を残すための機能を果たさなくなった、という事情があったようだ。つまり、こういうことなのだろう。石女とインポテンツが急増して、子供が生まれたりする家庭に恨み羨みが生じて、なんとなく誰も子供を作らなくなってしまったのではないかと。
そんな保多良ジマの平均寿命は高い。最高齢は133歳で80歳ではまだ若者である。
そのシマに不思議な出来事を目撃したことのある、117歳になるジラーという男がいた。ジラーの思い出パナス(話)を通じて、なんとも怪奇なこのシマの文化と光景が描かれている。
このシマではかつてある地方で実際にあった夜這の風習がずっと続いていた。ただ、保多良の夜這はイナグ(女)がイキガ(男)の寝所に夜這するのである。あくまでも主導権はイナグ(女)によって「仕切られて」いるのだ。しかも実際の婚姻とはまったく切り離されていて、婚姻が行われる前であれ後であれいっこうにかまわず、イナグは目当てのイキガをたずね歩いた。
つまり、現代社会のように、女が性によって男に取り込まれることはなく、あくまで自由であった。それは古代日本の農村に似ていなくもない。
保多良ジマの葬儀は水葬である。したがって島内に墓はない。人は死ねば海に返されるのだ。静かに死に行く年寄りたちは、人々の手で戸板状の板に乗せられ、裸の全身に絡められた蔦葛とともに、そっと海に流され静かに消えていくのだ。
もしこの小説が、すべて標準語で書かれていたならば、そうとう破天荒なものになっていただろう。しかし、仰天するような内容が、シマ言葉によって上手にフィルターがかけられていて、美しくも物悲しい。
崎山多美の作品の中で「水上往還」とともにお薦めしたい傑作である。
同書には、表題作の覚書とも位置づけられる「ホタラ綺譚余滴」が併催されている。こちらはこちらで面白い。