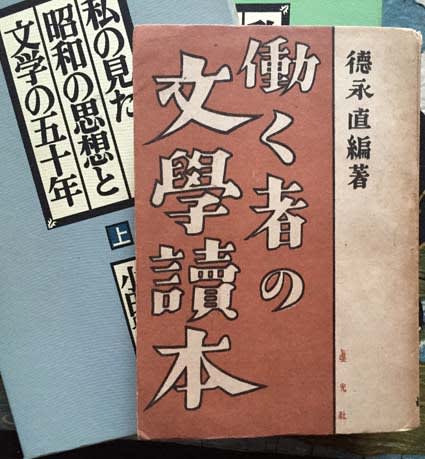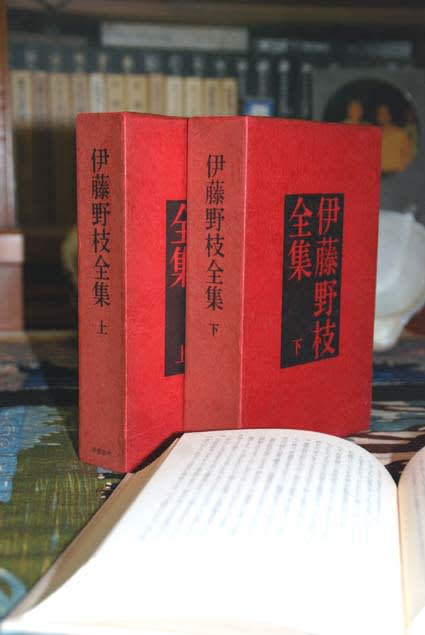先日亡くなった水木しげる氏の妖怪のルーツを辿ってみた。
妖怪と言えば、鳥山石燕の『図画百鬼夜行』が有名で、「ゲゲゲの鬼太郎」に登場する妖怪もそこから引いてきたと思われるものが多い。こちらは妖怪図鑑のようなもので、説明はそれぞれがいかなる妖怪であるかに留まる。
本書『妖怪談義』(講談社学術文庫)は民俗学の立場から、庶民の間で自然発生的に現れてきた妖怪を、それぞれ当時の生活や環境を鑑みながら解説している。特徴は、『百鬼夜行』がおどろおどろしいのに比べ、柳田國男が語る妖怪にはそこはかとなく愛嬌がある。「ゲゲゲの鬼太郎」に登場する妖怪は、どうもこちらを主力に参考にしたのではないだろうかと思えるのだ。
巻末に「妖怪名彙」という、妖怪辞書のような一節があって、そのなかに『百鬼夜行』には載っていない妖怪が多数登場する。
イッタンモメン、ヌリカベ、スナカケ、コナキジジイ、アズキスクイなど。スナカケは砂かけばばあ、アズキスクイは小豆洗いだ。
たとえばヌリカベについては、こんな解説がある。
〈ヌリカベ〉筑前遠賀郡の海岸でいう。夜路をあるいていると急に行く先が壁になり、どこへも行けぬことがある。それを塗り壁といって怖れられている。棒を以て下を払うと消えるが、上のほうをたたいてもどうもならぬという。壱岐島でヌリボウというのも似たものらしい。夜間路側の山から突き出すという。出る場処も定まりいろいろの言い伝えがある(続方言集)。
かつて日本には「真の暗闇」があった。夜、月明かり星明かりだけがたよりであった時代、曇りや雨の夜などは、「一寸先」も見えない。足元を照らすのはか弱い提灯の明かりかたいまつで、庶民はそれすらも手元にないのがあたりまえ。従って、闇夜の外出はよほど火急の用事がない限り控えたものであった。道に迷うこともあったろうし、なにかの自然現象で発光体が現れたり飛翔することがあったろう。発光虫の集団が頭上を飛べば「イッタンモメン」、樹木の葉が揺れてなにかがハラハラと落ちてくれば「スナカケ」になる。
いずれも、恐怖心が生み出した妖怪だ。翻って、そうした妖怪たちは精霊としての意味合いもあって、そこから自然を敬い神を畏れる風習が広がり、宗教へと発展して行った。
水木しげる氏も言っているが、妖怪とは人類に対する警告である。妖怪の風習は自然を破壊し争いごとを起こす人間をいさめる役割を果たしてきた。
はなから、非科学的、迷信を切って捨てるのは簡単だが、一旦立ち止まってその意味を考えてみたいものだ。