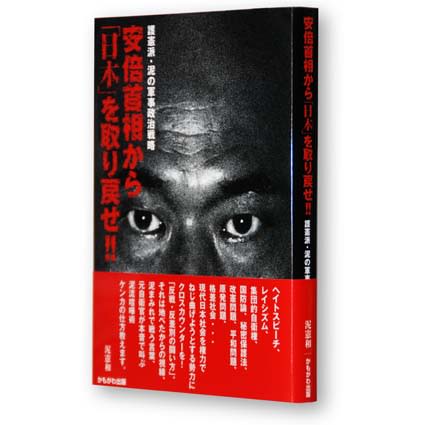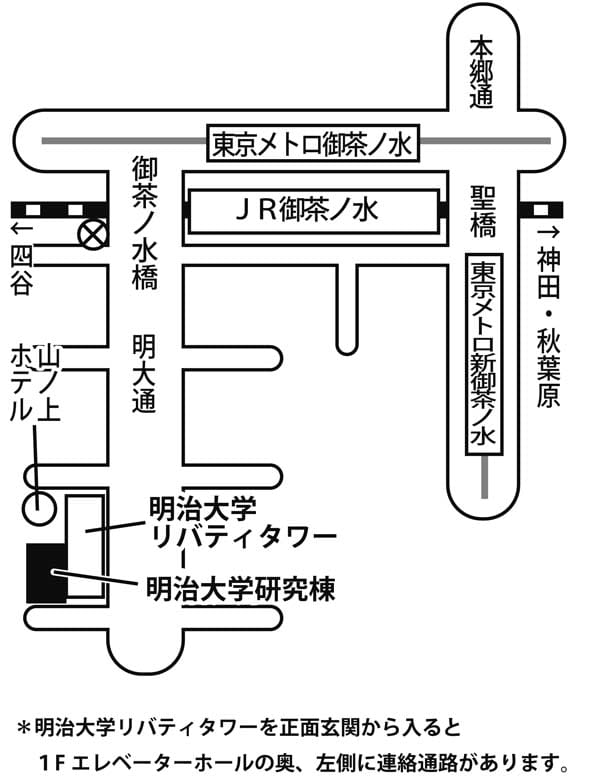ひょんなことから、たまたま定価に近い値段で入手できた。
崎山多美の単行本は、最新刊(2012年9月)の『月や、あらん』以外ことごとく品切れで、ほぼ絶版同様の状態が続いている。古書がネット市場に出品されても、タイミングにもよるがとんでもない高値が付けられていることもあって、とにかく入手困難である。
まあだいたい、目取真俊や池上永一など、メジャーな作家以外、沖縄文学は手に入りにくいのが常だが。
崎山多美の代表作といえば芥川賞候補になった『水上往還』である。これも収録されている『くりかえし がえし』が版元の砂子屋書房で品切れになっており、状態の良いものはなかなか手に入らず、根気よく待ってようやく半年ほど前に入手した。
熱心なファンがいるにもかかわらず、なぜ再版されないのかといえば理由は簡単だ。採算が取れないからである。費用は印刷代だけではない、在庫を持てば倉庫代がかかるし税金もかかる。出版不況の昨今、1000部刷ったらその1000部は完売できないと困るのだ。1000部くらいと思うかもしれないが、今の時代、新刊ならともかく再版の1000部を売り切るのは大変なのである。
崎山多美は、沖縄では著名な作家だが、本土では作品を読んだ人はおろか、名前すら知らない人がほとんどだと思う。それでも、わが杉並中央図書館には主要な本が揃っていて嬉しかった。
つまり、崎山多美の作品に興味を持つ人間はマニアックな部類に入るといえる。
そういう自分も、名前だけは知っていたが、作品を読んだのは友人のブログで紹介されたのがきっかけだから、自慢できたものではない。
崎山多美の作品には、シマコトバがちりばめられていて、本土の人間にはわかりにくく取っ付きにくい。講談社文芸文庫の『現代沖縄文学作品選』に収録されている「見えないマチからションカネーが」などはほぼ全編ウチナーグチで構成されている。
「ムイアニ由来記」もシマコトバが解説なしで多く含まれているので、度々つっかかった。だが、崎山多美独特の幻想的な文学世界に、シマコトバ、ウチナーグチは欠かせない。日常生活で標準語しか使わないわれわれには、別世界の雰囲気を感じさせてくれるのだ。たぶん、方言をあまり使わなくなった現代沖縄の若者たちにとっても、本土の人間ほどではないにしても、似たような効果があるのではないだろうか。
「ムイアニ由来記」は作者目線で沖縄の女性が抱える問題をファンタジックに描いている。
一人暮らしをする30代半ばの「わたし」は就寝前、いつもの習慣で「さる大手出版社(たぶん新潮社)から出版された」バルガス・リョサの『緑の家』の分厚い文庫本を読んでいると、突然電話があり「約束の日を忘れたのか」と呼び出され、連れて行かれる(リョサの小説がこの後の物語に何か意味があるのかと思ったが、どうやらそれは無関係のようだ)。
実は彼女には5年前に書き置きを残し、子どもをおいて出奔した経験がある。だが、その記憶はいつしか欠落しまっていた。
その書き置きに「5年後の誕生日に迎えにくる」と書かれてあり、今日がその日(約束の日)だったのだ。彼女は連れて行かれた先で、失われた記憶をひとつひとつ紡ぎ合わせていく。その子どもは色白で目が大きく、沖縄の人間とはまったく違った風貌を持っていたのである。
「ムイアニ」が子どもの名前であることが最後にわかる。
その子はいったい誰の子どもなのか、どんな成り行きで生まれ、どんな境遇で育ったのか、詳細はすべて読者の想像にゆだねられている。
幻想的な中に、沖縄という特別な環境のもとで暮らす女たちの精神構造が、すこしだけ垣間みられる。
もう一つの作品「オキナワンイナグングァヌ・パナス」と、花田俊典による「崎山多美論のために」を併載。