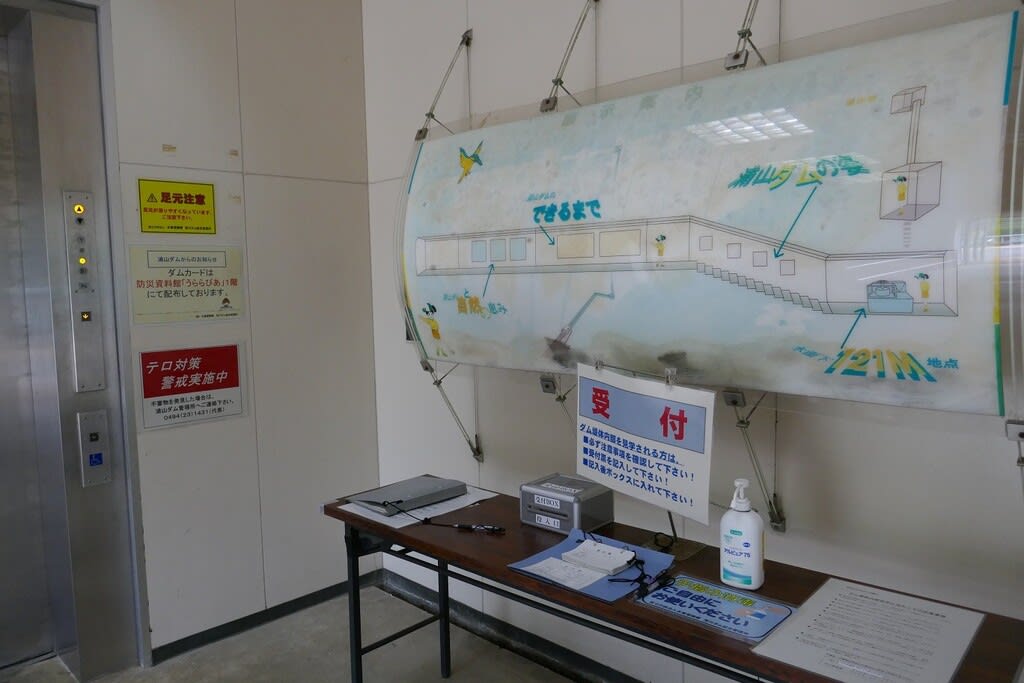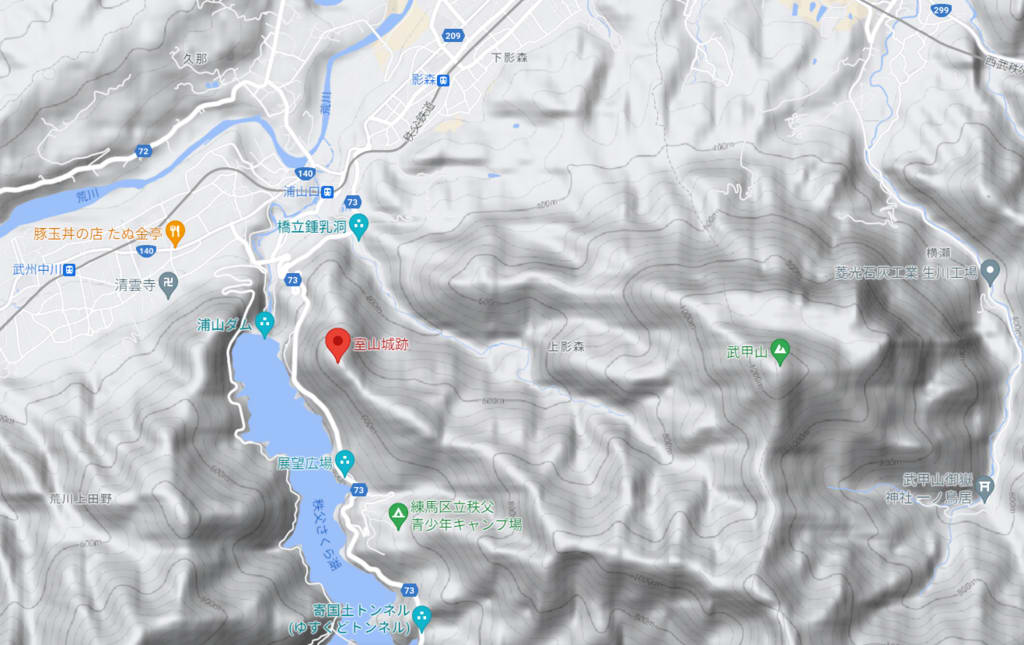夏の疲れの回復に、成田へ鰻を食べに行きました。
出かけに、庭に酔芙蓉が咲いていました。本当に夕方赤くなるのか確かめたいと思います。

1時間15分ほどで、到着。東京からではこうはいきませんね。

ばちが当たるので、まずはお参りです。

いつ来ても、大きくて立派なお寺です。真言密教だそうで、弘法大師空海の教えを教義とし、「真言」とは、仏の真実の「ことば」を意味しているのだそうです。
悪行を尽くすダーキシ(頭の中が空虚な岸田首相)に聞かせたやりたいですね。
さて、お参りも終えたので、参道を歩きます。
さすがに外国人が目立ちます。

お目当ての鰻屋「川豊」に入ります。

なんか、また値段が上がったような。

鰻も心なしか小さくなったような。
でも、味はいつもの通りおいしくて、食べているそばから体力が回復するような気がしました。

お土産にこれも定番の米屋の羊羹を買いました。

鰻を食べただけで帰るのでは、さすがにもったいないので、前から気にかかっていた成田空港施設のそば「航空科学博物館」に行ってみました。

地元の要望を受けて、運輸省が(財)航空科学振興財団を設立し、平成元年8月に開館したとのこと。いわゆるやらせによる天下り先設立ということですね。
だからなのか、展示がやる気ない雰囲気満載でした。そのくせ入場料が700円もします。更に、ほとんどの体験展示が準備中で何も試せませんでした。


コクピットの模型も映画「ハッピーフライト」で使用したものを譲り受けたもののようです。

階段がついていますが、中には入れません。有料の体験ツアーの人だけだそうです。

屋外展示は無料で見られますから、これだけにしておけばよかった。

YS-11 は、懐かしくって見られてよかったですけど。

ということで早々に引き上げました。
道の駅「風和里しばやま」で野菜を仕入れ、うちに帰ってみると、確かに酔芙蓉が赤く色づいていました。不思議ですね。
































































![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/347511cc.cb457604.347511cd.2c57c324/?me_id=1378518&item_id=10000333&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fararechanchi%2Fcabinet%2Fitems%2Fcl001%2Fthum_cl001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)