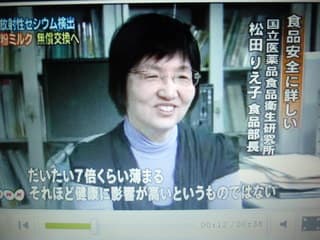女川港付近。
津波をかぶり、打ち捨てられたビル。
木造の建物は一軒も残ってない。
もちろん人の住んでいる家はない。

土台ごとひっくり返ったビル。
しかも周りは地盤沈下し、海の中に頭を突っ込んだ状況になっている。

車が入り込んだままの生涯教育センター。
車が倒れないようにロープがかけられているが、町にはこの車を片づける余力もないのだろうか。

カーナビで見るとここが女川駅なのだが、駅だった痕跡は何もない。
レールも駅の看板も流失した。

かつての女川駅。

広い範囲が地盤沈下して、海が陸側に寄ってきた。
一帯にはコンクリートの建物しか残っておらず、それはすべて廃墟である。
なにより人の姿が見えないのが恐ろしい。

住宅も人も消えた鷲神浜。

マリンパルは敷地全体が水没していた。

まるでベニスのような風景。
時刻は午後4時。カメラの露出を最大にしているから明るく見えるが、辺りはもう薄暗くなっている。

露出をノーマルにすると、このように写る。
灯りのない世界。もうすぐ漆黒の闇が降りてくる。

かつてのマリンパル。
このように賑わっていた。

けっして海の中ではなかった。
万石浦に移転した「おさかな市場」もここにあった。

遠くの高台に建つのは町立病院である。
病院は海抜18mに位置するが、驚くことに津波は病院の1階の1.9mの高さにまで来た。