The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―73. QMSとEMSを統合することによって、経営体質の改善に役立つ?”
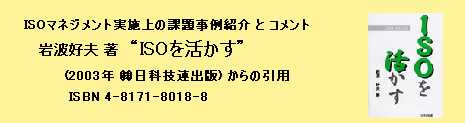
今回は、品質マネジメントシステムと環境マネジメントシステムの両立がテーマです。
【組織の問題点】
電気メーカーのA社は5年前にISO9001の認証取得し、最近ISO14001の認証も取得しました。
ところが、今後 定期審査の頻度が2倍になると困っているのですが、何とか効率的に運営する方法はないだろうか、という課題です。
【磯野及泉のコメント】
著者・岩波氏は 今 流行の品質マネジメントシステム(以下QMS:Quality Management System)と環境マネジメントシステム(以下EMS:Environment Management System)の統合を推奨しています。一般的には こういう見解は現在流行中です。セミナーなどでも 両マネジメントシステム統合に関することをテーマとして取り上げているものが多いように思います。
しかし、私は企業規模によっては一概に マネジメントシステムの統合が適切であると言い切れるかどうかは 疑わしいと 私は思っています。したがって、この事例での電気メーカーA社の規模は どの程度かによって QMSとEMSの統合の適切性を判断するべきではないか、と考えます。
単純に会社の規模に大きく影響されると言いましたが、実は その組織の複雑さにはもっと大きく依存すると考えています。事業所が複数かどうか、そして この事業所に部門が錯綜して所属しているかいないか、などの組織の状態によって、品質と環境のマネジメントシステムの統合が適切であるかどうかが 異なってくると考えています。
何故 そうなるのか。それは、EMSは 直接的に本来業務の指示命令系統に依拠して運営されるものではなくて、実際の事業所毎に運営・管理されなければならないために 生じる問題です。逆に、QMSは本来業務の指示命令系統に依拠して運営されるべきものです。
例えば環境コンプライアンスをとってみれば、事業所の所在する都市自治体の条例等による独自の規制も存在するため、事業所毎に マネジメントの在り方を考慮・検討しなければならないのです。したがって、事業所のトップは、事業所内に所属する他の誰よりも強い権限で EMSを指揮・運営しなければならなくなります。そうでなければ、事業所の対社外的課題を処理できなくなるからです。
そうなると、製品ごとに仕切られた事業部が有って、これが複数の事業所に展開している場合などは、この事業部のトップは EMSの中での権能は事業所長の権限より抑制されるべきなのです。しかも、一箇所の事業所に 複数の事業部の部署が並存するようであれば、ますます、どの事業部長よりも事業所長の権限が優越しなければEMSは 機能不全に陥ってしまいます。
逆に、当然のことながらQMSでは事業部長の権限が優越させなければなりません。
(このように組織が錯綜する事例を 下図に示します。)

したがって、例えば 全社的な品質政策の意思決定機関を 品質委員会とするならば、各製品の事業部長は必須のメンバーとなり、全社的な環境政策の意思決定機関を 環境委員会とするならば、事業所長は 必須のメンバーとなり、事業部長は 陪席する程度のメンバーとするべきでしょう。
こうなると、品質と環境のマネジメントシステムのマネジメントレビューへの参加者も それぞれの委員会からの横すべりとなり、その参加者は異なることになります。
この状態を 統合するとなると、品質・環境の統合委員会の運営はよほど たくみになされなければなりません。
このように 特に、大規模組織の企業では 統合マネジメントシステムの運営は 返って難しく、そのために不合理になることが予想されますし、事実 そういう見解を持って、システム統合していない大企業は存在します。
つまり、組織内で、それぞれのマネジメントシステムを運営する主体部署が異なるため、両者を統合することには原則的に困難が伴うと言えます。
この端的な事例が QMSは製品毎の運営で ISO9001の認証を取得しているが、ISO14001では 事業所毎に取得しているという やり方に見られます。EMSに関しては、小さな本社だけが コストのかからないKES(KEMS)という上手いやり方もあるようです。
但し、このように錯綜する組織は 常に修正のためのリストラクチャリングや再配置の対象とすることが不可欠であり、そうしなければ会社全体が非効率で不透明な組織となってしまいますので注意するべきでしょう。しかし、再配置が経済効率から見て非常に困難な場合も往々にしてあるでしょうから、QMSとEMSの統合は容易ではありません。
著者・岩波氏が指摘するように、品質活動や環境活動の実際の行為者にとっては 全て既に統合された業務そのものであって、両マネジメントシステムではその業務の側面を品質か環境かと区分けして見ているだけなのだという本質も忘れてはなりません。
したがって、いわゆる中堅以下の中小企業で よく見かける1企業1事業所の場合は 両システムの統合は 当然 検討されるべきでしょう。この事例での電気メーカーA社が そうであれば、著者・岩波氏の指摘通りだと思います。
要は 何でもカンでも“システム統合した方が効率的で良いのだ!”と言っていることが 問題なのであって、“自分たちはどうする?”という視点から 主体的に捉え考えることが重要なのです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 乃木希典 | 旧乃木邸訪問 » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




