The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
40年遅れの読書―糸川英夫著“逆転の発想”を読んで
前々々回書いたように映画“はやぶさ”を見て、あらためて糸川英夫博士の影響力の大きさに感動したものだったが、そう言えば博士が創始した組織工学なるものは その後どうなったのか、その活動の消息が全く伝わって来ていない。そこで博士の残した著書に触れてみたくなり、図書館で“逆転の発想”(角川文庫)という小冊子を見つけたので読んでみた。
糸川博士は、戦前は 専ら旧陸軍の戦闘機・九七式戦、隼(一式戦)、鐘馗(二式戦)の設計に携わっていた。それぞれ、当時優秀な戦闘機とされていた。戦後、GHQが 日本の再軍備を警戒して飛行機の研究開発を禁止したので、博士は ロケット研究に移ったとされる。そして、このロケット研究が その後 あの“はやぶさ”につながっている。そのせいか、日本の航空機産業は、世界の後塵を拝しているが、宇宙開発の技術は世界の先端を走っていると言って良い状態にある。
ミュー・ロケット開発後、博士自身は組織工学研究所を創設し、組織工学の研究開発へと進んで行ったものと思っていた。この組織工学なるものが、どのようなものだったのか、その名称からも想像がつかないので、いずれ それが発展してくれば明らかになるだろうと思っていたら、今に至ってしまった、というのが私の印象である。
そのあたりの事情を 振り返ってみようとネット・サーフィンを試みたが、どうやら組織工学研究所は 今は無く、糸川博士が亡くなって以降、残念ながら霧消したというのが実態のようだ。博士自身の個人的名声に支えられて存続し、引き継ぐ人に有力な人物が出ず、成果を上げることなく終わったのであろう。
さて、ここで取り上げた本だが、その組織工学の片鱗でも把握できれば、と思いつつ読み進めたのであるが、発行された1970年代にはベスト・セラーだったようで、巻末の“あとがき”に “『逆転の発想』は、正・続・続々・新上・新下と今までに5冊発行されて、「発想ブーム」の元祖になったように言われている。”と著者自身の言葉がある。そう言えば、私も“逆転の発想”のこれら正・続・続々・新上・新下のいずれかを読んだのかもしれない。記憶の彼方に、定かでないかすかに そんな印象がある。読み始めると、何よりもその70年代の雰囲気が芬々と甦ってくる。
ここで、標題の“逆転の発想”であるが、何が逆転なのかが気になるところである。これは博士によれば、70年代より以前にはビジネス(事業)は、「ビジネス・マン(企業人)」によって主導され、そのビジネス・マンは「企業」に依拠し、企業は「経済」活動というか「経済」社会の中にあり、その「経済」の背景に「技術」があり、その背景には「科学」があり、その科学は「論理・数学」的なものの上に成立している。その論理は人間の「理性」によるものであり、それは「言語」を使うことで形成され、その「言語」のシステムは その社会の「文化」、「体制」によっている。“そしてその体制は、シンボリックな「オーソリティ(権威)」というものにつながっているのである。” “ところが、現代(この本の時代:70年代)は論理的な考え方、数量的な考え方よりも、フィーリングの時代といわれる。・・・「企業」に対してはマーケットを構成している「消費者」が消費者運動(コンシューマリズム)を起こし、消費者は企業人を信用しないという不信感が起こってくる。また、「経済」においても「くたばれGNP!」という運動が起きるし、「技術」に対抗して「芸術」が台頭してきて『技術が人間を滅ぼしたのだ』と主張し、「哲学・宗教」が『科学者が人類を危険にした』と攻撃し、それでフィーリングと直感が有利になり、情緒的な行動が重要になるのである。”と言っている。これが“逆転の発想”の根拠になっている。
つまり、70年代当時は「ビジネス・マン(企業人)」←「企業」←「経済」←「技術」←「科学」←「論理・数学」←「言語システム」←「文化」←「体制」←「オーソリティ(権威)」が主導していたのが、それに対立する概念の「消費者」←「消費者団体市場」←「反経済」←「芸術」←「宗教・哲学」←「直感・フィーリング」←「情緒」←「行動」←「原始自然」←「反権威」の方に主導権が移りつつあるとして社会現象の解釈を総括しているのである。
こう言えば、日本の最高の選良に対し失礼な表現ではあるが、中々上手く現象を整理しているなぁとの感想だが、中にはこじつけ気味のところもあるように思える部分もある。例えば、現代の世俗的には「宗教・哲学」と「科学」は対立するのもと思われがちだが、実は「宗教・哲学」と「科学」は親和性が非常に高く、場合によっては 厳密にはその区別がつかないことがある。それを糸川博士はどう考えてこのような図式の中に組み込んだのか、まぁそういう社会現象があると言っているのdが・・・。また、後世の後講釈になるが、この70年代からようやく日本社会が モノ不足による供給牽引型から、モノ余りによる消費者中心の需要牽引型の構造に変化しつつあり、五輪音頭で有名な三波春夫の“お客様は神様でございます!”の時代に変化していった冒頭の頃のことである。したがって、供給側の「企業」より、「消費者団体市場」→「消費者」に主導権が移りつつある時代だった。また、当時は既成の権威に盲従していては、社会の矛盾の解決には寄与しないという雰囲気が横溢していて、それが「反権威」という気分に至っていたものだっただが、そこへ上手くつなげて解釈して見せたものだと感心させられる。
ここで、気になるのが「直感・フィーリング」や「情緒」的発想が、最近も世間に横溢していることである。70年代以降 ズーットそうだったのかも知れない。戦前、日米開戦を冷徹な計算に基づかず、反米感情という「情緒」で決した愚を繰り返すのであろうか。当時、昭和天皇が心配して側近に問合せたところ、側近が“(世論は)最早そのような(開戦の)「空気」でございます。”と奏上し、開戦やむなしに傾いたとされる。日本は「空気」つまり情緒で無謀にも開戦し、無条件降伏し崩壊した。戦前の日本はそういう「理性」の働かない状況だったが、現在も非常に感情的な反原発の雰囲気に溢れている。始末に悪いのは、それがあたかも「理性」に裏打されているかのような装いをこらしていることである。つまり、原子力村から村八分にされていた一部の学者が、一見「理性」的に振舞いつつも、その核心部分を感情的に誤魔化した結論を吹聴して回っていることである。特に自然放射能のことを無視して説明せず、人々を煽っていることは意図的としか思えない。放射能ゼロの世界は、この宇宙・自然界のどこにも存在しない。測定すればかならず何らかの放射能がカウントされる。しかも生ある限り、リスクはどこにでもある。絶対安全のリスク・ゼロは死の世界だ。リスクと便益をどう考えるのか、その利害得失を理性的に判定するのが科学の最重要課題のはずだ。
同じようなことは “二酸化炭素地球温暖化説”にも見られる。自分で徹底的に熟慮するのではなく、そういう感情的に煽る人について行く傾向は 絶えることがないのが残念なのだ。IPCCは本当に「権威」として認めてよい団体なのだろうか。戦前にも 大勢の開戦論を煽る人は居たようで、その人々が開戦への“勇ましい「空気」”を醸成したのである。
話が横にそれたようだが、ところで糸川博士は原発をどう見ていたのだろうか。本書には次のような記述があった。“核分裂による原子力発電は根本的にムリがあり、技術は放射性物質の問題を解決し得ないだろう。ウラン235とウラン235をぶつけてエネルギーを得る方法は縫い目のほころびているお手玉を作るようなもので、縫い目から放射性廃棄物がポロポロとこぼれてしまう。これを完全に縫い合わせることはむずかしい。・・・平和利用には不向きであり、平和利用は核融合が完成するまでおあずけ。”と言っている。確かに、核融合とまでは言わずとも、少なくとも核燃料サイクルの技術が完成しない内に、原発の商用化したのは開発戦略の決定的誤りではないかと思われる。
ところで、さすがの糸川博士も 現代では非常に意識されている“(地球)環境”という言葉には留意はしていない。当時、ローマ・クラブが将来の石油不足を煽った見解を発表していて、その後しばらくして、“宇宙船・地球号”という発想が喧伝されるようになった。本書はその少し手前のタイミングで発表されたのであろう、そういう概念はここでは見当たらない。恐らく、この時期ようやく日本が世界の先頭集団に参加し始めた頃で、グローバルな視点は未だなく、米国の社会状況を強く意識するので精一杯であり、また そうすることで先端を走ることが可能な時代であった。そうした、米国の最新動向を細かく紹介する部分がこの本にも随所にあったが、その米国でも“(地球)環境”という発想は未だなかったためであろう。
さて、ここで もう一つ博士の貴重な見解に触れることができる箇所を紹介したい。それは“新商品開発のヒント―失敗しないための8つのチェック・ポイント”として提示された図である。これは今で言う技術経営(MOT)の分野のテーマだ。そこでは、調査段階、検討段階、開発段階、市場に出す前のチェック段階、新商品のテスト及び発表、セールス段階に分けて、それぞれの段階で特に注意するべきことを挙げている。“調査段階”で①マスクド・ニードの発見、②クリエイティブ・ニード時代の終わり、“検討段階”で③社内説得のスケジュール化、“開発段階”で④使用者の言葉をよく理解せよ、“市場に出す前のチェック段階”では⑤社内環境の研究、⑥ブラック・ボックス・アレルギー、⑦卵は分けて入れよ、セールス段階で⑧テレビからFMラジオへ、となっている。
これは、恐らく、戦闘機開発や、ロケット開発の過程で博士が身に着けた貴重な注意事項の整理の結果なのであろう。こういう開発プロセスの概念を、その後、新製品開発に地道を挙げる日本の企業が注目しなかったのには非常に残念である。その後、米国流MOTの死の谷、ダーウィンの海などという概念を得意気に紹介する経営学者は居たが、それ以前に糸川博士は こういった整理をしていて、これの方が日本人にはより馴染み易いのではなかったか、と思うのである。このような日本人の発想が日本人により、発展させられることなく、米国で発想され、発展したMOTに安易に飛びつく傾向が、未だに日本人に染み付いているのが残念なのである。
①の“マスクド・ニード”とは本書によれば“潜在需要”のことだが、ISO9001で言う“暗黙の要求事項”の方が理解し易い。博士は戦闘機の設計に際し、その要求事項をパイロットの“(スピードは遅くても)すれ違いざまの一瞬にして相手を撃ち落す”という言葉では理解できなかったので、そのパイロット達と一緒に生活して“非言語系の表現に注目”したという。そうして、何とか“旋回半径の小さい機体”という工学的言語に翻訳して“隼”を作った。これが④の意味。しかし、実は、こういう当時の日本のパイロットの要求は 世界の戦闘機の設計思想からは外れた傾向の軽戦闘機*重視指向であって、それに気付いた陸軍と中島飛行機はその後、重戦闘機の“鐘馗”を作った。それに対し、海軍はパイロットの要求を重視し過ぎて、軽戦の零式戦にこだわり、その後の米軍の新型機に遅れをとったとされる。使用者(顧客)要求が全てではなく、むしろ それを適切な方向に導くような高度な設計者の意思が重要なこともある。今のソニーの停滞原因は そういう点に気付きがないことにあるのだろう。
*軽戦闘機とは、速度は遅いが、空中戦性能が良く“旋回半径の小さい”戦闘機のことで、“隼”や零式戦がこれに当たる。これに対し、重戦闘機とは、重武装(大口径機関砲等を搭載)で高速の戦闘機を言う。当時の日本のエンジン製造技術では、重戦闘機の仕様を満足することが難しかったという事情もあったとされる。
②の“クリエーティブ・ニード”とは、本書によれば “ドラッカー教授が元祖であり、「社会のニードが見つからなかったら、マーケットを開発し、そこへ売り込んだらどうか」という卓越したアイデア”とのこと。博士が今、大流行のドラッカー教授に 当時既に注目していたとは驚きである。
③の“社内説得のスケジュール”とは、“エジソンが「発明は2%のインスピレーションと98%のパーアスピレーション(反対)」”と言ったが、“私(著者)は、社内の賛成が40%になったらスタートすべきで、もし社内の賛成が60%になったらそれはもう手遅れだ”とのこと。繰り返すが、顧客の要求が全てではないのだ。
⑥の“ブラック・ボックス・アレルギー”とは、一般消費者等の使用者に不安感を与えないように製品の内容・特性を十分に開示するべきだという注意事項。今の原発問題での“放射能汚染”への専門家の説明不足は大衆の不安感を助長している、そういうことへの警告である。⑦の“卵は分けて入れよ”とは、ここではブランド・イメージは分散させて、リスク分散せよとの意味。金融分野では今もよく言われている警句である。⑧の“テレビからFMラジオへ”は、70年代特有の現象で、FMラジオの聴取者が増加した傾向を捉えたもので、それを博士は“視覚から聴覚へ”移る現象と解釈したようだ。これはむしろ、当時の消費者の要求が個別化する傾向を示すもので、今で言う、ネット化に相当するものだろうと思われる。
この本を読むことで 改めて“不易流行”という言葉を 思い起こした。正解を知った上で、答案を読んだようなもので、如何に世の選良・天才といえども、その現象のどれが本質であり、どれがその側面を示しているに過ぎないのかを見分けることが困難であるかを理解できたように思う。ここで、やはり、「反権威」を信条に、自分で徹底的に思考することの重要性を思い知らされた。如何に凡人の足りない脳力であっても、それをフルに使って考えてこそ、自分の見解に責任を持てるのであろう。
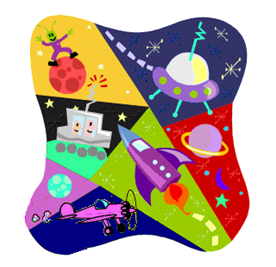
糸川博士は、戦前は 専ら旧陸軍の戦闘機・九七式戦、隼(一式戦)、鐘馗(二式戦)の設計に携わっていた。それぞれ、当時優秀な戦闘機とされていた。戦後、GHQが 日本の再軍備を警戒して飛行機の研究開発を禁止したので、博士は ロケット研究に移ったとされる。そして、このロケット研究が その後 あの“はやぶさ”につながっている。そのせいか、日本の航空機産業は、世界の後塵を拝しているが、宇宙開発の技術は世界の先端を走っていると言って良い状態にある。
ミュー・ロケット開発後、博士自身は組織工学研究所を創設し、組織工学の研究開発へと進んで行ったものと思っていた。この組織工学なるものが、どのようなものだったのか、その名称からも想像がつかないので、いずれ それが発展してくれば明らかになるだろうと思っていたら、今に至ってしまった、というのが私の印象である。
そのあたりの事情を 振り返ってみようとネット・サーフィンを試みたが、どうやら組織工学研究所は 今は無く、糸川博士が亡くなって以降、残念ながら霧消したというのが実態のようだ。博士自身の個人的名声に支えられて存続し、引き継ぐ人に有力な人物が出ず、成果を上げることなく終わったのであろう。
さて、ここで取り上げた本だが、その組織工学の片鱗でも把握できれば、と思いつつ読み進めたのであるが、発行された1970年代にはベスト・セラーだったようで、巻末の“あとがき”に “『逆転の発想』は、正・続・続々・新上・新下と今までに5冊発行されて、「発想ブーム」の元祖になったように言われている。”と著者自身の言葉がある。そう言えば、私も“逆転の発想”のこれら正・続・続々・新上・新下のいずれかを読んだのかもしれない。記憶の彼方に、定かでないかすかに そんな印象がある。読み始めると、何よりもその70年代の雰囲気が芬々と甦ってくる。
ここで、標題の“逆転の発想”であるが、何が逆転なのかが気になるところである。これは博士によれば、70年代より以前にはビジネス(事業)は、「ビジネス・マン(企業人)」によって主導され、そのビジネス・マンは「企業」に依拠し、企業は「経済」活動というか「経済」社会の中にあり、その「経済」の背景に「技術」があり、その背景には「科学」があり、その科学は「論理・数学」的なものの上に成立している。その論理は人間の「理性」によるものであり、それは「言語」を使うことで形成され、その「言語」のシステムは その社会の「文化」、「体制」によっている。“そしてその体制は、シンボリックな「オーソリティ(権威)」というものにつながっているのである。” “ところが、現代(この本の時代:70年代)は論理的な考え方、数量的な考え方よりも、フィーリングの時代といわれる。・・・「企業」に対してはマーケットを構成している「消費者」が消費者運動(コンシューマリズム)を起こし、消費者は企業人を信用しないという不信感が起こってくる。また、「経済」においても「くたばれGNP!」という運動が起きるし、「技術」に対抗して「芸術」が台頭してきて『技術が人間を滅ぼしたのだ』と主張し、「哲学・宗教」が『科学者が人類を危険にした』と攻撃し、それでフィーリングと直感が有利になり、情緒的な行動が重要になるのである。”と言っている。これが“逆転の発想”の根拠になっている。
つまり、70年代当時は「ビジネス・マン(企業人)」←「企業」←「経済」←「技術」←「科学」←「論理・数学」←「言語システム」←「文化」←「体制」←「オーソリティ(権威)」が主導していたのが、それに対立する概念の「消費者」←「消費者団体市場」←「反経済」←「芸術」←「宗教・哲学」←「直感・フィーリング」←「情緒」←「行動」←「原始自然」←「反権威」の方に主導権が移りつつあるとして社会現象の解釈を総括しているのである。
こう言えば、日本の最高の選良に対し失礼な表現ではあるが、中々上手く現象を整理しているなぁとの感想だが、中にはこじつけ気味のところもあるように思える部分もある。例えば、現代の世俗的には「宗教・哲学」と「科学」は対立するのもと思われがちだが、実は「宗教・哲学」と「科学」は親和性が非常に高く、場合によっては 厳密にはその区別がつかないことがある。それを糸川博士はどう考えてこのような図式の中に組み込んだのか、まぁそういう社会現象があると言っているのdが・・・。また、後世の後講釈になるが、この70年代からようやく日本社会が モノ不足による供給牽引型から、モノ余りによる消費者中心の需要牽引型の構造に変化しつつあり、五輪音頭で有名な三波春夫の“お客様は神様でございます!”の時代に変化していった冒頭の頃のことである。したがって、供給側の「企業」より、「消費者団体市場」→「消費者」に主導権が移りつつある時代だった。また、当時は既成の権威に盲従していては、社会の矛盾の解決には寄与しないという雰囲気が横溢していて、それが「反権威」という気分に至っていたものだっただが、そこへ上手くつなげて解釈して見せたものだと感心させられる。
ここで、気になるのが「直感・フィーリング」や「情緒」的発想が、最近も世間に横溢していることである。70年代以降 ズーットそうだったのかも知れない。戦前、日米開戦を冷徹な計算に基づかず、反米感情という「情緒」で決した愚を繰り返すのであろうか。当時、昭和天皇が心配して側近に問合せたところ、側近が“(世論は)最早そのような(開戦の)「空気」でございます。”と奏上し、開戦やむなしに傾いたとされる。日本は「空気」つまり情緒で無謀にも開戦し、無条件降伏し崩壊した。戦前の日本はそういう「理性」の働かない状況だったが、現在も非常に感情的な反原発の雰囲気に溢れている。始末に悪いのは、それがあたかも「理性」に裏打されているかのような装いをこらしていることである。つまり、原子力村から村八分にされていた一部の学者が、一見「理性」的に振舞いつつも、その核心部分を感情的に誤魔化した結論を吹聴して回っていることである。特に自然放射能のことを無視して説明せず、人々を煽っていることは意図的としか思えない。放射能ゼロの世界は、この宇宙・自然界のどこにも存在しない。測定すればかならず何らかの放射能がカウントされる。しかも生ある限り、リスクはどこにでもある。絶対安全のリスク・ゼロは死の世界だ。リスクと便益をどう考えるのか、その利害得失を理性的に判定するのが科学の最重要課題のはずだ。
同じようなことは “二酸化炭素地球温暖化説”にも見られる。自分で徹底的に熟慮するのではなく、そういう感情的に煽る人について行く傾向は 絶えることがないのが残念なのだ。IPCCは本当に「権威」として認めてよい団体なのだろうか。戦前にも 大勢の開戦論を煽る人は居たようで、その人々が開戦への“勇ましい「空気」”を醸成したのである。
話が横にそれたようだが、ところで糸川博士は原発をどう見ていたのだろうか。本書には次のような記述があった。“核分裂による原子力発電は根本的にムリがあり、技術は放射性物質の問題を解決し得ないだろう。ウラン235とウラン235をぶつけてエネルギーを得る方法は縫い目のほころびているお手玉を作るようなもので、縫い目から放射性廃棄物がポロポロとこぼれてしまう。これを完全に縫い合わせることはむずかしい。・・・平和利用には不向きであり、平和利用は核融合が完成するまでおあずけ。”と言っている。確かに、核融合とまでは言わずとも、少なくとも核燃料サイクルの技術が完成しない内に、原発の商用化したのは開発戦略の決定的誤りではないかと思われる。
ところで、さすがの糸川博士も 現代では非常に意識されている“(地球)環境”という言葉には留意はしていない。当時、ローマ・クラブが将来の石油不足を煽った見解を発表していて、その後しばらくして、“宇宙船・地球号”という発想が喧伝されるようになった。本書はその少し手前のタイミングで発表されたのであろう、そういう概念はここでは見当たらない。恐らく、この時期ようやく日本が世界の先頭集団に参加し始めた頃で、グローバルな視点は未だなく、米国の社会状況を強く意識するので精一杯であり、また そうすることで先端を走ることが可能な時代であった。そうした、米国の最新動向を細かく紹介する部分がこの本にも随所にあったが、その米国でも“(地球)環境”という発想は未だなかったためであろう。
さて、ここで もう一つ博士の貴重な見解に触れることができる箇所を紹介したい。それは“新商品開発のヒント―失敗しないための8つのチェック・ポイント”として提示された図である。これは今で言う技術経営(MOT)の分野のテーマだ。そこでは、調査段階、検討段階、開発段階、市場に出す前のチェック段階、新商品のテスト及び発表、セールス段階に分けて、それぞれの段階で特に注意するべきことを挙げている。“調査段階”で①マスクド・ニードの発見、②クリエイティブ・ニード時代の終わり、“検討段階”で③社内説得のスケジュール化、“開発段階”で④使用者の言葉をよく理解せよ、“市場に出す前のチェック段階”では⑤社内環境の研究、⑥ブラック・ボックス・アレルギー、⑦卵は分けて入れよ、セールス段階で⑧テレビからFMラジオへ、となっている。
これは、恐らく、戦闘機開発や、ロケット開発の過程で博士が身に着けた貴重な注意事項の整理の結果なのであろう。こういう開発プロセスの概念を、その後、新製品開発に地道を挙げる日本の企業が注目しなかったのには非常に残念である。その後、米国流MOTの死の谷、ダーウィンの海などという概念を得意気に紹介する経営学者は居たが、それ以前に糸川博士は こういった整理をしていて、これの方が日本人にはより馴染み易いのではなかったか、と思うのである。このような日本人の発想が日本人により、発展させられることなく、米国で発想され、発展したMOTに安易に飛びつく傾向が、未だに日本人に染み付いているのが残念なのである。
①の“マスクド・ニード”とは本書によれば“潜在需要”のことだが、ISO9001で言う“暗黙の要求事項”の方が理解し易い。博士は戦闘機の設計に際し、その要求事項をパイロットの“(スピードは遅くても)すれ違いざまの一瞬にして相手を撃ち落す”という言葉では理解できなかったので、そのパイロット達と一緒に生活して“非言語系の表現に注目”したという。そうして、何とか“旋回半径の小さい機体”という工学的言語に翻訳して“隼”を作った。これが④の意味。しかし、実は、こういう当時の日本のパイロットの要求は 世界の戦闘機の設計思想からは外れた傾向の軽戦闘機*重視指向であって、それに気付いた陸軍と中島飛行機はその後、重戦闘機の“鐘馗”を作った。それに対し、海軍はパイロットの要求を重視し過ぎて、軽戦の零式戦にこだわり、その後の米軍の新型機に遅れをとったとされる。使用者(顧客)要求が全てではなく、むしろ それを適切な方向に導くような高度な設計者の意思が重要なこともある。今のソニーの停滞原因は そういう点に気付きがないことにあるのだろう。
*軽戦闘機とは、速度は遅いが、空中戦性能が良く“旋回半径の小さい”戦闘機のことで、“隼”や零式戦がこれに当たる。これに対し、重戦闘機とは、重武装(大口径機関砲等を搭載)で高速の戦闘機を言う。当時の日本のエンジン製造技術では、重戦闘機の仕様を満足することが難しかったという事情もあったとされる。
②の“クリエーティブ・ニード”とは、本書によれば “ドラッカー教授が元祖であり、「社会のニードが見つからなかったら、マーケットを開発し、そこへ売り込んだらどうか」という卓越したアイデア”とのこと。博士が今、大流行のドラッカー教授に 当時既に注目していたとは驚きである。
③の“社内説得のスケジュール”とは、“エジソンが「発明は2%のインスピレーションと98%のパーアスピレーション(反対)」”と言ったが、“私(著者)は、社内の賛成が40%になったらスタートすべきで、もし社内の賛成が60%になったらそれはもう手遅れだ”とのこと。繰り返すが、顧客の要求が全てではないのだ。
⑥の“ブラック・ボックス・アレルギー”とは、一般消費者等の使用者に不安感を与えないように製品の内容・特性を十分に開示するべきだという注意事項。今の原発問題での“放射能汚染”への専門家の説明不足は大衆の不安感を助長している、そういうことへの警告である。⑦の“卵は分けて入れよ”とは、ここではブランド・イメージは分散させて、リスク分散せよとの意味。金融分野では今もよく言われている警句である。⑧の“テレビからFMラジオへ”は、70年代特有の現象で、FMラジオの聴取者が増加した傾向を捉えたもので、それを博士は“視覚から聴覚へ”移る現象と解釈したようだ。これはむしろ、当時の消費者の要求が個別化する傾向を示すもので、今で言う、ネット化に相当するものだろうと思われる。
この本を読むことで 改めて“不易流行”という言葉を 思い起こした。正解を知った上で、答案を読んだようなもので、如何に世の選良・天才といえども、その現象のどれが本質であり、どれがその側面を示しているに過ぎないのかを見分けることが困難であるかを理解できたように思う。ここで、やはり、「反権威」を信条に、自分で徹底的に思考することの重要性を思い知らされた。如何に凡人の足りない脳力であっても、それをフルに使って考えてこそ、自分の見解に責任を持てるのであろう。
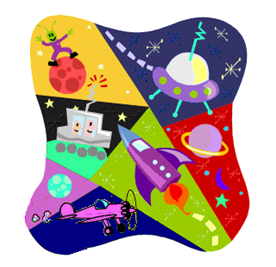
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 最近のソニー... | 消費税増税 » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




