◆内田樹『日本辺境論 (新潮新書) 』
』
これまで、現代日本の若者の間に和風志向や日本回帰の傾向が見られることをいくつかのデータで見てきた。それは、日本の社会や文化をバカにし欧米の文化に憧れ追い求めていた親の世代に比べるとかなり大きな変化である。このような変化をどのような歴史的なスパンで見るかによって、その意味のとらえ方ににかなりの違いが生じる。
論集『論集・日本文化〈1〉日本文化の構造 (1972年) (講談社現代新書) 』(1972年)の中に上山春平の「日本文化の波動」という論文がある。ここで上山は、日本文化がほぼ600年のサイクルで外に向かって開いたり閉じたりを繰り返していると指摘する。
』(1972年)の中に上山春平の「日本文化の波動」という論文がある。ここで上山は、日本文化がほぼ600年のサイクルで外に向かって開いたり閉じたりを繰り返していると指摘する。
まず西暦300年ごろからシナ文化の受け入れが始まり、900年ごろにそれが頂点に達する。894年は、菅原道真が遣唐使の廃止を建議した年だ。その後、仮名文字や大和絵など和風の文化が起こるが、平安時代はまだ唐風の影響をかなり残しての内面化であった。律令制も残り、唐文化に影響された公家文化も続いた。やがて1200年ごろから武士中心の時代に移り、それとともに文化の内面化が進んだ。日本独自の文化が生まれ、たとえば仏教では理論的なものは影をひそめ、浄土真宗や日蓮宗などきわめて単純で、日本の民衆の心をじかにとらえる宗派が活躍した。そうした内面化のクライマックスが1500年ごろであった。(遣唐使廃止の600年後)
その内面化の深まりに前後して、ポルトガル人の種子島漂着(1543年)などをきっかけに今度は西欧文化との接触が始まる。江戸時代は、鎖国体制の中で文化の内面化を進めながらも、出島を通して西欧文化を徐々に受け入れ続ける。そして1800年ごろから明治維新、近代日本へと再び活発に外の世界に対し始め、現代に至るという。彼の理論では、日本が外に開いて受け入れる傾向の頂点は、1500年頃から600年後だとして2100年頃になるし、事実そのように予想するサイクル図が掲載されている。
この論集が発行されたのは40年も前なので、上山はもちろん最近の若者の意識変化など知る由もない。現代は、古代や江戸時代に比べ時代の変化が飛躍的に早まっているから、上山の600年周期説にこだわる必要はまったくない。ただ、日本文化を見ると外来文化をひたすら受け入れた時期とそれを消化した時期とを繰り返してきたことを確認できればよいだろう。江戸時代は、鎖国という政策による遮断だから西欧文明を受け入れて内面化したのではない。しかし鎖国の中で日本独自の庶民文化が熟成されていったのは確かだ。
確認したいのは、かつて日本で唐文化の影響が頂点に達した後、今度はその消化、日本化に向かって進んでいったことだ。それと同じようなことが現代の日本で、今度は西欧文明との関係で起こり始めているのではないか、というのが私の仮説である。前に「その変化は、千年二千年単位の日本歴史のなかでも重要な変化であるような気がする」と言ったのはそのような意味である。つまり、遣唐使の廃止以降に起こった外来文化の内面化と対比できるようなプロセスが、現代の日本で、しかも若者を先頭にして起こり始めているような気がするのである。日本を取り巻く世界情勢の変化がそれを加速している。そのような世界情勢の変化との関係も含めてさらに考察を続けたい。
《関連図書》
『欲しがらない若者たち(日経プレミアシリーズ) 』
』
『ニッポン若者論 よさこい、キャバクラ、地元志向 (ちくま文庫) 』
』
『論集・日本文化〈1〉日本文化の構造 (1972年) (講談社現代新書) 』
』
《関連記事》
★若者の文化的「鎖国」が始まった?今後の計画など(1)
★日本人はなぜアメリカを憎まなかったのか?(1)
★日本人はなぜアメリカを憎まなかったのか?(2)
★日本人が日本を愛せない理由(1)
★日本人が日本を愛せない理由(2)
★日本人が日本を愛せない理由(3)
★日本人が日本を愛せない理由(4)
★クールジャパンに関連する本02
(『欲しがらない若者たち(日経プレミアシリーズ) 』の短評を掲載している。)
』の短評を掲載している。)
これまで、現代日本の若者の間に和風志向や日本回帰の傾向が見られることをいくつかのデータで見てきた。それは、日本の社会や文化をバカにし欧米の文化に憧れ追い求めていた親の世代に比べるとかなり大きな変化である。このような変化をどのような歴史的なスパンで見るかによって、その意味のとらえ方ににかなりの違いが生じる。
論集『論集・日本文化〈1〉日本文化の構造 (1972年) (講談社現代新書)
まず西暦300年ごろからシナ文化の受け入れが始まり、900年ごろにそれが頂点に達する。894年は、菅原道真が遣唐使の廃止を建議した年だ。その後、仮名文字や大和絵など和風の文化が起こるが、平安時代はまだ唐風の影響をかなり残しての内面化であった。律令制も残り、唐文化に影響された公家文化も続いた。やがて1200年ごろから武士中心の時代に移り、それとともに文化の内面化が進んだ。日本独自の文化が生まれ、たとえば仏教では理論的なものは影をひそめ、浄土真宗や日蓮宗などきわめて単純で、日本の民衆の心をじかにとらえる宗派が活躍した。そうした内面化のクライマックスが1500年ごろであった。(遣唐使廃止の600年後)
その内面化の深まりに前後して、ポルトガル人の種子島漂着(1543年)などをきっかけに今度は西欧文化との接触が始まる。江戸時代は、鎖国体制の中で文化の内面化を進めながらも、出島を通して西欧文化を徐々に受け入れ続ける。そして1800年ごろから明治維新、近代日本へと再び活発に外の世界に対し始め、現代に至るという。彼の理論では、日本が外に開いて受け入れる傾向の頂点は、1500年頃から600年後だとして2100年頃になるし、事実そのように予想するサイクル図が掲載されている。
この論集が発行されたのは40年も前なので、上山はもちろん最近の若者の意識変化など知る由もない。現代は、古代や江戸時代に比べ時代の変化が飛躍的に早まっているから、上山の600年周期説にこだわる必要はまったくない。ただ、日本文化を見ると外来文化をひたすら受け入れた時期とそれを消化した時期とを繰り返してきたことを確認できればよいだろう。江戸時代は、鎖国という政策による遮断だから西欧文明を受け入れて内面化したのではない。しかし鎖国の中で日本独自の庶民文化が熟成されていったのは確かだ。
確認したいのは、かつて日本で唐文化の影響が頂点に達した後、今度はその消化、日本化に向かって進んでいったことだ。それと同じようなことが現代の日本で、今度は西欧文明との関係で起こり始めているのではないか、というのが私の仮説である。前に「その変化は、千年二千年単位の日本歴史のなかでも重要な変化であるような気がする」と言ったのはそのような意味である。つまり、遣唐使の廃止以降に起こった外来文化の内面化と対比できるようなプロセスが、現代の日本で、しかも若者を先頭にして起こり始めているような気がするのである。日本を取り巻く世界情勢の変化がそれを加速している。そのような世界情勢の変化との関係も含めてさらに考察を続けたい。
《関連図書》
『欲しがらない若者たち(日経プレミアシリーズ)
『ニッポン若者論 よさこい、キャバクラ、地元志向 (ちくま文庫)
『論集・日本文化〈1〉日本文化の構造 (1972年) (講談社現代新書)
《関連記事》
★若者の文化的「鎖国」が始まった?今後の計画など(1)
★日本人はなぜアメリカを憎まなかったのか?(1)
★日本人はなぜアメリカを憎まなかったのか?(2)
★日本人が日本を愛せない理由(1)
★日本人が日本を愛せない理由(2)
★日本人が日本を愛せない理由(3)
★日本人が日本を愛せない理由(4)
★クールジャパンに関連する本02
(『欲しがらない若者たち(日経プレミアシリーズ)












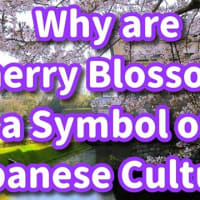
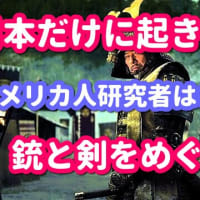

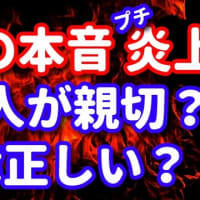




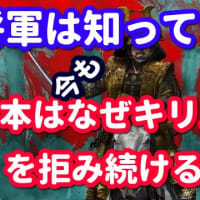






日本の歴史が外来文化の受け入れ期と国風文化の発展期に別れていることには全く異論はありませんし、これからその時期に移り変わっていくんだと言われても、特におかしいとも思いませんが、若者の意識変化の急変(600年と比較して)の説明としてはちょっと弱い気がします。近代から現代にかけての世相の変化に言及しなければならないのではないでしょうか。
次の展開で、おっしゃるような疑問に関する考察をする予定でいました。2・3回にまたがるかもしれませんが、途中で疑問があればぜひお聞かせください。